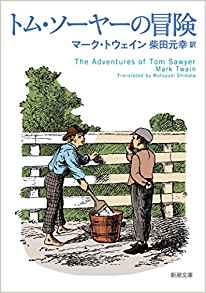嫌な映画である。
ノワールというのは権謀術数、裏切り渦巻くどろどろした世界だが、最後は結局暴力がモノを言うわかりやすいジャンルでもある。
しかしこの映画はどうもすっきりしない。
結論から言うと登場人物が全員嫌な奴だから、ということになると思う。
「全員悪人」というキャッチコピーが非常に印象的な北野武監督の一連の「アウトレイジ」シリーズ。
たしかに凄惨であるし、登場人物全員が悪人だけあってどいつもこいつもろくでなしばかりである。
北野武の美学に則ったラストもいかにも虚無的だ。
しかし不思議と見た後はスッキリする。
映画というのはたいてい登場人物に感情移入してみるものだ。
そうなると俄然物語に興味が出てくる。
身近に感じられてリアルに思えてくる。
手に汗握る。
「アシュラ」でもそのプロセスは起こるわけだが、こちらの映画は登場人物が全員クズなのである。
クズと悪人はちょっと違う。
北野武の描くキャラクターたちは近寄りがたい暴力的な男ばかりだが、どこか愛嬌がある。
会話や仕草に愛嬌と笑いがある。
北野武自身が芸人であることに結びつけるのはいささか短絡的で、たいていどんなノワールでもそんな共感しやすい、というよりは応援しやすいスキが作られている。
もしくは悪いが格好いいのだ。
「アシュラ」の登場人物たちにはそれがない。
主人公はうまく立ち回っているふうだが、実際にはかなりドジを踏んでいるし、病気の女房を看病しながらも浮気はしている。
すぐにカッとなって後先考えずに行動する。
ガキ扱いしていた後輩が上司に気に入られているのが気に食わない。嫉妬する。
悪辣な男パク市長はサイコパスである。
こういうキャラクターは大抵サディストのように書かれることが多い役柄だが、この映画はそんなキャッチーなことはしない。
単に権力と金にとりつかれた汚い男である。
イカれているが魅力的ではないのだ。
検察側のキムも一見寡黙でできる男を装っているが、いざとなると頼りにならない。
情けない。
みんな欲望が人一倍強いわりに、痛がりですぐに保身に走る。
かっこよくない。
ここで描かれているのは確かに邪悪だが、それはフィクションにありがちなロマンティックな狂気ではない。(この言葉は春日武彦さんの本の名前から拝借した。)
私達が抱くありふれた、小心な欲望から生まれた狂気なのだ。
これは見ても面白くない。
むしろ自分が心中密かに抱えている欲望を見せつけられているようで気分が悪い。
かっこよくないクズがかっこよくないクズと争う。
これはすっきりしない。
大量の血、痛々しい暴力という装置によって緊迫感だけが高まっていくが、ラストのラストまでそれが解消されることなく終わる。
私達全員を糾弾しているわけではなかろうが、暴力とはこんなものだ、と汚物を叩きつけているようでその姿勢に顔をしかめながらもどこか楽しくなってしまうのだ。
何回も見たいような映画ではないが、この作りの底意地の悪さにはゾクゾクした。
よいね。
韓国映画はやっぱりやりすぎで、残酷でとても面白い。
2019年5月25日土曜日
リチャード・ブローティガン/芝生の復讐
ブローティガンは大学生の頃に「西瓜糖の日々」を読んだっけ。
だからもう10年以上前か。内容は殆ど覚えていない。
あちらは長編だったが、この本は短編集。
全部で62個の短編が収録されている。どれもとても短い。ショートショートくらい。
どの短編も日常を切り取ったような語り口で、主に現実的な内容について平明な言葉で書かれている。
しかし日記と言うには唐突で脈絡がないし、かと言って幻想文学と言うには現実的すぎる。絶妙なバランスで書かれていて、しかしどれもがオフビートである。
余計なお世話だと思うが、もっと恋愛もしくはセックスについて触れ、生活臭をなるべくげんじておしゃれに仕立て上げたら、あるいはもっと意味の有りそう(で実はまったくない)もっともらしい言葉を充填すれば、もっと大衆の評価を得たのではと。それだとブローティガンが好きな人はそっぽを向くだろうが。
ものによっては一風変わった世捨て人のボヤキ集みたいな趣があり、仕方なく入った冴えないバーに忘れられた使い込まれたノートを読んでいるような趣である。(実際には日記名ているが、きちんとした文学作品である。こんなにも引き込む日記はない。)
もとはといえばマッカーシーの作品に触れて、そのアメリカ像に拭い去ることのできない血の匂いを嗅ぎつけたのが、私がアメリカ文学にハマった要因の一つだ。
風変わりなビートニクだったブローティガンには暴力性がない。しかし私は書き方としてのアメリカ文学を彼の文章に確かに感じ取った。
アメリカ文学(少なくともその一部)は徹底的に肉体的である。
感情表現より肉体表現が優先される。それは運動であり、現象である。
完全に好みだが、私は人の運動を見て(読んで)その人が何を考えているのか、今どんな心情なのかを想像するのが好きなのである。(直接的に心情を描くのは何故かあまり好きじゃない。)
ブローティガンの短編はどれも幻想というには具体的である。いくらか時代が違うものの私達が送っているのとほぼ同じ生活が書かれている。
オフビートでぶっきらぼう。動きは早くないがそこに書かれているのはちょっとした運動たちである。
人の心情を描き出すのは不可能である。だから絵画や音楽は優れている。なぜならそれは「私は悲しい」という気持ちをそのまま表現することができないからだ。だから別の形態をとってそれを表現しようとする。
一方で人の気持ちは複雑で多層的だから、「私は悲しい」と言葉にすることはたしかに真実だが、それが全てではない。大抵は悲しみ以外の気持ちが含まれているからだ。
心情を言葉にすることはわかりやすさを獲得させるが、同時に多層的な感情を固定化しすぎてしまう。
だからブローティガンはそれを直接書くことを良しとせず、感じた気持ちをそれを感じるに至った運動(=日常の一部)をまるごと書くことにしたのだ。
しかし人は生まれたときから連続しているから、1日の1部を切り取って読ませても書いた人と読む人で感じる気持ちは別物である。
この断絶が文学であり、私にはとても面白い。
最後は拳銃自殺したブローティガン。
この本に書いてある小説の中には思わずにやりとさせられるものも多いが、手放しで明るいものはほぼない。
どれもなんとも言えない憂鬱をその内に含んでいる。
毎日を送ることはできる。しかし常に不可解だ。そんな気持ちは単に読みての心情を投影しているだけだろうか。
生きにくさを感じている人はこの本を読んでみると良いかもしれない。
めくるめくスペクタクルはないし、ときによく意味すらわからないが妙に「なんとなくわかるな」と思うのではないかと思う。
だからもう10年以上前か。内容は殆ど覚えていない。
あちらは長編だったが、この本は短編集。
全部で62個の短編が収録されている。どれもとても短い。ショートショートくらい。
どの短編も日常を切り取ったような語り口で、主に現実的な内容について平明な言葉で書かれている。
しかし日記と言うには唐突で脈絡がないし、かと言って幻想文学と言うには現実的すぎる。絶妙なバランスで書かれていて、しかしどれもがオフビートである。
余計なお世話だと思うが、もっと恋愛もしくはセックスについて触れ、生活臭をなるべくげんじておしゃれに仕立て上げたら、あるいはもっと意味の有りそう(で実はまったくない)もっともらしい言葉を充填すれば、もっと大衆の評価を得たのではと。それだとブローティガンが好きな人はそっぽを向くだろうが。
ものによっては一風変わった世捨て人のボヤキ集みたいな趣があり、仕方なく入った冴えないバーに忘れられた使い込まれたノートを読んでいるような趣である。(実際には日記名ているが、きちんとした文学作品である。こんなにも引き込む日記はない。)
もとはといえばマッカーシーの作品に触れて、そのアメリカ像に拭い去ることのできない血の匂いを嗅ぎつけたのが、私がアメリカ文学にハマった要因の一つだ。
風変わりなビートニクだったブローティガンには暴力性がない。しかし私は書き方としてのアメリカ文学を彼の文章に確かに感じ取った。
アメリカ文学(少なくともその一部)は徹底的に肉体的である。
感情表現より肉体表現が優先される。それは運動であり、現象である。
完全に好みだが、私は人の運動を見て(読んで)その人が何を考えているのか、今どんな心情なのかを想像するのが好きなのである。(直接的に心情を描くのは何故かあまり好きじゃない。)
ブローティガンの短編はどれも幻想というには具体的である。いくらか時代が違うものの私達が送っているのとほぼ同じ生活が書かれている。
オフビートでぶっきらぼう。動きは早くないがそこに書かれているのはちょっとした運動たちである。
人の心情を描き出すのは不可能である。だから絵画や音楽は優れている。なぜならそれは「私は悲しい」という気持ちをそのまま表現することができないからだ。だから別の形態をとってそれを表現しようとする。
一方で人の気持ちは複雑で多層的だから、「私は悲しい」と言葉にすることはたしかに真実だが、それが全てではない。大抵は悲しみ以外の気持ちが含まれているからだ。
心情を言葉にすることはわかりやすさを獲得させるが、同時に多層的な感情を固定化しすぎてしまう。
だからブローティガンはそれを直接書くことを良しとせず、感じた気持ちをそれを感じるに至った運動(=日常の一部)をまるごと書くことにしたのだ。
しかし人は生まれたときから連続しているから、1日の1部を切り取って読ませても書いた人と読む人で感じる気持ちは別物である。
この断絶が文学であり、私にはとても面白い。
最後は拳銃自殺したブローティガン。
この本に書いてある小説の中には思わずにやりとさせられるものも多いが、手放しで明るいものはほぼない。
どれもなんとも言えない憂鬱をその内に含んでいる。
毎日を送ることはできる。しかし常に不可解だ。そんな気持ちは単に読みての心情を投影しているだけだろうか。
生きにくさを感じている人はこの本を読んでみると良いかもしれない。
めくるめくスペクタクルはないし、ときによく意味すらわからないが妙に「なんとなくわかるな」と思うのではないかと思う。
ラベル:
アメリカ,
リチャード・ブローティガン,
純文学,
短編集,
本
マーク・トウェイン/トム・ソーヤーの冒険
最近はアメリカ文学を好んで読んでいる。
名作は数あれど必ず名前が上がるのがマーク・トウェインの「ハックルベリィ・フィンの冒険」。読んでみるかと思ったのだがこの話には前日譚というべきもう一つの物語があって、それが「トム・ソーヤーの冒険」。
流石に名前くらい走っているが読んだことがなかった。子供向けの冒険小説だと思っていたから、なんとなく子供の頃に読みそびれてそのままである。
読み始めると作者のまえがきで「この物語は子供が主人公で読者も子供を想定しているけど大人も読んでくれよ」って釘を差してくる。
ほうほう、ってページをめくるとたしかに面白かった。
子供の頃学校からの帰路、道路の上に引かれた白線の上を歩いて家に帰った。この線を踏み外すと死ぬからである。
祖父母の家に向かう新幹線の車窓の外、時速200kmで流れ去るその景色。家々の屋根の上には忍者が走って電車を追いかけていた。
子供の頃にはいろいろな法則があった。それは呪いであり、ルールでもあった。また子供同士の共通の言語でもあった。
人気のない校舎には人知を超えた存在が密かに潜み、また特殊な指の組合せはそれらの魔に抗する力を秘めていた。
それらは他愛のない子供の想像力の産物であったが、しかし私はあれ程真に迫り(私達が語り合った虚構はたしかに真実だった)、そして愉快な空想を物心ついて以来したことがない。
この本にはそんな子供の呪いがこれでもかというくらいふんだんに書き込まれている。
土地も、言語も、肌の色も違うが、それでも彼らの会話の一つづつが懐かしい。
たしかにこれは単に子供に向けて作られた話ではない。なぜなら誰しも一度は子供だからだ。つまりこれは私達全員の物語。
普遍的な子供と大人の心理を扱いつつ、時代性も閉じ込めている。
一言で言うならおおらかさだろうか。
トム・ソーヤーはかなり破天荒な少年である。
多分小学校低学年くらいの年頃なんだと思うが、学校には全然行かないし、手の混んだ悪戯をするし、夜の12時位に家を抜け出したりもする。
やたら行方不明になって村の人総動員でトムを探したりもする。
現代なら超問題児で炎上確定だろうが、この時代だと結構大目に見られて暖かく見守られているといった体。
昔は良かったというのではない。概ね技術の進み具合で生活環境とそれに乗っかる社交性が変遷しているからだ。
現代には現代の呪いがあり、現代のトム・ソーヤーがいるはずだ。
2019年5月19日日曜日
ヘミングウェイ/老人と海
ヘミングウェイは学生の頃に何冊か読んだたことがある。
最近はアメリカ文学に興味があるので読んでなかったこの代表作に手を伸ばした次第。
小説というのは省略だと思う。
面白いと思うのはこれは本当にタイトル通りで、おじいさんが小舟で魚を取りに行くだけの話である。ページ数も少ない。
何かを表現するときに割と話が広がっていく(地理的時間的にだったり、人が死んだりして内容的に劇的にする)小説が多くてその”たくさん”の中に人生のなにかを入れ込んだりることが多いと思っていたのだけど、この話は逆にどこまでもスケールを小さくしていくというか、老人の3日間(ほぼ一人きり)を淡々と書いている。つまり通常の手法と違って、何かを付け足して本質を浮かび上がらしていくのではない。研磨して研磨して余計なものを取り除いて、そこにちょっとだけキラリと光る本質を取り出そうとしているのだ。砂金採りに似ているような作り。
もう一つ印象的なのはタイトルで内容的には「老人と魚」になるはずだが実際には海。
これはわかりやすい、というのもサンチャゴおじいさんが何度も行っているように彼にとって魚というのは友達であって、本当ならそんな崇高な奴らを撮って食う権利は人間などにはないのだ。食うために殺すという仏教的な迷いを抱えつつ、人は海に出ていく。
ただ自然に戦いを挑んでいく人間の姿を賛美しているわけではないのだ。
海の上では何一つうまくいかない、そして友人(サンチャゴ曰く兄弟)と命をとしてやり合う、というのはそのまま人生に拡大解釈することができる。
命がけで獲得した成果も姑息なサメが掠め取っていくように、とかくこの世では真剣勝負すら許されないのだった。
翻訳した福田恆存氏のあとがきが大変面白かった。
この人は基本的にアメリカ文学はヨーロッパのそれに比べるとつまらね〜と思っている人で、最近アメリカ文学にハマっている身としては諸手を挙げて酸性とはならないんだけど、言っていることは興味深い。
とにかく肉体で世界にぶつかっていくのがアメリカ文学で、私にはその無骨さが好きだ。世界を拳で制していくという世界観はむしろ嫌いなのだが、登場人物の心情を読みたくないのだ。想像する楽しみがないから。
そこ行くとこういう小説はやっぱり良いなと思う。
最近はアメリカ文学に興味があるので読んでなかったこの代表作に手を伸ばした次第。
小説というのは省略だと思う。
面白いと思うのはこれは本当にタイトル通りで、おじいさんが小舟で魚を取りに行くだけの話である。ページ数も少ない。
何かを表現するときに割と話が広がっていく(地理的時間的にだったり、人が死んだりして内容的に劇的にする)小説が多くてその”たくさん”の中に人生のなにかを入れ込んだりることが多いと思っていたのだけど、この話は逆にどこまでもスケールを小さくしていくというか、老人の3日間(ほぼ一人きり)を淡々と書いている。つまり通常の手法と違って、何かを付け足して本質を浮かび上がらしていくのではない。研磨して研磨して余計なものを取り除いて、そこにちょっとだけキラリと光る本質を取り出そうとしているのだ。砂金採りに似ているような作り。
もう一つ印象的なのはタイトルで内容的には「老人と魚」になるはずだが実際には海。
これはわかりやすい、というのもサンチャゴおじいさんが何度も行っているように彼にとって魚というのは友達であって、本当ならそんな崇高な奴らを撮って食う権利は人間などにはないのだ。食うために殺すという仏教的な迷いを抱えつつ、人は海に出ていく。
ただ自然に戦いを挑んでいく人間の姿を賛美しているわけではないのだ。
海の上では何一つうまくいかない、そして友人(サンチャゴ曰く兄弟)と命をとしてやり合う、というのはそのまま人生に拡大解釈することができる。
命がけで獲得した成果も姑息なサメが掠め取っていくように、とかくこの世では真剣勝負すら許されないのだった。
翻訳した福田恆存氏のあとがきが大変面白かった。
この人は基本的にアメリカ文学はヨーロッパのそれに比べるとつまらね〜と思っている人で、最近アメリカ文学にハマっている身としては諸手を挙げて酸性とはならないんだけど、言っていることは興味深い。
とにかく肉体で世界にぶつかっていくのがアメリカ文学で、私にはその無骨さが好きだ。世界を拳で制していくという世界観はむしろ嫌いなのだが、登場人物の心情を読みたくないのだ。想像する楽しみがないから。
そこ行くとこういう小説はやっぱり良いなと思う。
ラベル:
アーネスト・ヘミングウェイ,
アメリカ,
純文学,
本
2019年5月12日日曜日
鼓直編/ラテンアメリカ怪談集
自宅の小さい部屋の閉じこもる私にとってラテンアメリカは未知の土地である。
メキシコでは麻薬戦争が常態化し、そして人々は死者の日やサンタ・ムエルテに代表されるように死にたいして独特の信仰を持っているとか。
それではキューバでは?ウルグアイでは?
全然わからない。
作家で言えば、ボルヘス、マルシア・ガルケス、バルガス=リョサ、コルタサルくらいか。
そんな私にとっての暗黒大陸であるラテンアメリカの、更に怪談とくれば買わないわけにはいけない。
死者が鬼として起き上がる中国の怪談、古式騒然たる荘厳な屋敷に曰くある幽霊が出現する英国怪異、表情豊かな妖怪たち恨みを持って、または死んだ女の幽霊が人を脅かす本邦の怪談。
どうもラテンアメリカの怪談はこれらとは合致しないようだ。
いわゆる私達の頭の中にあるオールドスクールな「怪談」の範疇に入るのは意外に少なくて、ウルグアイのキローガの「彼方へ」、メキシコの作家フエンテスの手による「トラクトカツィネ」のみだろうか。(これが一番幽霊譚かなと。個人的には抜群に怖く、そして面白い。)
いわゆる幻想文学という範疇に入るような作風の物語が多いが、面白いのは概ねどの話にも「死」の要素が入っている。
死を描くってどういうことだろう?
ただの死はニュースで聞く海の向こうの死と同じだ。痛ましいが数値でしかない。
つまり物語において死を描くというのは生を描くことだ。
わかりやすいのは日本的な幽霊譚で、多くの物語がなぜ彼もしくは彼女が幽霊となったのか、というのを解き明かすことが物語の軸になっている。(「モノノ怪」という非常に優れたアニメを思い出す。)
「断頭遊戯」や「魔法の書」などはそんな死に至る(あるいは至らない)奇妙な、数奇な運命をたどる生を描写していく。
幽霊にしても死後存在し続けるというのは生きている人たちにとっては慰めである。
そこをバツリと断ち切るのがラテンアメリカの死生観なのだろうか。だとしたらだいぶ救いがない。
そういえばこの本には天国や地獄は出てこない。彼らはいまある生だけがすべてであって、死後人間は何も残さずにただ消えると考えているなら非常に面白い。
死の意味が非常に重たくなり、同時に反対の要素である生もまた非常に貴重なものになっていくからだ。
死に侵食されるというのは生が危うくなることで、これは「ジャカランダ」(これは正統派の幻想)、「ミスター・テイラー」(これは風刺だが死が生を制圧している)などで取り扱われている。
「幽霊なんていないさ」しかし、死が確実に人間の性に影響を与えそれを幽霊と呼ぶこともできるかもしれない。「騎兵大佐」はそんな死が擬人化されているようにも読める。
死者たちがひょうきんに出歩いているイメージがなんとなくラテンアメリカにはあったけど、この本を読むとどうもちょっとそうでもないみたいだ。
この未知の土地の文学をもっともっと読んでみたい。
幽霊にしても死後存在し続けるというのは生きている人たちにとっては慰めである。
そこをバツリと断ち切るのがラテンアメリカの死生観なのだろうか。だとしたらだいぶ救いがない。
そういえばこの本には天国や地獄は出てこない。彼らはいまある生だけがすべてであって、死後人間は何も残さずにただ消えると考えているなら非常に面白い。
死の意味が非常に重たくなり、同時に反対の要素である生もまた非常に貴重なものになっていくからだ。
死に侵食されるというのは生が危うくなることで、これは「ジャカランダ」(これは正統派の幻想)、「ミスター・テイラー」(これは風刺だが死が生を制圧している)などで取り扱われている。
「幽霊なんていないさ」しかし、死が確実に人間の性に影響を与えそれを幽霊と呼ぶこともできるかもしれない。「騎兵大佐」はそんな死が擬人化されているようにも読める。
死者たちがひょうきんに出歩いているイメージがなんとなくラテンアメリカにはあったけど、この本を読むとどうもちょっとそうでもないみたいだ。
この未知の土地の文学をもっともっと読んでみたい。
Mateus Asato -LIVE in JAPAN 2019-@下北沢Garden
twitter好きなのは色んな人のおすすめ(音楽、食べ物、絵画、映画、漫画…)を知ることができるからだ。
音楽は自分で掘るのが一番、でも私は人のおすすめを聞くのが好きだ。何故かと言うと興味が広がるからだ。自分の感覚ではスルーしてしまう音楽も、特に興味のある人(友人、知り合い、好きなバンドマン)が勧めているものはその人達なりのフィルータを通して新しい可能性になる。
私の会社の上司は大概頭がおかしいのだが、自身演奏することもあって音楽が好きである。そんな上司がおすすめするのがこのMateus Asatoだった。若干25歳のギタリスト、活動の場はtwitterやyoutubeなど。確実に新しい世代のミュージシャンなのだろう。面白いのは音源がほぼ皆無(コンピレーションに1曲のみ提供したものが流通しているのみ)なのにギターメイカーから彼のシグネイチャーモデルが発売されていること。
私は中学生の頃Sex Machinegunsにハマっていた。初めて買った洋楽のCDはBuckcherryではなくて確かJohn Sykesだったと思う。とはいえほぼほぼテクニカル系の音楽は聞かないできた。一回Nunoの来日を見に行ったことがあるけど、高音がきつい上にこれでもかというくらい弾きまくる(大抵のファンは喜ぶんだろうが、私は「Crave」などどちらかというとNunoのソングライティングの方に惹かれていたのです。)ので途中でちょっとうーむとなってしまった。
たしかに普段聞き慣れないジャンルではある、しかしメタルコアとクラシック音楽、そして日本のフォーク(長渕剛、吉田拓郎など)をこよなく愛する上司が押すくらいなら間違いないだろうということでライブへ。(平日にライブのために会社を抜け出すのは困難を極めるが、上司が一緒だととても安心だということを皆さんはご存知だろうか。)
下北沢のライブハウスには何回か行ったことがあるが、Gardenは初めて。
きれいで私がいつも行くようなライブハウスに比べると大きめ。
客はかなりはいっていて、男性がとても多め。見るからに学生、スーツ姿のサラリーマン、年配の方、バンドマンっぽい雰囲気の人、いろいろなカテゴリが参集していたがなんとなくみんなギターを弾きそう、という雰囲気が共通していて面白い。
やや押してライブがスタート。
以前の来日(上司は2回ともいったらしい)はマテウス本人のみだったが、今回はドラム、ベースとギターのマテウスの三人でバンド編成。(いずれもバカテク。)
この日のマテウスは終始リラックスした感じ。
どうなるもんだろう?という感じだったが始まってみるとこれがとても良かった!
まずは彼の表現力に驚かされる。とてもメロディアスでエモーショナルだ。こんな表現はどんな音楽にも当てはまるから意味がないが、まずこう描いておく。
通常の曲というのはテーマ(サビ)があってそれの前にいくつかの提携のメロディが配置されている。これはポップスもそうだが、メタルだろうがハードコアでもほぼ同じやり方が踏襲されている。ところがマテウスはそうではない。もちろんテーマはあるのだろうが、もっともっと自由に弾く。
(明確に継ぎ目がわからないのでなんとも言えないが)おそらく1曲はかなり長いと思う。例えば5個以下のリフとメインとなるメロディを作ってそれを回していく、というのではない。全部が連続していて、そして同じようなフレーズはあまり出てこない。
相当プログレッシブかというとそんな気がしない。相当テクニカルではある。しかし大仰な感じはまったくない。フレーズ自体が複雑でもリズムがシンプルでこまめに変えていかないからだと思う。
ギターの音色は弱めの歪み、リバーブなどの空間系をほんのちょっとかけるのみでごまかしの聞かないロウ(粗いではなく生々しい)なやつ。
音の粒がとにかくきれいで、雑味が入らない、音量が揃っているというよりは完全にアタックの強弱でコントロールされている、音はのっぺりしていなく、スライドやチョーキングで意図的に揺らされている。粘り気があり、ゆらぎがある。例えるならこうだ。ある晴れた日にお天気雨が降り、窓についた雨粒が流れるのを眺めているような。細かく、小気味の良い音が鈴なりになっている。
ピック弾きと指弾きを流れるように切り替え、単音、コード、カッティング、速弾き、スライド、チョーキング、ハーモニクスを駆使して曲を組み上げていく。(技術的な描写力のなさが歯がゆい。)どれにも固執することがなく、ただ必要だからそこにあるというテクニックだ。それでいて高等技術の博覧会的な要素はまったくない。全ては良い曲のため。
ボーカルが担当していたメロディラインをギターが担当する、または轟音ギターで重々しくもシンプルなメロディを補填するといったポストロック感はなし。
曲によってはかなりロックであり、ロック・ミュージックのギター解釈。それが結果的に典型的なロックの枠を出ている、といった趣。
音はきれいだがBGMとして耳から耳に素通りしていく小奇麗なそれではない。かなり実験的でそして挑戦的だ。
聴いてて思ったのは音楽は数学だ。
私も楽譜はみたことがあるが、オタマジャクシの種類に頓着したことがない。実際には4分音符、8分音符、休符と様々な種類があり、どんな音が鳴るかを示している。
一定の時間という概念、小節で切り取った時間を更に音符が分割していく。
マテウスはここが匠で、小節を自由自在に切り刻んでいく。たとえば小終わりの方でつじつまを合わせるみたいなのはない。音の数が増えたり減ったり、縦横無尽である。これによってメタルののっぺりした速弾きとは異なり、音にうねりが生まれてくる。
マシンみたいに正確ってなぜか芸術の分野ではむしろ侮蔑的に使われることがあるが、確実にそんなことはない。技巧が表現力を表現力が感動を生むのだ。
マテウスは常に良い顔でギターを弾く。よく白目をむいている。気持ち良いのかもしれない。終始楽しげで、そんな彼の人柄がよくよくにじみ出たライブだった。
ちなみに上司は痛く感動し、性的興奮すら覚えたと言っていた。やはりギターを弾く人間は頭がオカシイなと思った。
音楽は自分で掘るのが一番、でも私は人のおすすめを聞くのが好きだ。何故かと言うと興味が広がるからだ。自分の感覚ではスルーしてしまう音楽も、特に興味のある人(友人、知り合い、好きなバンドマン)が勧めているものはその人達なりのフィルータを通して新しい可能性になる。
私の会社の上司は大概頭がおかしいのだが、自身演奏することもあって音楽が好きである。そんな上司がおすすめするのがこのMateus Asatoだった。若干25歳のギタリスト、活動の場はtwitterやyoutubeなど。確実に新しい世代のミュージシャンなのだろう。面白いのは音源がほぼ皆無(コンピレーションに1曲のみ提供したものが流通しているのみ)なのにギターメイカーから彼のシグネイチャーモデルが発売されていること。
私は中学生の頃Sex Machinegunsにハマっていた。初めて買った洋楽のCDはBuckcherryではなくて確かJohn Sykesだったと思う。とはいえほぼほぼテクニカル系の音楽は聞かないできた。一回Nunoの来日を見に行ったことがあるけど、高音がきつい上にこれでもかというくらい弾きまくる(大抵のファンは喜ぶんだろうが、私は「Crave」などどちらかというとNunoのソングライティングの方に惹かれていたのです。)ので途中でちょっとうーむとなってしまった。
たしかに普段聞き慣れないジャンルではある、しかしメタルコアとクラシック音楽、そして日本のフォーク(長渕剛、吉田拓郎など)をこよなく愛する上司が押すくらいなら間違いないだろうということでライブへ。(平日にライブのために会社を抜け出すのは困難を極めるが、上司が一緒だととても安心だということを皆さんはご存知だろうか。)
下北沢のライブハウスには何回か行ったことがあるが、Gardenは初めて。
きれいで私がいつも行くようなライブハウスに比べると大きめ。
客はかなりはいっていて、男性がとても多め。見るからに学生、スーツ姿のサラリーマン、年配の方、バンドマンっぽい雰囲気の人、いろいろなカテゴリが参集していたがなんとなくみんなギターを弾きそう、という雰囲気が共通していて面白い。
やや押してライブがスタート。
以前の来日(上司は2回ともいったらしい)はマテウス本人のみだったが、今回はドラム、ベースとギターのマテウスの三人でバンド編成。(いずれもバカテク。)
この日のマテウスは終始リラックスした感じ。
どうなるもんだろう?という感じだったが始まってみるとこれがとても良かった!
まずは彼の表現力に驚かされる。とてもメロディアスでエモーショナルだ。こんな表現はどんな音楽にも当てはまるから意味がないが、まずこう描いておく。
通常の曲というのはテーマ(サビ)があってそれの前にいくつかの提携のメロディが配置されている。これはポップスもそうだが、メタルだろうがハードコアでもほぼ同じやり方が踏襲されている。ところがマテウスはそうではない。もちろんテーマはあるのだろうが、もっともっと自由に弾く。
(明確に継ぎ目がわからないのでなんとも言えないが)おそらく1曲はかなり長いと思う。例えば5個以下のリフとメインとなるメロディを作ってそれを回していく、というのではない。全部が連続していて、そして同じようなフレーズはあまり出てこない。
相当プログレッシブかというとそんな気がしない。相当テクニカルではある。しかし大仰な感じはまったくない。フレーズ自体が複雑でもリズムがシンプルでこまめに変えていかないからだと思う。
ギターの音色は弱めの歪み、リバーブなどの空間系をほんのちょっとかけるのみでごまかしの聞かないロウ(粗いではなく生々しい)なやつ。
音の粒がとにかくきれいで、雑味が入らない、音量が揃っているというよりは完全にアタックの強弱でコントロールされている、音はのっぺりしていなく、スライドやチョーキングで意図的に揺らされている。粘り気があり、ゆらぎがある。例えるならこうだ。ある晴れた日にお天気雨が降り、窓についた雨粒が流れるのを眺めているような。細かく、小気味の良い音が鈴なりになっている。
ピック弾きと指弾きを流れるように切り替え、単音、コード、カッティング、速弾き、スライド、チョーキング、ハーモニクスを駆使して曲を組み上げていく。(技術的な描写力のなさが歯がゆい。)どれにも固執することがなく、ただ必要だからそこにあるというテクニックだ。それでいて高等技術の博覧会的な要素はまったくない。全ては良い曲のため。
ボーカルが担当していたメロディラインをギターが担当する、または轟音ギターで重々しくもシンプルなメロディを補填するといったポストロック感はなし。
曲によってはかなりロックであり、ロック・ミュージックのギター解釈。それが結果的に典型的なロックの枠を出ている、といった趣。
音はきれいだがBGMとして耳から耳に素通りしていく小奇麗なそれではない。かなり実験的でそして挑戦的だ。
聴いてて思ったのは音楽は数学だ。
私も楽譜はみたことがあるが、オタマジャクシの種類に頓着したことがない。実際には4分音符、8分音符、休符と様々な種類があり、どんな音が鳴るかを示している。
一定の時間という概念、小節で切り取った時間を更に音符が分割していく。
マテウスはここが匠で、小節を自由自在に切り刻んでいく。たとえば小終わりの方でつじつまを合わせるみたいなのはない。音の数が増えたり減ったり、縦横無尽である。これによってメタルののっぺりした速弾きとは異なり、音にうねりが生まれてくる。
マシンみたいに正確ってなぜか芸術の分野ではむしろ侮蔑的に使われることがあるが、確実にそんなことはない。技巧が表現力を表現力が感動を生むのだ。
マテウスは常に良い顔でギターを弾く。よく白目をむいている。気持ち良いのかもしれない。終始楽しげで、そんな彼の人柄がよくよくにじみ出たライブだった。
ちなみに上司は痛く感動し、性的興奮すら覚えたと言っていた。やはりギターを弾く人間は頭がオカシイなと思った。
2019年5月5日日曜日
フォークナー/フォークナー短編集
同じアメリカの南部を描いた短編作品でも、1902年生まれのスタインベックの「朝めし」とフ1897年生まれのォークナーのこの短編集に収録された作品では雲泥の差がある。(二人共にノーベル文学賞を受賞している。)
前者が貧しいながらもアメリカの息を呑む光景の中での、たくましくも優しい人間の絆を美しく描いているのに対して、フォークナーの描く短編はどれも峻厳な景色の中で人間同士が憎み合い、そして時に殺し合う。
コップに半分入れられた水を見て何を思うかが千差万別のように、アメリカの土地と生活を見て、スタインベックとフォークナーは全く異なる感想を抱いたようだ。ただしふたりとも当時のアメリカという土地は生きるには大変厳しい土地だと考えているところは共通している。
苦境に立たされる貧しい者たちの尊厳を描いたスタインベック、一方フォークナーは前任の不在、とくに「サンクチュアリ」を読んで感じたのはフォークナーは悪人以上に平凡な人こそ諸悪の根源である衆愚であり、彼らを憎んでいたのではないかということだ。ここではキリスト教というのは愚か者の大義、つまりいわれのない差別、不正や暴力の言い訳にされている。フォークナーは教会に通っていたのだろうか???
この本には嫉妬に狂って男を殺す夫、執着心から婚約者を殺す女、身持ちの悪い黒人女、黒人にレイプされたと偽証する年増の女、偽証に基づき黒人をリンチして殺す白人男などなど、南部のいやらしさがこれでもかというくらいドロドロ描かれている。
ここでは教会、牧師、神父や聖書が役に立った試しがない。(それらしい描写があったかも怪しい。)
黒人を搾取し、差別し、そして殺す白人と、常に被害者として黒人、という構図でもない。もちろん状況が賢くなることを許さないのだが、学がない黒人の愚かさもフォークナーは克明に描いていく。
彼は一体どんな目でアメリカを見ていたのか???
彼の前では人は肌の色、性別、老若とわずすべてが愚かで救いがない。
死んだ目で米を見ていたのだろうか、いやおそらく違うだろう。自分も骨の髄までそんな南部人であることを否が応でも自覚させられ、その矛盾の中でこれらを生み出したのだ。
アメリカは呪われた土地だ、暴力と死で溢れているというのはいろいろな意味で間違いだ。(少なくともいくらかは間違いだ。)
スタインベックが描いたように美しい光景があったはず。フォークナーもそんな一瞬を必ず目にしたはず、香りを嗅いだはず、舌で味わったはずである。
個人的には言われているほどに「八月の光」のヒロインに陰に対する陽を感じられない。
しかしこの本の「バーベナの匂い」「納屋は燃える」には明らかに陰に対する陽が書かれている。一つは非暴力であり、一つ糾弾だ。
共通しているのは因習、つまり大多数(=衆愚)の法則に対する抵抗であること、自分の頭で考え、それに自分の手足で立ち向かうこと。
2つの小説の中でこのささやかな反乱を起こすのは二人の若者である。これがそのままフォークナーの希望になるだろう。
前者が貧しいながらもアメリカの息を呑む光景の中での、たくましくも優しい人間の絆を美しく描いているのに対して、フォークナーの描く短編はどれも峻厳な景色の中で人間同士が憎み合い、そして時に殺し合う。
コップに半分入れられた水を見て何を思うかが千差万別のように、アメリカの土地と生活を見て、スタインベックとフォークナーは全く異なる感想を抱いたようだ。ただしふたりとも当時のアメリカという土地は生きるには大変厳しい土地だと考えているところは共通している。
苦境に立たされる貧しい者たちの尊厳を描いたスタインベック、一方フォークナーは前任の不在、とくに「サンクチュアリ」を読んで感じたのはフォークナーは悪人以上に平凡な人こそ諸悪の根源である衆愚であり、彼らを憎んでいたのではないかということだ。ここではキリスト教というのは愚か者の大義、つまりいわれのない差別、不正や暴力の言い訳にされている。フォークナーは教会に通っていたのだろうか???
この本には嫉妬に狂って男を殺す夫、執着心から婚約者を殺す女、身持ちの悪い黒人女、黒人にレイプされたと偽証する年増の女、偽証に基づき黒人をリンチして殺す白人男などなど、南部のいやらしさがこれでもかというくらいドロドロ描かれている。
ここでは教会、牧師、神父や聖書が役に立った試しがない。(それらしい描写があったかも怪しい。)
黒人を搾取し、差別し、そして殺す白人と、常に被害者として黒人、という構図でもない。もちろん状況が賢くなることを許さないのだが、学がない黒人の愚かさもフォークナーは克明に描いていく。
彼は一体どんな目でアメリカを見ていたのか???
彼の前では人は肌の色、性別、老若とわずすべてが愚かで救いがない。
死んだ目で米を見ていたのだろうか、いやおそらく違うだろう。自分も骨の髄までそんな南部人であることを否が応でも自覚させられ、その矛盾の中でこれらを生み出したのだ。
アメリカは呪われた土地だ、暴力と死で溢れているというのはいろいろな意味で間違いだ。(少なくともいくらかは間違いだ。)
スタインベックが描いたように美しい光景があったはず。フォークナーもそんな一瞬を必ず目にしたはず、香りを嗅いだはず、舌で味わったはずである。
個人的には言われているほどに「八月の光」のヒロインに陰に対する陽を感じられない。
しかしこの本の「バーベナの匂い」「納屋は燃える」には明らかに陰に対する陽が書かれている。一つは非暴力であり、一つ糾弾だ。
共通しているのは因習、つまり大多数(=衆愚)の法則に対する抵抗であること、自分の頭で考え、それに自分の手足で立ち向かうこと。
2つの小説の中でこのささやかな反乱を起こすのは二人の若者である。これがそのままフォークナーの希望になるだろう。
ラベル:
アメリカ,
ウィリアム・フォークナー,
純文学,
短編集,
本
ザ・フォーリナー
昔12チャンネルでお昼から2時間吹き替え映画を毎日放送していたのを覚えている人は多分私と同じくらいの年齢の方だと思う。
その時分でも新しいとは言えない(おそらく権利費用が安いからだと思うけど)映画をただただ放送していて、小学生の自分は特に長期の休みのときにはよくそれを見ていた。ほぼ毎日かな?近所に友達がいなかったもんで。
で、よく放送されることもあって印象にあるのはジャッキー・チェン主演の映画である。「酔拳」「ポリス・ストーリー」「スパルタンX」などなど。当時の私は手に汗握ってみたし、笑ったものだ。
当時からだいぶ時間が経ち、上記の映画の記憶も全然曖昧なのだが(タイトルごとに区別つかないグチャッとした記憶になってる。)、自分のなかではジャッキー・チェンというのはスターである。いつもちょっとすきがあって、時に情けなかったりするが、正義のために戦う男。
そんなジャッキーが今までとは違う役柄に挑戦ってことで前々から気になっていた「ザ・フォーリナー」を見に行った。これは原作があるそうなのだがあえて読まないことに。
映画の中ではイギリス、ロンドンで中華料理店を営む初老の男になったクワンことジャッキー。テロでたった一人の家族である娘を失ったクワンは犯人探しに乗り出す。
という筋。早々に涙を流し悲しんだあとは、悲しみを封印し、娘を殺された怒りを通り越した無の表情で敵を襲う。とにかく行動が速い。そして呵責がない。手段を選ばず、目的に向かって一直線に愚直に行動する。無表情も相まってサイコパスにも見える。
良かったね。私は贔屓目があるから正当に判断できないかもしれないが、面白かった。
異質なジャッキーもきちんと描けている。彼の持つ非人間性は人間的な感情に基づいているからだ。スイッチのオンオフのようにキャラクターが切り替わるのも特殊部隊の経験が生んだモンスターと言う感じで良かった。
なにより途中で気がつくのだが、実は破滅的な攻めも抑制が効いている。それが彼に陰湿な印象を与え、それがなおさら怖い。
本当の敵以外は不殺を貫く、それも格好いい。はじめの爆破から「これは、イカれてますわ…」と思ってしまうんだけど、そうじゃない。行動からクワンの心理状態と覚悟が読み取れる。そうするとジャッキーの無の表情に対する印象も見ている間に変わってくる。こういうの楽しいよね。
ひょこひょこしたいかにもおじいちゃんぽいあるき方や、強引な割に礼儀正しい態度も示唆的だ。ここらへんの描写はなにより一辺倒でなく、そしてくどくなく簡潔で好きだ。
ジャッキー・アクション(私が今作った言葉)といえばそこら辺に落ちているものを戦闘に利用するってのがあると思うんだけど、今作でもそれは健在。
ジャッキーは明らかに強いのだけれど演技しているときは必死の形相で、今作は特に痛みの描写は結構すごい。ただすかっとするんじゃない、見てて「いてて」ってこっちが顔をしかめてしまう。
ジャッキー・アクション(私が今作った言葉)といえばそこら辺に落ちているものを戦闘に利用するってのがあると思うんだけど、今作でもそれは健在。
ジャッキーは明らかに強いのだけれど演技しているときは必死の形相で、今作は特に痛みの描写は結構すごい。ただすかっとするんじゃない、見てて「いてて」ってこっちが顔をしかめてしまう。
復讐劇なのだが、どちらかというとピアーズ・ブロスナン演じる副首相ヘネシーとの対決に焦点を絞っているのが良かった。
ヘネシーは権力、家族、仲間、そして土地に対する由緒を”持っ”ている男らしい男で、外国人で移住してきて慎ましく暮らし、そして今家族を失ったジャッキー演じるクワンとは正反対。
クワンがヘネシーを追い詰めていき、次第に彼の力=持っていたものが剥がれ落ちていく。そしていよいよ対決という構図になる。
敵側の人間はクワンのことを「チャイナ・マン」と呼ぶ。
フォーリナーである彼(ら)は表情が読みにくいし、何考えているかわからない、というところからこの物語が生まれたのかもしれない。
原作者Stephen Leatherはイギリスの方でこの物語の原題は「The Chinaman」。
私が子供の頃はまだIRAのニュースが結構耳に入ってきた。
最近はとんと聞かないような気がしていたのだが、もちろん血で血を洗う抗争があっという間に終わるわけもなく、いまでも続いているのかと思うと暗澹たる気持ちになった。
日常生活を害すテロリズム、破壊行動は嫌なものです。
私達世代、具体的には30〜40代くらいで子供の頃にジャッキー・チェンの映画を見て興奮した方は是非どうぞ。
ちなみにエンディングに流れる主題歌はジャッキー・チェン自らマイクを取って歌ってる。これはホント最高。
登録:
投稿 (Atom)