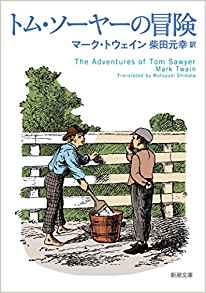この一冊は日本の怪談であること、に加えて場所に係る怪談であること、の条件で蒐集した短編が収められている。
収録作品は下記の通り。
- 日影丈吉「ひこばえ」
- 筒井康隆「母子像」
- 佐藤春夫「化け物屋敷」
- 吉田健一「化けもの屋敷」
- 吉行淳之介「出口」
- 森鴎外「百物語」
- 稲垣足穂「山ン本五郎左衛門只今退散仕る」
- 内田百閒「遊就館」
- 小泉八雲「狢」
- 森鴎外「鼠坂」
- 大岡昇平「車坂」
- 豊島与志雄「沼のほとり」
- 幸田露伴「幻談」
- 火野葦平「紅皿」
- 小田仁二郎「鯉の巴」
- 笹沢左保「老人の予言」
- 都筑道夫「怪談の作法」
- 武田百合子「怖いこと」
- 小沢信男「わたしの赤マント」
- 半村良「終の岩屋」
- 泉鏡花「雪霊続記」
- 澁澤龍彥「髑髏盃」
一体幽霊や化け物というのは日中堂々と出るものではない。
柳の下の幽霊を出すわけでもなく、たいてい恐ろしいものというのは暗い夜に人気がない(例えば墓場のような)特定の場所に現れるものだ。
つまり逆に言えば化け物というのは出現するには一定の条件が必要だと言える。
猫は人ではなく家に懐く、といういうが幽霊は人に憑く場合もあるが、大抵は場所に憑くものだ。
古今の怪談を思い返してみるとほとんどが「行くな」という場所に足を踏み入れて幽霊と出会い、それで憑かれると決まっている。
水場、墓場、古色蒼然たる屋敷でも、暗くジメジメした地下室でも、落書きだらけの廃墟でも良い、とにかく普通ではない建物や場所、そんなところがホラーの舞台になる。
このアンソロジーはそんな「場所」を集めた一冊。
いわば日常から離れた異界があって、知らないうちにそこに入り込んでいる。
そこでは日常的な法則から解き放たれているため、迷い込んだ人間はそこで常ならぬものを目にするというわけだ。
やはり家がわかりやすい。
⑤は象徴的でつまり外から見ても閉ざされていて見えない家の中でなにか異常が進行しているというもの。
⑰は舞台がタクシーでその近代的な時代設定が目を引くが、ある意味基本に忠実で怪談をどこまで縮めるか、という点でも非常に狭く距離が近いタクシーというのは面白い。
②も近代的だが、怪異がSF的なのは作者故か。
一方でthis is 怪談(kwaidan)の⑨八雲の物語はこれは外での出来事だが、開放的ではなくてむしろ坂を登っていくと真っ暗闇の別世界にたどり着いている。
㉑もやはり雪に振り込められて迷い込んだのが異界というパターン。天守物語もそうだけど異界を書くのはやはりお手の物という感じ。
面白いのは因縁のある場所を書いた作品が、場所をテーマに敷いたアンソロジーにしては意外に少ないこと。はっきりしているのは③⑧くらいか。
⑦は様々な人が元ネタにしている稲生物怪録ものだが、これは怪異は外からくる。
⑩と⑪は非常に話の筋が似ていいて、おいてきたと持った過去に復讐される話。いずれも坂が舞台だが、ここに遠く離れた異国の幽霊がいわば訪って復讐を果たしていく。
幽霊たちはいるだけでない、来るのでもある。
個人的に特に面白かったのが④。
アンチ怪談という意味では⑦に似ているがもっと強い。
愛の反対は無関心と入ったものが、幽霊にだって一番きついのは無視されることである。
怖がらない、気にしない、相手にしない、これは幽霊には効く。ただ同時に物語にならないからホラーでは禁じ手である。
④に関しては主人公は幽霊を気にしない。無視するのではない。普通に受け入れちゃう。お化け屋敷で幽霊と暮らしちゃう。言葉にしないが結構いいものだな〜なんて思っている風である。
で、一方の幽霊たちもそんな主人公と暮らしてなんか幸せそうである。
幽霊は怖がらせようとしていて、人間はひたすら怖がる、という常識をさらっと覆し、更に別逆張りで奇をてらっているわけではない。
いろいろな人間がいるようにこういう幽霊がいても良いよなと思わせる。