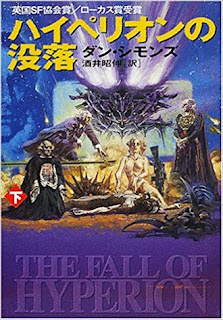日本の作家の短編小説集。
椎名誠さんの超常短編集の一冊。中古で購入。タイトルはもちろんヘンリ・ジェイムズの短編小説から取っているのだろう。
前回紹介した「鉄塔のひと」はSFの要素があっても結果的にSFと呼べる作品は収録されていなかったが、この本ははっきりSFと言い切っても良い作品が収録されている。あとはこの作者に対しては珍しく”しかけ”のあるホラー風の短編や、軽妙で軽薄な文体を活かしたファニーな短編など。何と言っても目玉はやはりこの間紹介したSF長編「水域」の原型の短編バージョンの「水域」だろう。長編の大体中盤までの物語を大まかに書いてある。面白いのは主人公の設定で、こちらだと結構熟練の旅人であるのに対して、長編に書き直した方はいっこの青春小説と言って良いくらい主人公が若く、そして青く設定されている。こうした結果読者の裾野を広げると行った意味もあるだろうが、むしろ旅の危うさ、そして初々しさというのが圧倒的に強調されており、冒険小説というのはその主人公はある程度無知(かつ才気と情熱に横溢している)な人のほうが面白くなるのだな、と妙に納得してしまった。
私もかつてはそうだったが、椎名誠さんというとやたらがっしりしていてCMとかに出ている作家のひとというイメージで(外国で馬に乗っていて「シーナさん」「シーナさん」と呼びかけられる何かのCMのことをおぼろげに覚えている。)、それから実際に椎名さんが書いた本を読むと、「うおお本当に作家だったのね」というギャップめいた驚きに打たれるものだ。渡しの場合はでもやはり結構健康的な見た目にあった強靭な内容だな〜と思ったのだが、幾つか作品を読むとただただ牧歌的な風景の中で造語にまみれたへんてこな小説を書くだけのひとではないということに気付かされる。おそらく意識的にあまり出さないようにしているが、やはりその底にはどろりとした凄みや怖さというのがあって、それがたまにその作品に滲み出しているのを感じるのである。はじめから剣呑であれば(とくに直接的な脅威でないほどに)人間というのはそれに適応してしまうものなので、逆に言うとこうやってたまに垣間見えるほうがその恐ろしさが強調されるものである。この短編集でも、そのヤバさみたいなのが幾つかの作品で垣間見えて面白い。「ニワトリ」の滑稽な状況に背後にある男の身勝手さ(これは仕事でいつも家を留守にして置いてけぼりにしている実際の奥様に対する椎名さんの罪悪感が色濃く強調されているようなきがする。ほかにも妻との関係に不安が浮かび上がったような不安な小説が幾つかある。)や、なんといっても「月の夜」における、人間に対する深い愛情とそしてその愚かさを、人外を語り手にすることでなかば神の視点で客観的に浮かび上がらせており、その人間からすると非常にすら見える寛大さが、人間にとってはこの上なく理解不能で恐ろしく見えるのである。
SFほど異世界ではないし、かといって日常からは1歩か2歩は逸脱している程よいレベルなので、古本屋さんで見かけたら手に取ってもらって是非どうぞ。
2017年12月29日金曜日
2017年12月24日日曜日
椎名誠/鉄塔のひと その他の短編
日本の作家の短編小説集。
私は椎名誠さんのファンなのだが、SFがメインでその他のフィクションとなると短編集1〜2冊しか読んでいない。というわけで何冊か、フィクションでそれも少し不思議な要素が入っていさそうな本を買った。
そもそも椎名誠さんのSFの面白いところに突飛な世界観(SFは多かれ少なかれ突飛な事が多いけど、この作者の場合説明が少なく、かわりに造語を多分に用いた)と、そこに蠢く(人間も含めた)奇妙で生命力に溢れたキャラクターが起こす小さな(たとえば銀河系の命運を決める、とかそういうのではないという意味で)騒動だと思うのだが、その要素がSF以外では活かしきれないのでは?という気が私は全然しなかったんだけど、改めてSFではない作品を読んでもやはりそのとおりだった。
この本に収録されている10の短編はどれもSFとは言い難いが、日常のなにか表層を一部だけひっくり返したような超常性があり、そこが怖い。というのもわかりやすいのは妻が別人に思えてならない話(「妻」)などは妻帯者でなくても夫婦という状況が想像しやすいゆえに、突飛でなく(むしろ突飛でないゆえに)恐ろしいのである。この日常に埋もれた非日常感というのが大切で、例えば田舎で良い感じに酔っ払って裏道に迷い込んで不思議な祭りに遭遇する話(「抱貝」)なんかは、特に都会で暮らす者にとっては非日常である田舎の暮らしに抱くロマン(ちょっと色っぽいシーンも有る)が見事に表現されていると思う。それは未知との遭遇であり、つまりSF的でもあると思う。(この短編は椎名流の造語も出てきて一番SFっぽいと言っても良い。)つまり筆者の持ち味はSFというフィールドを離れても少しの瑕疵もなく、同じ軽薄な文体の中にとらえどころなく存在している。それは言ってしまえばここではない、どこかへのあこがれであり、それが日常のちょっとした空隙の先に存在しているという優しい物語である。
また文体に気取ったところが一切なく、それでいて読みやすさを考慮されて練られた独特の語り口(つまり昭和軽薄体)は非常に読みやすく、ごろんと寝転んで読んでいいのね、位の気持ちで物語に入れるようになっている。軽い気持ちで是非どうぞ。
私は椎名誠さんのファンなのだが、SFがメインでその他のフィクションとなると短編集1〜2冊しか読んでいない。というわけで何冊か、フィクションでそれも少し不思議な要素が入っていさそうな本を買った。
そもそも椎名誠さんのSFの面白いところに突飛な世界観(SFは多かれ少なかれ突飛な事が多いけど、この作者の場合説明が少なく、かわりに造語を多分に用いた)と、そこに蠢く(人間も含めた)奇妙で生命力に溢れたキャラクターが起こす小さな(たとえば銀河系の命運を決める、とかそういうのではないという意味で)騒動だと思うのだが、その要素がSF以外では活かしきれないのでは?という気が私は全然しなかったんだけど、改めてSFではない作品を読んでもやはりそのとおりだった。
この本に収録されている10の短編はどれもSFとは言い難いが、日常のなにか表層を一部だけひっくり返したような超常性があり、そこが怖い。というのもわかりやすいのは妻が別人に思えてならない話(「妻」)などは妻帯者でなくても夫婦という状況が想像しやすいゆえに、突飛でなく(むしろ突飛でないゆえに)恐ろしいのである。この日常に埋もれた非日常感というのが大切で、例えば田舎で良い感じに酔っ払って裏道に迷い込んで不思議な祭りに遭遇する話(「抱貝」)なんかは、特に都会で暮らす者にとっては非日常である田舎の暮らしに抱くロマン(ちょっと色っぽいシーンも有る)が見事に表現されていると思う。それは未知との遭遇であり、つまりSF的でもあると思う。(この短編は椎名流の造語も出てきて一番SFっぽいと言っても良い。)つまり筆者の持ち味はSFというフィールドを離れても少しの瑕疵もなく、同じ軽薄な文体の中にとらえどころなく存在している。それは言ってしまえばここではない、どこかへのあこがれであり、それが日常のちょっとした空隙の先に存在しているという優しい物語である。
また文体に気取ったところが一切なく、それでいて読みやすさを考慮されて練られた独特の語り口(つまり昭和軽薄体)は非常に読みやすく、ごろんと寝転んで読んでいいのね、位の気持ちで物語に入れるようになっている。軽い気持ちで是非どうぞ。
Bell Witch/Mirror Reaper
アメリカ合衆国ワシントン州シアトルのドゥーム・メタルバンドの3rdアルバム。
2017年にProfound Lore Recordsからリリースされた。
2010年にドラムとベース兼ボーカルの二人組で結成されたバンド。バンド名は実際にアメリカで起こった幽霊屋敷事件に基づく。(wikiなんかを読むと非常に面白い事件であるようだ。)なんとなく1st「Longing」の頃から聴いている。2016年にオリジナルメンバーであるドラマーのAdrian Guerraが逝去。もうバンドとしては終わりになってしまうのかと思っていたのだが、新しくドラムのメンバーを迎え入れて発表した新作。嬉しくてLP盤を購入。アートワークはベクシンスキーっぽい。
もともと長尺の曲を演奏するドゥーム・メタルバンドだったが、1stが6曲、2ndで4曲、ついにこの3rdで1曲83分という次元に突入。この情報で当惑するのではなくテンション上がるのは変な人だと思う。一応LPだと「As」、「Above」、「So」、「Below」と片面ずつ別れているようだが…。
1曲にしたのはもちろん長い曲をやるために他ならない。元々長い曲をドローンの要素を入れつつプレイしていたが、それでも結構明確にパートが分かれているのがこのバンドの特徴だった。今回ではそれぞれのパートを本当に贅沢に使っており、83分という長さを活かした”1曲”をプレイしている。ベースと言っても6弦あるものを使っているようで、ダウンチューニングしてエフェクトを掛けたギターと正直あまり違いがわからないのだが(バンドやっている人ならやはり明確にわかるのだろうか)、それをズアーーーっともったり引き伸ばすような弾き方をしており、とにかく全体的にめちゃくちゃ引き伸ばされた残響を楽しむためのバンドである。それ故フューネラル・ドゥームの要素もあるのだが、わかりやすくブラックメタルを彷彿とさせる要素はあまりない。邪悪さも黒さもあるが、それこそ幽霊のように”曖昧”であることがこのバンドの一番の魅力だ。
khanateを通過してのSunn O)))に通じるところがある(世界観や雰囲気も)が、しかしあちらが邪悪な神話だとするとこちらはロアというかやはり幽霊譚というのがしっくり来る。もっとしっとり、いやじっとりと湿っていて、そして地味であまり知られていない感じ。この湿度というのはつまり叙情的であることだ。この手のジャンルでは敬遠されがちな感情豊かな表現をBell Witchは積極的に自分のフィールドとしている。とにかく重たく遅々として進まない演奏と地を這うような低音ボーカルを主体にしながらも、はクリーンボーカルが歌うメロディそして、感情的なメロディ性のあるベースライン。とくにリフはもはやフレーズと化していて、このバンドならではの曲の長さを存分に活かして贅沢に長く、そして繰り返されていく様はまさに桃源郷。よくよく計算されていて音はでかいが、フィードバックノイズは制限されており、体の表皮を震わし、その後体内に浸透していくような柔らかさがある。いわばうるさくないノイズだ。ひたすら暗く、潜行していくように下に潜っていくが、どんな幽霊もその重さのない身(心)中に物語を隠しているように、聞けば聞くほどにその豊かさにハッとする。
そしてやっぱりクリーンボーカルが映えること。今回もたまらなく良い。うっすらあるメロディラインを良い感じに魂の抜けた声がふわーっと通り過ぎていく。うっすら滲む諦念が背後に渦巻く低音にのってじわじわしみてくる。アメリカのバンドだが、この彼らの「幽霊感」に和風な、恐ろしくも儚く、そして地上には特定の条件下でしかとどまっていないような存在の薄さ、軽さを感じてしまう。非常にヘヴィな音楽なので我ながら妙な感想だとは思うのだが。
曲の長さもあってとっつきやすい音楽ではないが、この手の音楽が好きな人は是非どうぞ。私はやはり非常に好きだ。スラッジ方面に舵を取るでもなく、この物語性に飛んだ幽玄さに感じを取るというのはメタル的だが、どれもやはりソリッドでこういう浮遊感のあるバンドというのは他に知らない。じっとりとした湿度は日本人にはしっくり来ると思うのでぜひ聴いてみて頂きたい。きっと予想より聞きやすいはず!おすすめです。
2017年にProfound Lore Recordsからリリースされた。
2010年にドラムとベース兼ボーカルの二人組で結成されたバンド。バンド名は実際にアメリカで起こった幽霊屋敷事件に基づく。(wikiなんかを読むと非常に面白い事件であるようだ。)なんとなく1st「Longing」の頃から聴いている。2016年にオリジナルメンバーであるドラマーのAdrian Guerraが逝去。もうバンドとしては終わりになってしまうのかと思っていたのだが、新しくドラムのメンバーを迎え入れて発表した新作。嬉しくてLP盤を購入。アートワークはベクシンスキーっぽい。
もともと長尺の曲を演奏するドゥーム・メタルバンドだったが、1stが6曲、2ndで4曲、ついにこの3rdで1曲83分という次元に突入。この情報で当惑するのではなくテンション上がるのは変な人だと思う。一応LPだと「As」、「Above」、「So」、「Below」と片面ずつ別れているようだが…。
1曲にしたのはもちろん長い曲をやるために他ならない。元々長い曲をドローンの要素を入れつつプレイしていたが、それでも結構明確にパートが分かれているのがこのバンドの特徴だった。今回ではそれぞれのパートを本当に贅沢に使っており、83分という長さを活かした”1曲”をプレイしている。ベースと言っても6弦あるものを使っているようで、ダウンチューニングしてエフェクトを掛けたギターと正直あまり違いがわからないのだが(バンドやっている人ならやはり明確にわかるのだろうか)、それをズアーーーっともったり引き伸ばすような弾き方をしており、とにかく全体的にめちゃくちゃ引き伸ばされた残響を楽しむためのバンドである。それ故フューネラル・ドゥームの要素もあるのだが、わかりやすくブラックメタルを彷彿とさせる要素はあまりない。邪悪さも黒さもあるが、それこそ幽霊のように”曖昧”であることがこのバンドの一番の魅力だ。
khanateを通過してのSunn O)))に通じるところがある(世界観や雰囲気も)が、しかしあちらが邪悪な神話だとするとこちらはロアというかやはり幽霊譚というのがしっくり来る。もっとしっとり、いやじっとりと湿っていて、そして地味であまり知られていない感じ。この湿度というのはつまり叙情的であることだ。この手のジャンルでは敬遠されがちな感情豊かな表現をBell Witchは積極的に自分のフィールドとしている。とにかく重たく遅々として進まない演奏と地を這うような低音ボーカルを主体にしながらも、はクリーンボーカルが歌うメロディそして、感情的なメロディ性のあるベースライン。とくにリフはもはやフレーズと化していて、このバンドならではの曲の長さを存分に活かして贅沢に長く、そして繰り返されていく様はまさに桃源郷。よくよく計算されていて音はでかいが、フィードバックノイズは制限されており、体の表皮を震わし、その後体内に浸透していくような柔らかさがある。いわばうるさくないノイズだ。ひたすら暗く、潜行していくように下に潜っていくが、どんな幽霊もその重さのない身(心)中に物語を隠しているように、聞けば聞くほどにその豊かさにハッとする。
そしてやっぱりクリーンボーカルが映えること。今回もたまらなく良い。うっすらあるメロディラインを良い感じに魂の抜けた声がふわーっと通り過ぎていく。うっすら滲む諦念が背後に渦巻く低音にのってじわじわしみてくる。アメリカのバンドだが、この彼らの「幽霊感」に和風な、恐ろしくも儚く、そして地上には特定の条件下でしかとどまっていないような存在の薄さ、軽さを感じてしまう。非常にヘヴィな音楽なので我ながら妙な感想だとは思うのだが。
曲の長さもあってとっつきやすい音楽ではないが、この手の音楽が好きな人は是非どうぞ。私はやはり非常に好きだ。スラッジ方面に舵を取るでもなく、この物語性に飛んだ幽玄さに感じを取るというのはメタル的だが、どれもやはりソリッドでこういう浮遊感のあるバンドというのは他に知らない。じっとりとした湿度は日本人にはしっくり来ると思うのでぜひ聴いてみて頂きたい。きっと予想より聞きやすいはず!おすすめです。
ラベル:
Bell Witch,
アメリカ,
スラッジコア,
ドゥームメタル,
フューネラルドゥーム,
音楽
ミシェル・ウェルベック/地図と領土
フランスの作家による長編小説。
なんとなく名前はしっていた作家の作品、何の気なしに買ってみたのがこちら。作者ミシェル・ウェルベックはフランスで今最もスキャンダラスな作家だとか。イスラムの台頭と脅威を予見したとか、その過激な言動でとか。この本でかれはフランスで最も権威のある文学賞の一つであるゴングール賞を受賞した。
舞台はフランス。成功した建築士を父親に持ち、母親は若くして自殺、ジェド・マルタンは芸術の道に進んだ。世間ずれした男だが、若くして成功したジェドの前には前途洋々とした道が広がっていた。
人が殺される小説だがミステリーではない。ジェド・マルタンというアーティストの人生を追った純文学である。私はなんとなく難解な現代文学なのかな、と思っていたが(気になった本は殆ど調べずに買ってしまう。)、読んでみると違った。まだ中盤にようやく差し掛かるか、というところでtwitterで「俗っぽい」と表現したのだがこれは間違いだった。たしかに主人公は若くしてアーティストとして成功し、俗っぽさのひとつの頂点であるところの社交界に入り、セレブリティたちの仲間入りをする。おそらく作者ウェルベックの経験を存分に活かして書いたのだろうこのパートは、私のように昼ごはんの値段に一喜一憂するみみっちい小市民からするとギラギラ輝いて非常に魅力的である。私にできるのは虚構の世界のくだらなさにかこつけて、僻みっぽくつぶやくことくらいである。(もし自分がそこに入れたらな、と夢想くせに。)しかしこの小説はセレブリティたちの現実離れしたライフスタイルをひたすら書いていく通俗小説ではない。そこが若きアーティストの通過地点だから書いたに過ぎない。
ジェドというのは変わった男で人と世間に対して極端に没交渉である。女性らしい魅力的な容姿に恵まれていて、なにより才能と名声もあるので美しい恋人もできる。しかし友達はほぼ一人もいなくて、たまにはコールガールを買ったりもする。めんどくさがり屋で食べ物にはこだわりがなく、部屋は汚い。言葉少なく一見すると仙人めいた超人に見えるが、ウェルベックはそんな彼を変わっているが(天才なのだろうが)一人の何の変哲もない人間として描いている。恋人との別れを平然と選べるし、離れようとする彼女を止めないし(彼女は止めてほしかったのだが)、その後10年間も連絡を取らないような男だが、別れの直後は泣いたりする。(泣き叫ぶ人が一番悲しんでいるわけでは当たり前だがない。)なにより世間と交渉のない彼は父親に対して強い愛情というか、絆を感じている。頻繁に会うわけではないが(むしろあまり会わない方なのかもしれないが)、必ずクリスマスには食事をともにし、父親のこと知りたいと考えている。
文体は結構特徴的で、時系列の連続性がたまにずれるし、会話のようにとある言葉や事柄から話題がそれていくような書き方をする。翻訳が上手いこともあって読みにくさというのは皆無だが、特徴的ではあると思う。言葉は多い方だが、あまり説明的でなく、出来事を描写することに終始している。作者がこの作品にどんな思いを込めているか、というのは読む人次第で解釈が変わるとも言える。ミステリアスであり、たしかに話題性のある書き方である。つまり何か重要なことを行っているように思える、という作品でもある。別にディスっているわけではなく、このやり方で中身が伴わなければただの軽い小説になってしまうだろう。
月並みに言って人生を書いた小説であり、孤独とその辛さを書いた小説である。ジェドはなぜ成功したのか、というと物語的にも面白くなるのはあるけど、逆に不遇の芸術家でもいくらでも物語ができる。おそらくだが、なぜ彼は芸術家で有り続けたのか?というのを書くためであるのではと思う。ジェドは結構人生の早々に一生困らないくらいの金持ちになる。しかし彼はあまり金に頓着がなく、ずっと調子の悪いボイラーのある(おそらく)あまりセレブリティが住むような部屋(マンションなので)に住み続けている。ウェルベックはこう言いたい、つまりジェドは成功しても成功しなくても一生アートに取り組み続けただろう。彼は表現者であり、それ故道具を選ばない。はじめは写真、そして絵画、次は動画と表現手段を変えつつ、一貫して作品を生み出し続けた。実はここにあまりよくある「産みの苦しみ」(一作品だけ完成しなかった作品があってそこに表現されているが)、「生まれながらの芸術家としてのこだわり(アートのために生まれてきた、アートによって生かされアートが私にとって生きることである、みたいなくだらないやつ)」ではなく、ただ何かの巨大な法則の一部として自分はアートに取り組んでいる、のようなかかれ方がしているのが一番個人的には面白かったし良かった。彼にとってアートが重要であることは、生涯それに取り組み続けたことを見れば一目瞭然である。かれはアート(そしてそれを生み出す自分を)を至高(苦しいがみんなのために取り組み続ける殉教者のような(非常にくだらない))何か、に誇張することなく、それに取り組み続けた。言葉は少ないが、人生を捧げたと言っても良い。
面白かった。ちゃんと読みやすく、わかりやすい山場(上流階級の暮らしぶりや凄惨な殺人)もあるが、それでいてなによりも非常に真面目な小説であった。読み終わらないうちからウェルベックの別の本を買った。
なんとなく名前はしっていた作家の作品、何の気なしに買ってみたのがこちら。作者ミシェル・ウェルベックはフランスで今最もスキャンダラスな作家だとか。イスラムの台頭と脅威を予見したとか、その過激な言動でとか。この本でかれはフランスで最も権威のある文学賞の一つであるゴングール賞を受賞した。
舞台はフランス。成功した建築士を父親に持ち、母親は若くして自殺、ジェド・マルタンは芸術の道に進んだ。世間ずれした男だが、若くして成功したジェドの前には前途洋々とした道が広がっていた。
人が殺される小説だがミステリーではない。ジェド・マルタンというアーティストの人生を追った純文学である。私はなんとなく難解な現代文学なのかな、と思っていたが(気になった本は殆ど調べずに買ってしまう。)、読んでみると違った。まだ中盤にようやく差し掛かるか、というところでtwitterで「俗っぽい」と表現したのだがこれは間違いだった。たしかに主人公は若くしてアーティストとして成功し、俗っぽさのひとつの頂点であるところの社交界に入り、セレブリティたちの仲間入りをする。おそらく作者ウェルベックの経験を存分に活かして書いたのだろうこのパートは、私のように昼ごはんの値段に一喜一憂するみみっちい小市民からするとギラギラ輝いて非常に魅力的である。私にできるのは虚構の世界のくだらなさにかこつけて、僻みっぽくつぶやくことくらいである。(もし自分がそこに入れたらな、と夢想くせに。)しかしこの小説はセレブリティたちの現実離れしたライフスタイルをひたすら書いていく通俗小説ではない。そこが若きアーティストの通過地点だから書いたに過ぎない。
ジェドというのは変わった男で人と世間に対して極端に没交渉である。女性らしい魅力的な容姿に恵まれていて、なにより才能と名声もあるので美しい恋人もできる。しかし友達はほぼ一人もいなくて、たまにはコールガールを買ったりもする。めんどくさがり屋で食べ物にはこだわりがなく、部屋は汚い。言葉少なく一見すると仙人めいた超人に見えるが、ウェルベックはそんな彼を変わっているが(天才なのだろうが)一人の何の変哲もない人間として描いている。恋人との別れを平然と選べるし、離れようとする彼女を止めないし(彼女は止めてほしかったのだが)、その後10年間も連絡を取らないような男だが、別れの直後は泣いたりする。(泣き叫ぶ人が一番悲しんでいるわけでは当たり前だがない。)なにより世間と交渉のない彼は父親に対して強い愛情というか、絆を感じている。頻繁に会うわけではないが(むしろあまり会わない方なのかもしれないが)、必ずクリスマスには食事をともにし、父親のこと知りたいと考えている。
文体は結構特徴的で、時系列の連続性がたまにずれるし、会話のようにとある言葉や事柄から話題がそれていくような書き方をする。翻訳が上手いこともあって読みにくさというのは皆無だが、特徴的ではあると思う。言葉は多い方だが、あまり説明的でなく、出来事を描写することに終始している。作者がこの作品にどんな思いを込めているか、というのは読む人次第で解釈が変わるとも言える。ミステリアスであり、たしかに話題性のある書き方である。つまり何か重要なことを行っているように思える、という作品でもある。別にディスっているわけではなく、このやり方で中身が伴わなければただの軽い小説になってしまうだろう。
月並みに言って人生を書いた小説であり、孤独とその辛さを書いた小説である。ジェドはなぜ成功したのか、というと物語的にも面白くなるのはあるけど、逆に不遇の芸術家でもいくらでも物語ができる。おそらくだが、なぜ彼は芸術家で有り続けたのか?というのを書くためであるのではと思う。ジェドは結構人生の早々に一生困らないくらいの金持ちになる。しかし彼はあまり金に頓着がなく、ずっと調子の悪いボイラーのある(おそらく)あまりセレブリティが住むような部屋(マンションなので)に住み続けている。ウェルベックはこう言いたい、つまりジェドは成功しても成功しなくても一生アートに取り組み続けただろう。彼は表現者であり、それ故道具を選ばない。はじめは写真、そして絵画、次は動画と表現手段を変えつつ、一貫して作品を生み出し続けた。実はここにあまりよくある「産みの苦しみ」(一作品だけ完成しなかった作品があってそこに表現されているが)、「生まれながらの芸術家としてのこだわり(アートのために生まれてきた、アートによって生かされアートが私にとって生きることである、みたいなくだらないやつ)」ではなく、ただ何かの巨大な法則の一部として自分はアートに取り組んでいる、のようなかかれ方がしているのが一番個人的には面白かったし良かった。彼にとってアートが重要であることは、生涯それに取り組み続けたことを見れば一目瞭然である。かれはアート(そしてそれを生み出す自分を)を至高(苦しいがみんなのために取り組み続ける殉教者のような(非常にくだらない))何か、に誇張することなく、それに取り組み続けた。言葉は少ないが、人生を捧げたと言っても良い。
面白かった。ちゃんと読みやすく、わかりやすい山場(上流階級の暮らしぶりや凄惨な殺人)もあるが、それでいてなによりも非常に真面目な小説であった。読み終わらないうちからウェルベックの別の本を買った。
ラベル:
フランス,
ミシェル・ウェルベック,
純文学,
本
Amenra/Mass IIII
ベルギーはウェスト=フランデレン州コルトレイクのポストメタル/ハードコアバンドの4thアルバム。2008年にHepertension Recordsからリリースされた。私が買ったのは一つ前の記事の前作とセットになった編集盤の、さらに日本盤でTokyo Jupiter Recordsからリリースされたもの。
基本的な路線は前作を踏襲しているが、大きく変えているところはある。
一つは演奏技術力の向上による表現力の幅の増加。スキルが上がったことと更に、そこを支点にして曲に新しい要素を加えようという意思を感じる。これは展開にあらわれていて、ミニマル差を実験精神の表現として使っていた前作から脱却して曲を”動か”すことに意識を向けている。プログレッシブ方向に舵を取ったとも言えるが、むしろ曲の中を区切ってそれぞれのパーツの差異がはっきりして陰影がついた。立体的になって曲が鮮やかに(明るくなったという意味ではなく)なっている。私の耳には各パーツの以降はスムーズに聞こえる。つまりドゥーム的な”重苦しい長さ”はプログレッシブさの導入により損なわれていない。
もう一つはよりハードな方面への舵取りで、クリーンボーカルの登場頻度を減らしている。前作の感想で書いたが、重苦しく閉鎖的で更に長い楽曲だからこそクリーンなメロディ(ただし陰々滅々とした)はよく映えたし、ハードなバンドのわかり易い表現の取っ掛かりになっていた。ここを大胆に減らしている。完全にオミットしているわけではなく使用自体はしているが、曲中占める割合は減り、ともすると何回か聞けば聞き手が一緒に歌えるくらいの明快なメロディというのは減退しており、より曖昧に、不穏な部分を強調するような断片的なものに変更されている。自分たちの持ち味がどこにあるのかという時にやはりハードコアだろうという判断が生じたのかもしれない。
この手のジャンルで用いられるアトモスフェリックというのは何かというと、個人的には浮遊感や壮大さというか、バンドサウンド以外の音も積極的に取り入れて得る”非ソリッド感”のような気がしている。表現の幅が広がる反面、バンドサウンドの生々しさや直感性は損なわれるわけだ。そこへ来ると前作もそうだったが、Amenraに関してはそういったアトモスフェリックなテイストはあまり感じられない。アートワークや宙吊りになるというステージングからアート感というより、どうやって自分たちが見られるか、そして見られたいか、という意図や企図は感じられるのだが、音の方は徹頭徹尾暗く陰気である。閉塞感という言葉がしっくり来る。増やした展開も重たい霧のように全体を覆い尽くす陰鬱さを切り裂くようなものではない。変転する世界が幾つもの層を持っているとして、世界の変転を認めず、そして明るい面を半ば無視して暗い面ばかり凝視しているような音楽である。そんな生き方は体に毒だと思うのだが、鈍い輝きは人を引きつけるのかもしれない。
ぜひTokyo Jupiter Recordsから出ている前作とのセットの編集盤をどうぞ。年内に売り切れると来日の可能性アリとのことなので。このあとの5th、それから最新作も気になるところ。
基本的な路線は前作を踏襲しているが、大きく変えているところはある。
一つは演奏技術力の向上による表現力の幅の増加。スキルが上がったことと更に、そこを支点にして曲に新しい要素を加えようという意思を感じる。これは展開にあらわれていて、ミニマル差を実験精神の表現として使っていた前作から脱却して曲を”動か”すことに意識を向けている。プログレッシブ方向に舵を取ったとも言えるが、むしろ曲の中を区切ってそれぞれのパーツの差異がはっきりして陰影がついた。立体的になって曲が鮮やかに(明るくなったという意味ではなく)なっている。私の耳には各パーツの以降はスムーズに聞こえる。つまりドゥーム的な”重苦しい長さ”はプログレッシブさの導入により損なわれていない。
もう一つはよりハードな方面への舵取りで、クリーンボーカルの登場頻度を減らしている。前作の感想で書いたが、重苦しく閉鎖的で更に長い楽曲だからこそクリーンなメロディ(ただし陰々滅々とした)はよく映えたし、ハードなバンドのわかり易い表現の取っ掛かりになっていた。ここを大胆に減らしている。完全にオミットしているわけではなく使用自体はしているが、曲中占める割合は減り、ともすると何回か聞けば聞き手が一緒に歌えるくらいの明快なメロディというのは減退しており、より曖昧に、不穏な部分を強調するような断片的なものに変更されている。自分たちの持ち味がどこにあるのかという時にやはりハードコアだろうという判断が生じたのかもしれない。
この手のジャンルで用いられるアトモスフェリックというのは何かというと、個人的には浮遊感や壮大さというか、バンドサウンド以外の音も積極的に取り入れて得る”非ソリッド感”のような気がしている。表現の幅が広がる反面、バンドサウンドの生々しさや直感性は損なわれるわけだ。そこへ来ると前作もそうだったが、Amenraに関してはそういったアトモスフェリックなテイストはあまり感じられない。アートワークや宙吊りになるというステージングからアート感というより、どうやって自分たちが見られるか、そして見られたいか、という意図や企図は感じられるのだが、音の方は徹頭徹尾暗く陰気である。閉塞感という言葉がしっくり来る。増やした展開も重たい霧のように全体を覆い尽くす陰鬱さを切り裂くようなものではない。変転する世界が幾つもの層を持っているとして、世界の変転を認めず、そして明るい面を半ば無視して暗い面ばかり凝視しているような音楽である。そんな生き方は体に毒だと思うのだが、鈍い輝きは人を引きつけるのかもしれない。
Amnera/Mass III-II
ベルギーはウェスト=フランデレン州コルトレイクのポストメタル/ハードコアバンドの3rdアルバムにボーナストラックを加えたもの。
元は2005年にHypertension Records(良いレーベル名だ)など複数のレーベルからリリースされたもの。私が買ったのはボーナストラック3曲(EPから2曲、ライブトラック1曲)を追加して、さらにこの後リリースされたアルバム「Mass IIII」をセットにしたコンピレーションアルバム「Mass III-II + Mass IIII」というアルバム。こちらも幾つかのレーベルからリリースされたが、私のは日本のTokyo Jupiter Recordsから出ているもの。元は別の作品なので別々に感想を書こうかなと。
Amenraでアメン・ラーだ。たしかエジプトの太陽神の名前だったと思う。結成は1999年で今は5人組のようだ。メンバーチェンジもあったようでオリジナルメンバーは今二人(ボーカルとギター)残っている。もう一人ギター担当のメンバーがいてこの人はOathbreakerのメンバーでもあるそうな。
新作はNeurot Recordingsからリリースされているのだが、それも納得のサウンドを鳴らしている。根っこがハードコアだが病みに病んで速度が遅くなり、展開も複雑かつ大仰になったスラッジ・サウンドを鳴らしている。スラッジと言ってもEyehategod系の退廃的かつ厭世的、薬とアルコールでハイになったスラッジ・コアとは明らかに一線を画す暗い内容でどちらかと言うと、頭にポストとつく感じのインテリジェンスなサウンド。不良というよりは優等生が病んだ的な雰囲気の方のやつです。ポストの次がロック(ではないような印象だけど)、メタル、ハードコアのどれかっていうのがちょっと判然としないのがこのバンドの面白いところ。この手のバンドはDownfall of Gaiaとか、Rorcalとかが思い浮かぶが、曲が長くなるに連れて展開が複雑に、そして劇的(ドラマティック)になってくるものだけど、このバンドは結構その手の方向に進むことを拒否していてあくまでも陰湿なハードコアを徹頭徹尾プレイしている。外へ外へ広がっていかないのだ。また美麗なアルペジオや浮遊感のあるシンセサウンドもなし。あくまでもソリッドかつ重厚でどこか想像の別天地に飛翔することを許さない牢獄感。逃げようとする足首をぐっと掴んでくる陰湿さがある。もともと内省的なジャンルだが音もその精神に忠実で中期(遅くなって以降の)Neurosisの影響を色濃く感じる。結果密室的で閉塞感のあるハードコアが長尺で延々とプレイされるかなりハードな地獄絵図が展開されるのだが、最後の希望が用意されている。それが陰鬱なメロディの大胆な導入。サビのための他のパートという使い方ではなく、長い曲のなかの一部としてクリーンボーカルによるメロディを取り込んでいる。この「歌」というのもなかなかどうしても暗く陰鬱で、少し耽美なところがある。病的な男の現実逃避めいていて、音楽が密室を構築するなら、梁に縄を引っ掛ける時に幼く幸せだったときの同様を口ずさんでいるような嫌〜な感じがする。これが良い。
前述の2つのバンドのようなハードコアから始まり、ブラックメタルも飲み込んだ壮大なポストメタル/スラッジというより、自分的には激情系やエモバイオレンスに自殺感を持ち込んだようなイメージが近い。というのも長い曲でアトモスフェリックな要素をほぼ用いず、バンドサウンドで勝負していること。アート感はなく、ハードコアを貫いていること。歌詞は分からないが、全体的に極めて内省的で自己批判的な精神が感じられること、これは出す音が”個人的”なように私には聞こえる。矮小や卑小と言っても良いかもしれないが、壮大な曲のドラマティックさに胸を打たれるのも良いが、どこまで行っても自分という檻からは逃げ切れないような、そういった日常的な悲痛さが強調されていて個人的には妙に共感してしまう。
ポストメタルが好きな人が聴いてみるのはもちろん良いし、日本や海外の悩み過ぎ系病みハードコアが好きな人も結構好きになるのではないかと思う。
ちなみに年内にこの編集盤が完売すると、発売元のTokyo Jupiter Recordsが来日に向けてバンド側との本格的な交渉に入るとのこと。残り少ない年内だが、気になっている人は買ってみると良いかもしれない。
また、Decayed Sun Recordsの特集記事がとても読み応えがあるのでぜひ読んでみていただきたい。私は自分が書いているのは感想文なのだが、この記事というのは私が考えるレビューの一つの理想形だと思う。
元は2005年にHypertension Records(良いレーベル名だ)など複数のレーベルからリリースされたもの。私が買ったのはボーナストラック3曲(EPから2曲、ライブトラック1曲)を追加して、さらにこの後リリースされたアルバム「Mass IIII」をセットにしたコンピレーションアルバム「Mass III-II + Mass IIII」というアルバム。こちらも幾つかのレーベルからリリースされたが、私のは日本のTokyo Jupiter Recordsから出ているもの。元は別の作品なので別々に感想を書こうかなと。
Amenraでアメン・ラーだ。たしかエジプトの太陽神の名前だったと思う。結成は1999年で今は5人組のようだ。メンバーチェンジもあったようでオリジナルメンバーは今二人(ボーカルとギター)残っている。もう一人ギター担当のメンバーがいてこの人はOathbreakerのメンバーでもあるそうな。
新作はNeurot Recordingsからリリースされているのだが、それも納得のサウンドを鳴らしている。根っこがハードコアだが病みに病んで速度が遅くなり、展開も複雑かつ大仰になったスラッジ・サウンドを鳴らしている。スラッジと言ってもEyehategod系の退廃的かつ厭世的、薬とアルコールでハイになったスラッジ・コアとは明らかに一線を画す暗い内容でどちらかと言うと、頭にポストとつく感じのインテリジェンスなサウンド。不良というよりは優等生が病んだ的な雰囲気の方のやつです。ポストの次がロック(ではないような印象だけど)、メタル、ハードコアのどれかっていうのがちょっと判然としないのがこのバンドの面白いところ。この手のバンドはDownfall of Gaiaとか、Rorcalとかが思い浮かぶが、曲が長くなるに連れて展開が複雑に、そして劇的(ドラマティック)になってくるものだけど、このバンドは結構その手の方向に進むことを拒否していてあくまでも陰湿なハードコアを徹頭徹尾プレイしている。外へ外へ広がっていかないのだ。また美麗なアルペジオや浮遊感のあるシンセサウンドもなし。あくまでもソリッドかつ重厚でどこか想像の別天地に飛翔することを許さない牢獄感。逃げようとする足首をぐっと掴んでくる陰湿さがある。もともと内省的なジャンルだが音もその精神に忠実で中期(遅くなって以降の)Neurosisの影響を色濃く感じる。結果密室的で閉塞感のあるハードコアが長尺で延々とプレイされるかなりハードな地獄絵図が展開されるのだが、最後の希望が用意されている。それが陰鬱なメロディの大胆な導入。サビのための他のパートという使い方ではなく、長い曲のなかの一部としてクリーンボーカルによるメロディを取り込んでいる。この「歌」というのもなかなかどうしても暗く陰鬱で、少し耽美なところがある。病的な男の現実逃避めいていて、音楽が密室を構築するなら、梁に縄を引っ掛ける時に幼く幸せだったときの同様を口ずさんでいるような嫌〜な感じがする。これが良い。
前述の2つのバンドのようなハードコアから始まり、ブラックメタルも飲み込んだ壮大なポストメタル/スラッジというより、自分的には激情系やエモバイオレンスに自殺感を持ち込んだようなイメージが近い。というのも長い曲でアトモスフェリックな要素をほぼ用いず、バンドサウンドで勝負していること。アート感はなく、ハードコアを貫いていること。歌詞は分からないが、全体的に極めて内省的で自己批判的な精神が感じられること、これは出す音が”個人的”なように私には聞こえる。矮小や卑小と言っても良いかもしれないが、壮大な曲のドラマティックさに胸を打たれるのも良いが、どこまで行っても自分という檻からは逃げ切れないような、そういった日常的な悲痛さが強調されていて個人的には妙に共感してしまう。
ポストメタルが好きな人が聴いてみるのはもちろん良いし、日本や海外の悩み過ぎ系病みハードコアが好きな人も結構好きになるのではないかと思う。
ちなみに年内にこの編集盤が完売すると、発売元のTokyo Jupiter Recordsが来日に向けてバンド側との本格的な交渉に入るとのこと。残り少ない年内だが、気になっている人は買ってみると良いかもしれない。
また、Decayed Sun Recordsの特集記事がとても読み応えがあるのでぜひ読んでみていただきたい。私は自分が書いているのは感想文なのだが、この記事というのは私が考えるレビューの一つの理想形だと思う。
2017年12月16日土曜日
All Pigs Must Die/Hostage Animals
アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンのハードコアバンドの3rdアルバム。
2017年にSouthern Lord Recordingsからリリースされた。
ConvergeのドラマーBen Kollerが在籍していることで有名なバンド。他にはBloodhorseやThe Hope Conspiracyといった同じボストンのバンドのメンバーが名を連ねている。
スーパーグループってことになるのかもしれないけどコンスタントに活動しているようではや三枚目。私はこのアルバムで初めて聴く。
タイトルは「人質動物」だろうか。10曲をほぼ35分で突っ走るハードコアのアルバムなのだが、ハードコアというフォーマットでよくもここまで…という圧倒的な表現力を存分に発揮しているアルバムになっている。
シンプルかつソリッドなハードコアが他ジャンルからの要素を取り込みつつ、新しい表現力を獲得してきて久しい。わかりやすいのは明快なメロディの導入、ひたすら速さの中にピュア度を上げることに心血を注ぐファストコアや激烈な速さとそしてベクトルの真逆の遅さを取り入れたパワーバイオレンスなどなど。音的にも特に同じうるさい音楽というくくりで特にメタルからの影響は強くて、スラッシュメタル、ポストロック、昨今ではブラックメタルなどのサブジャンルを解体し、刻みまくるリフ、アルペジオや複雑な展開、トレモロリフなどに分解したパートをハードコアという骨組みに再構築する作業。まさにクロスオーバーな異ジャンル感の異種交配が、ハードコア(に限らないが)というジャンルを豊かにしていった。当たり前だが別の手法を持ち込めばしかし、元々のハードコアの濃度というのはどうしても薄まってしまう。今では音だけ聞いたら初期衝動あふれるハードコア・パンクから遠くはなれてしまったバンドなどは枚挙に暇がない。(念のため言っておくどちらが良い悪いのはなしではない。)
前置きが長くなってしまったが、どうしても表現力を豊かにしようとするとハードコアというフォーマットだとその濃度が薄まってしまうということが言いたく、その点からするとこの「Hostage Animal」というアルバムはどこまで言ってもシンプルかつソリッドで攻撃的なハードコアでい続けながら、その表現力の豊かさには目をみはるものがあると言いたい。ジャンルの限界に挑戦した、などというのは非常に陳腐な表現だが、このアルバムに関してはそう言いきってもよいのではと個人的に思っている。別に目新しいことを、奇をてらったことをやっているわけではない。しかしそれ故更に驚異的である。基本に忠実ながらここまで感情の振れ幅のあるアルバムはそうない。感情の表現といえばエモ、エモバイオレンス、激情などのサブジャンルが思い浮かぶが、それらのジャンルがそれなりの舞台装置を曲の中で作り上げるのに対して、APMDはあくまでもハードコアだ。余計な部分がほぼない。冗長にもなってしまうアルペジオや、悩みすぎて捻くれた複雑なリフと展開、ことさら残虐性を強調する(ともするとメタル的な)スラッジ展開、もちろんわかりやすいメロディなんかもない。だがそれらで表現しようとする、”アグレッション以外の何か”がたしかに存在する。一つにはリフというかフレーズの引き出しが半端なく、短いフレーズにも心を打つ響きが隠されていること、それから速度をうまく使っていること(テンポチェンジというのではなくて)があると思うのだが、それだけなら他のバンドもやっているだろう。なんとなく長大な曲を作ってそのコアだけが残るように削ぎ落としてしまったような感じすらある。ボーカルだけとるとどの曲も汚くがなりたてているだけであるのに(もちろん良い意味で。)、なんでこうも曲によって、そして曲の中に感情が詰まっているのか。シンプルに表現すればシンプルな感動が惹起されるというのは明確に間違いであるということを証明している、という意味で非常に優れたハードコアのアルバム。
表現力のために拡張し続けるジャンルを雑に殴りつけるような、バッキバキに引き締まりまくった筋肉質なアルバム。ちょっとこれはすごくて今年はConvergeの新作もあったが、そちらに行けずにここにとどまってしまったくらい。色々こねくり回す必要なんてなかったのか??と呆然とする。実際にハードコアのバンドをやっている人の感想が聞きたいところ。非常におすすめなので是非どうぞ。
2017年にSouthern Lord Recordingsからリリースされた。
ConvergeのドラマーBen Kollerが在籍していることで有名なバンド。他にはBloodhorseやThe Hope Conspiracyといった同じボストンのバンドのメンバーが名を連ねている。
スーパーグループってことになるのかもしれないけどコンスタントに活動しているようではや三枚目。私はこのアルバムで初めて聴く。
タイトルは「人質動物」だろうか。10曲をほぼ35分で突っ走るハードコアのアルバムなのだが、ハードコアというフォーマットでよくもここまで…という圧倒的な表現力を存分に発揮しているアルバムになっている。
シンプルかつソリッドなハードコアが他ジャンルからの要素を取り込みつつ、新しい表現力を獲得してきて久しい。わかりやすいのは明快なメロディの導入、ひたすら速さの中にピュア度を上げることに心血を注ぐファストコアや激烈な速さとそしてベクトルの真逆の遅さを取り入れたパワーバイオレンスなどなど。音的にも特に同じうるさい音楽というくくりで特にメタルからの影響は強くて、スラッシュメタル、ポストロック、昨今ではブラックメタルなどのサブジャンルを解体し、刻みまくるリフ、アルペジオや複雑な展開、トレモロリフなどに分解したパートをハードコアという骨組みに再構築する作業。まさにクロスオーバーな異ジャンル感の異種交配が、ハードコア(に限らないが)というジャンルを豊かにしていった。当たり前だが別の手法を持ち込めばしかし、元々のハードコアの濃度というのはどうしても薄まってしまう。今では音だけ聞いたら初期衝動あふれるハードコア・パンクから遠くはなれてしまったバンドなどは枚挙に暇がない。(念のため言っておくどちらが良い悪いのはなしではない。)
前置きが長くなってしまったが、どうしても表現力を豊かにしようとするとハードコアというフォーマットだとその濃度が薄まってしまうということが言いたく、その点からするとこの「Hostage Animal」というアルバムはどこまで言ってもシンプルかつソリッドで攻撃的なハードコアでい続けながら、その表現力の豊かさには目をみはるものがあると言いたい。ジャンルの限界に挑戦した、などというのは非常に陳腐な表現だが、このアルバムに関してはそう言いきってもよいのではと個人的に思っている。別に目新しいことを、奇をてらったことをやっているわけではない。しかしそれ故更に驚異的である。基本に忠実ながらここまで感情の振れ幅のあるアルバムはそうない。感情の表現といえばエモ、エモバイオレンス、激情などのサブジャンルが思い浮かぶが、それらのジャンルがそれなりの舞台装置を曲の中で作り上げるのに対して、APMDはあくまでもハードコアだ。余計な部分がほぼない。冗長にもなってしまうアルペジオや、悩みすぎて捻くれた複雑なリフと展開、ことさら残虐性を強調する(ともするとメタル的な)スラッジ展開、もちろんわかりやすいメロディなんかもない。だがそれらで表現しようとする、”アグレッション以外の何か”がたしかに存在する。一つにはリフというかフレーズの引き出しが半端なく、短いフレーズにも心を打つ響きが隠されていること、それから速度をうまく使っていること(テンポチェンジというのではなくて)があると思うのだが、それだけなら他のバンドもやっているだろう。なんとなく長大な曲を作ってそのコアだけが残るように削ぎ落としてしまったような感じすらある。ボーカルだけとるとどの曲も汚くがなりたてているだけであるのに(もちろん良い意味で。)、なんでこうも曲によって、そして曲の中に感情が詰まっているのか。シンプルに表現すればシンプルな感動が惹起されるというのは明確に間違いであるということを証明している、という意味で非常に優れたハードコアのアルバム。
表現力のために拡張し続けるジャンルを雑に殴りつけるような、バッキバキに引き締まりまくった筋肉質なアルバム。ちょっとこれはすごくて今年はConvergeの新作もあったが、そちらに行けずにここにとどまってしまったくらい。色々こねくり回す必要なんてなかったのか??と呆然とする。実際にハードコアのバンドをやっている人の感想が聞きたいところ。非常におすすめなので是非どうぞ。
ラベル:
All Pigs Must Die,
アメリカ,
ハードコア,
音楽
Blut aus Nord/Deus Salutis Meae
フランスはノルマンディ地方モンドヴィルのブラックメタルバンドの12枚めのアルバム。
2017年にDebemur Morti Productionsからリリースされた。
1994年から活動しており2011年からコンセプチュアルな3枚のアルバムをリリースして話題になっていたバンド。当時はなんとなく横目で見ていただけだけど今回はじめて買ってみた。
タイトルはラテン語で翻訳すると「私の神」となるようだ。覆面被った三人組なのだが、日本のwikiにかなり情報があって、そちらによると意外にも悪魔崇拝が売りの典型的なブラックメタル・バンドとは違うんだよ、ということらしい。おどろおどろしいイメージや音を使っているが、どうも独自の世界観を作ろうというバンドらしい。
実際に聞いてみるとなるほどかなり尖った音の作りになっている。音質悪くも生々しいプリミティブ・ブラックメタルとも違うし、デスメタルと融合しつつある力強くモダンで攻撃的なブラックメタルとも異なる。陰湿な世界観をややノイズに接近した音の作りで、決して速くないもったりとした速度で瘴気が滞留するように垂れ流す不穏な音世界。低音からずるっと滑るように滑らかに耳障りな高音に移行するギターリフ。ぐしゃっと潰れた低音や朗々とした詠唱めいた呪術的なボーカルが特徴的で、なんとなくDeathspell Omegaっぽいな、というのがファースト・インプレッション。もちろんこちらのバンドのほうが活動歴は長いのだが。ブラックメタルの武器であるブリザードのように寒々しいトレモロの中にうっすら見える美メロ、というのはもう気前よく捨てて別の次元で勝負しようというアルバム。(どうもアルバムごとにだいぶ作風を変えてくるバンドらしい。)
このアルバムを聴いて思ったのはかなりテクノ的ではないか?ということ。中心となるリフがあってそれをもったーり執拗に反復していく。かなりミニマル。ボーカルが変幻自在に唸ったりするもので一見してわかりにくいのだが、ふと我に返ると同じところをぐるぐると迷っていことに気がつく。途中でツーバスを踏んできたり、なんとも名状しがたいリフがうねうねとその様相を変えていくさま(曲によってはオーストラリアのデスメタルバンドPortalにも通じるところがある、あそこまであからさまにテクニカルではないのだが。)など、微妙にその姿を変えていくのも面白い。かなり強靭なリズム(金属質でインダストリアル、といっても良いくらい。)が一本曲を貫いているのだが、メロディというわかりやすい取っ掛かりが一切排除されているため、全体的に茫洋とした音になっており、聴いている人がどこにいるのかがわかりにくい。昔のゲームだと画面がスクロールしても同じような景色が続く「迷いの森」的なステージがあったのだが(流石に今はないんだろうな〜)、ああい言う感じで執拗かつ陰湿に曲が練られており、聞き手は自分の居場所がわからなくなってしまうのだ。こういうふうに曲を作るバンドというのは実はあまりいないのではなかろうか。非常に面白い。「私たちには別の美意識がある。」と言い放つのもなかなかすごいが、有言実行なのはさらにすごい。
かなりわかりにくいアルバムなのだが10曲を34分弱にまとめており、気がつくと終わっている。この突き放したような感じが良い。悪夢のサントラみたいな感じ。
なかなか万人におすすめできるアルバムではないが、激しい音楽に攻撃性だけを求めるのではなく、もっと暗い世界観が好きなんだと言う人なら聴いてみると良いのではと。あとは実験的な音楽が好きな人はブラックメタルのフォーマットでやっているこのアルバムを聞いてどんな感想を持つか知りたいところ。
2017年にDebemur Morti Productionsからリリースされた。
1994年から活動しており2011年からコンセプチュアルな3枚のアルバムをリリースして話題になっていたバンド。当時はなんとなく横目で見ていただけだけど今回はじめて買ってみた。
タイトルはラテン語で翻訳すると「私の神」となるようだ。覆面被った三人組なのだが、日本のwikiにかなり情報があって、そちらによると意外にも悪魔崇拝が売りの典型的なブラックメタル・バンドとは違うんだよ、ということらしい。おどろおどろしいイメージや音を使っているが、どうも独自の世界観を作ろうというバンドらしい。
実際に聞いてみるとなるほどかなり尖った音の作りになっている。音質悪くも生々しいプリミティブ・ブラックメタルとも違うし、デスメタルと融合しつつある力強くモダンで攻撃的なブラックメタルとも異なる。陰湿な世界観をややノイズに接近した音の作りで、決して速くないもったりとした速度で瘴気が滞留するように垂れ流す不穏な音世界。低音からずるっと滑るように滑らかに耳障りな高音に移行するギターリフ。ぐしゃっと潰れた低音や朗々とした詠唱めいた呪術的なボーカルが特徴的で、なんとなくDeathspell Omegaっぽいな、というのがファースト・インプレッション。もちろんこちらのバンドのほうが活動歴は長いのだが。ブラックメタルの武器であるブリザードのように寒々しいトレモロの中にうっすら見える美メロ、というのはもう気前よく捨てて別の次元で勝負しようというアルバム。(どうもアルバムごとにだいぶ作風を変えてくるバンドらしい。)
このアルバムを聴いて思ったのはかなりテクノ的ではないか?ということ。中心となるリフがあってそれをもったーり執拗に反復していく。かなりミニマル。ボーカルが変幻自在に唸ったりするもので一見してわかりにくいのだが、ふと我に返ると同じところをぐるぐると迷っていことに気がつく。途中でツーバスを踏んできたり、なんとも名状しがたいリフがうねうねとその様相を変えていくさま(曲によってはオーストラリアのデスメタルバンドPortalにも通じるところがある、あそこまであからさまにテクニカルではないのだが。)など、微妙にその姿を変えていくのも面白い。かなり強靭なリズム(金属質でインダストリアル、といっても良いくらい。)が一本曲を貫いているのだが、メロディというわかりやすい取っ掛かりが一切排除されているため、全体的に茫洋とした音になっており、聴いている人がどこにいるのかがわかりにくい。昔のゲームだと画面がスクロールしても同じような景色が続く「迷いの森」的なステージがあったのだが(流石に今はないんだろうな〜)、ああい言う感じで執拗かつ陰湿に曲が練られており、聞き手は自分の居場所がわからなくなってしまうのだ。こういうふうに曲を作るバンドというのは実はあまりいないのではなかろうか。非常に面白い。「私たちには別の美意識がある。」と言い放つのもなかなかすごいが、有言実行なのはさらにすごい。
かなりわかりにくいアルバムなのだが10曲を34分弱にまとめており、気がつくと終わっている。この突き放したような感じが良い。悪夢のサントラみたいな感じ。
なかなか万人におすすめできるアルバムではないが、激しい音楽に攻撃性だけを求めるのではなく、もっと暗い世界観が好きなんだと言う人なら聴いてみると良いのではと。あとは実験的な音楽が好きな人はブラックメタルのフォーマットでやっているこのアルバムを聞いてどんな感想を持つか知りたいところ。
ラベル:
Blut aus Nord,
ブラックメタル,
フランス,
音楽
アルフレッド・ベスター/ベスター傑作選 イヴのないアダム
アメリカの作家の短編小説集。
アルフレッド・ベスターである。SFのオールタイムベストを出すと必ず名前の出て来る「虎よ、虎よ!」の作者である。私も学生時代に寺田克也さんの表紙の文庫本を今はなき渋谷のビルまるごとブックファーストで購入したのだった。アレクサンドル・デュマの「巌窟王」(私は子供の頃青い鳥文庫で読んだだけなんだけど)を下敷きにした、広大な宇宙を舞台にした一人の男の執念の復讐譚であり、その壮大な、壮大なストーリーともはや一つの記念碑のようになっているラストでもって私は心臓を顔に入れ墨のある大男(「虎よ、虎よ!」の主人公)とベスターに鷲掴みにされたのである。いつかこの現実から青ジョウントしたいものだ、と今も思っている。(完全に余談だがその後私の「虎よ、虎よ!」はゴールディングの「蝿の王」とともに飼い猫のおしっこを引っ掛けられ泣く泣く捨てたので、いい加減買い直そうかなと思っている。)
その後最近になって「分解された男」を読み、これは完全にディストピアを書いた小説だと一人頷いたものだ。そして今度は短編集がでるというので喜び勇んで買ったわけ。ちなみにこの本の後書きによるとベスターは作家以外(コミック、ラジオ、ドラマのシナリオライター)の活動期間も長く、あまり作品自体は書いていなかったようなのだ。たしかにあとは「ゴーレム100」くらいなのかな?日本で出ているのは。(他の短編集はおそらく収録作品がこの本とかぶっている。)
SFで描かれる未来というのはたいてい暗いものだが、ベスターは輪にかけて苦い世界を書く。2つの長編でもそうだったが、短編となると壮大さにはページを割かない分その苦さがより個人的なものになっており、範囲が狭まった分より生々しくなっている。ベスターの描く未来というのは人間を幸福にするはずの科学や近代的な思想が、取り扱う人間の愚かさ故に人間を苦しめる枷になっているというもので、未来に行けば行くほどその枷が重くなっているようだ。つまり人間は根本的に良い方向に進化せず、愚かなままだと言っているようだ。暴力は高きから低きに流れ、常にその時弱いものがツケを払わされている。技術がむしろ人間の愚かさを無遠慮に露呈している。星まで到達しているのに相変わらず人間たちは騙し、妬み、互いに殺し合っている。「地獄は永遠に」では5分の4の地獄は現代のことであった。ベスター流として一見華麗な世界を醜く暴くというやり方に心血をそいでいるというところがあって、実は人間の内面を描いているとしても、人間の内面の不可解さ(ことさら否定的、批判的ではないと思う。)を冷静に書こうとするバラードなんかとは明らかに一線を画している。ベスターのほうが情熱的だが、その持ち味は暗く一般受けはしないだろうなと思う。ただ徹底的に人間嫌いがベスターなわけではなく、この短編では唯一「時と三番街と」だけが異彩を放っている。そこで書かれているのは人間の善性への期待であり、この善性というのは生まれ持って備えたものというよりは、未熟な状態で生まれ持ったそれをしがらみの多い暗い世界で、考えることで人類はまだ発揮することができるのだ、というベスター流の期待が描かれており、そういった意味では非常に希望のある作品である。「虎よ、虎よ!」のラストを思い出してほしい。あのラストは本法に絶望だけしている人間には決して書けないということは沢山の人にわかってもらえると思う。多くは語れないが、あそこにはベスターの希望が圧倒的なカタルシスになって詰まっていると思っている。あそこがないと「虎よ、虎よ!」はだめなんだ。あそこに向かって無茶苦茶な速度で分解しながら落ちていくような、そんな小説なんだと私は思っているので、そういった意味ではやはりこの短編集の中にも、ベスターのそんな思いを感じ取ってやはりじーんと熱くなってしまうのであった。
手頃にベスターの作品を味わえるという意味では非常に良い短編集。短いながらも暗い世界観がぎっちり。ここを通過してぜひ「虎よ、虎よ!」を読んでほしいと思う。
アルフレッド・ベスターである。SFのオールタイムベストを出すと必ず名前の出て来る「虎よ、虎よ!」の作者である。私も学生時代に寺田克也さんの表紙の文庫本を今はなき渋谷のビルまるごとブックファーストで購入したのだった。アレクサンドル・デュマの「巌窟王」(私は子供の頃青い鳥文庫で読んだだけなんだけど)を下敷きにした、広大な宇宙を舞台にした一人の男の執念の復讐譚であり、その壮大な、壮大なストーリーともはや一つの記念碑のようになっているラストでもって私は心臓を顔に入れ墨のある大男(「虎よ、虎よ!」の主人公)とベスターに鷲掴みにされたのである。いつかこの現実から青ジョウントしたいものだ、と今も思っている。(完全に余談だがその後私の「虎よ、虎よ!」はゴールディングの「蝿の王」とともに飼い猫のおしっこを引っ掛けられ泣く泣く捨てたので、いい加減買い直そうかなと思っている。)
その後最近になって「分解された男」を読み、これは完全にディストピアを書いた小説だと一人頷いたものだ。そして今度は短編集がでるというので喜び勇んで買ったわけ。ちなみにこの本の後書きによるとベスターは作家以外(コミック、ラジオ、ドラマのシナリオライター)の活動期間も長く、あまり作品自体は書いていなかったようなのだ。たしかにあとは「ゴーレム100」くらいなのかな?日本で出ているのは。(他の短編集はおそらく収録作品がこの本とかぶっている。)
SFで描かれる未来というのはたいてい暗いものだが、ベスターは輪にかけて苦い世界を書く。2つの長編でもそうだったが、短編となると壮大さにはページを割かない分その苦さがより個人的なものになっており、範囲が狭まった分より生々しくなっている。ベスターの描く未来というのは人間を幸福にするはずの科学や近代的な思想が、取り扱う人間の愚かさ故に人間を苦しめる枷になっているというもので、未来に行けば行くほどその枷が重くなっているようだ。つまり人間は根本的に良い方向に進化せず、愚かなままだと言っているようだ。暴力は高きから低きに流れ、常にその時弱いものがツケを払わされている。技術がむしろ人間の愚かさを無遠慮に露呈している。星まで到達しているのに相変わらず人間たちは騙し、妬み、互いに殺し合っている。「地獄は永遠に」では5分の4の地獄は現代のことであった。ベスター流として一見華麗な世界を醜く暴くというやり方に心血をそいでいるというところがあって、実は人間の内面を描いているとしても、人間の内面の不可解さ(ことさら否定的、批判的ではないと思う。)を冷静に書こうとするバラードなんかとは明らかに一線を画している。ベスターのほうが情熱的だが、その持ち味は暗く一般受けはしないだろうなと思う。ただ徹底的に人間嫌いがベスターなわけではなく、この短編では唯一「時と三番街と」だけが異彩を放っている。そこで書かれているのは人間の善性への期待であり、この善性というのは生まれ持って備えたものというよりは、未熟な状態で生まれ持ったそれをしがらみの多い暗い世界で、考えることで人類はまだ発揮することができるのだ、というベスター流の期待が描かれており、そういった意味では非常に希望のある作品である。「虎よ、虎よ!」のラストを思い出してほしい。あのラストは本法に絶望だけしている人間には決して書けないということは沢山の人にわかってもらえると思う。多くは語れないが、あそこにはベスターの希望が圧倒的なカタルシスになって詰まっていると思っている。あそこがないと「虎よ、虎よ!」はだめなんだ。あそこに向かって無茶苦茶な速度で分解しながら落ちていくような、そんな小説なんだと私は思っているので、そういった意味ではやはりこの短編集の中にも、ベスターのそんな思いを感じ取ってやはりじーんと熱くなってしまうのであった。
手頃にベスターの作品を味わえるという意味では非常に良い短編集。短いながらも暗い世界観がぎっちり。ここを通過してぜひ「虎よ、虎よ!」を読んでほしいと思う。
ラベル:
SF,
アメリカ,
アルフレッド・ベスター,
短編集,
本
香山滋/海鰻荘奇談 香山滋傑作選
日本の作家香山滋の短編集。河出文庫の<探偵・怪奇・幻想シリーズ>の一冊としてリリースされた。今庵野秀明監督の「シン・ゴジラ」を皮切りに今何回目かのゴジラ・ブームなのだろうけど、その「ゴジラ」の原作を書いたのがこの香山滋という人。1904年生まれで昭和の時代に活躍した文人。私は多分短編一つも読んだことがなかったと思うが、名前は知っていたのでなんとなく買ってみた次第。怪奇も幻想も好きなので。
奇妙なタイトルは海の鰻とかいて「かいまん」と読む。海鰻というのはうつぼのこと。
冒頭を飾るデビュー作「オラン・ペンデクの復讐」を少し読めばそこにあるのは重厚なで大仰な文体で飾られた昔日の怪奇譚で、例えば夢野久作の「ドグラ・マグラ」を読み始めたときのような、「ああ私は今現代とはかけ離れた異郷の地のような世界に足を踏みれたぞ」というようなくらっとする感覚が味わえて興奮する。この頃の日本の小説にしか出ない味ではなかろうか。一体ラブクラフトの小説もそうだが超自然という”不自然”をあたかも存在するかのように描写するには、かなり凝った下準備と言うか舞台装置が必要で、その一つが仰々しい文体ではなかろうかと思っている。(音楽ジャンルとしてのメタルに少し通じるところがあると思う。)おそらくだが完全な幻想文学というのはやはり日本では(外国ではどうなのだろうか)なかなかやっていくのが難しいのだろう。香山滋もその溢れ出る怪奇への情熱をミステリーという鋳型に収めるように整形して小説を組み立てている。物語の中心となるのは殺人であり、それを取り巻くのは血と汗の匂いのする人間たち、そしてその周囲に異形の者の影がちらつくというやり方だ。やはりどうしても江戸川乱歩の世界を思い出してしまうのは仕方ないだろうと思う。(ちなみにあとがきを読むと乱歩も香山滋のことをよく評価しているようだ。)
精密な”怪奇”を描くにあたって香山が武器にしているのが博物学というか、生物と植物に対する深い造詣と図鑑的な説明文の大胆な挿入だろう。動植物にしても一般に流布している名称でなくて、学名をいちいち入れてきたりと、異常さをアピールすることに余念がない。これらはあくまでも作者にとって道具であって説明に終始しないところも結構読みやすさを意識して描いている姿勢が見て取れる。
もう一つ面白いのが”憧れ”でこれは具体的には地球上にまだある未開の地へのあこがれである。衛生で地球の地表上ほぼすべてを網羅できる現代では難しいかもしれないが、昭和の時代ならまだ人類未踏破の未知の世界があり、そこには文明に発見されていない全く目新しい生物、植物が溢れているだろうという考えである。(もっともいくら昭和でもないのはわかっているけどやはり憧れを抑えきれない、という知識人の心持ちだったのではないかと思うけど。)その憧憬が絶海の孤島のトカゲだらけの島や、ゴビ砂漠の奥地から来た未知の蝶だったりという要素を生み出す一つの理由になっているように思う。まったく私達の世界の理論とは別の思考体型で動き躍動する生命の野蛮さというのが、半端に文明化された私達の心に不思議なノスタルジックさ(人間はいったことのない土地、存在したことのない土地にもノスタルジーを感じることができる。)を呼び起こす。
エロとグロをしっかり抑えているし、この時代の怪奇にどっぷり浸りたいという人には文句無しでおすすめの一冊。
奇妙なタイトルは海の鰻とかいて「かいまん」と読む。海鰻というのはうつぼのこと。
冒頭を飾るデビュー作「オラン・ペンデクの復讐」を少し読めばそこにあるのは重厚なで大仰な文体で飾られた昔日の怪奇譚で、例えば夢野久作の「ドグラ・マグラ」を読み始めたときのような、「ああ私は今現代とはかけ離れた異郷の地のような世界に足を踏みれたぞ」というようなくらっとする感覚が味わえて興奮する。この頃の日本の小説にしか出ない味ではなかろうか。一体ラブクラフトの小説もそうだが超自然という”不自然”をあたかも存在するかのように描写するには、かなり凝った下準備と言うか舞台装置が必要で、その一つが仰々しい文体ではなかろうかと思っている。(音楽ジャンルとしてのメタルに少し通じるところがあると思う。)おそらくだが完全な幻想文学というのはやはり日本では(外国ではどうなのだろうか)なかなかやっていくのが難しいのだろう。香山滋もその溢れ出る怪奇への情熱をミステリーという鋳型に収めるように整形して小説を組み立てている。物語の中心となるのは殺人であり、それを取り巻くのは血と汗の匂いのする人間たち、そしてその周囲に異形の者の影がちらつくというやり方だ。やはりどうしても江戸川乱歩の世界を思い出してしまうのは仕方ないだろうと思う。(ちなみにあとがきを読むと乱歩も香山滋のことをよく評価しているようだ。)
精密な”怪奇”を描くにあたって香山が武器にしているのが博物学というか、生物と植物に対する深い造詣と図鑑的な説明文の大胆な挿入だろう。動植物にしても一般に流布している名称でなくて、学名をいちいち入れてきたりと、異常さをアピールすることに余念がない。これらはあくまでも作者にとって道具であって説明に終始しないところも結構読みやすさを意識して描いている姿勢が見て取れる。
もう一つ面白いのが”憧れ”でこれは具体的には地球上にまだある未開の地へのあこがれである。衛生で地球の地表上ほぼすべてを網羅できる現代では難しいかもしれないが、昭和の時代ならまだ人類未踏破の未知の世界があり、そこには文明に発見されていない全く目新しい生物、植物が溢れているだろうという考えである。(もっともいくら昭和でもないのはわかっているけどやはり憧れを抑えきれない、という知識人の心持ちだったのではないかと思うけど。)その憧憬が絶海の孤島のトカゲだらけの島や、ゴビ砂漠の奥地から来た未知の蝶だったりという要素を生み出す一つの理由になっているように思う。まったく私達の世界の理論とは別の思考体型で動き躍動する生命の野蛮さというのが、半端に文明化された私達の心に不思議なノスタルジックさ(人間はいったことのない土地、存在したことのない土地にもノスタルジーを感じることができる。)を呼び起こす。
エロとグロをしっかり抑えているし、この時代の怪奇にどっぷり浸りたいという人には文句無しでおすすめの一冊。
椎名誠/水域
日本の作家によるSF小説。
椎名誠さんのSF小説はたくさんあるけど、初期の(1990年台)三部作みたいになっているのが「アド・バード」、「武装島田倉庫」、そしてこの「水域」。前の2冊に関しては賞をとったり、漫画化されたり(ちなみに何回も言っているけど「武装〜」の方は弐瓶勉さんの漫画「BLAME!」の元ネタの一つでもある。)しているので手に入りやすいのだけど「水域」だけは結構前から絶版状態。いつか読もうと思っていたけどようやく買ってみた。
地球が水に覆われた未来。当て所なく海流の赴くままに世界を旅する男。偶然手に入れた筏に書いてあるローマ字から「HARU」と名乗り、奇妙に変形した生物、そして荒廃した世界に適応した野蛮な人間たちと出会っていく。
いわゆるポスト・アポカリプスもので現在の文明はほとんど滅びている。海の水位が上昇し地球全体を覆う、というのはそういった映画があったと思う(有名な俳優が出ているやつで中身はあまり覚えていない)。椎名誠さんはたくさんのSFを書いていて、実は一貫しているような世界があるのだが、この物語はどうもその世界には属していないように思える。いわゆる「北政府」ものじゃないんじゃないかなと。あっちの世界でもやはり文明は一度崩壊しているのだが、海は油の被膜で覆われてほとんど曇天が重たくのしかかっているはず。地域が違うという可能性もあるが、「水域」では海は割ときれいで雨はどちらかと言うと珍しいみたいなので。
「つがね」や「ねご銃」などの椎名流の一風変わった(最先端だがどこか土着的な匂いのする)テクノロジーはほぼ出てこないというところも相違点の一つ。なんせほとんど海の上、と言うか水の上(場所によっては淡水だったりするのも天変地異が予想できて面白いところだ。)ということもあって余り”物”自体がない。そういう世界で人間とその生活がどうなるかというとより原始的になってくる。やはり敵性勢力(人やそれ以外)も出て来るが、争い方はより地味で生々しい。椎名さんの小説は一言で言うと「生命力」だと思う。前述のテクノロジーや特異な状況でも「生命力」は発揮されるが、SFのヴェールでやや隠れがちになってしまう。それが「水域」では存分に発揮されている。水の上なのでボートを漕ぐといっても限りがある(海流は強く、流れに逆らって漕ぐのは数時間が限度)、食べ物は魚をとるしかない(水はろ過装置がある)。こんな世界では生命力を発揮する前に魚が取れなかった死ぬし、ボートや筏から落ちたら死ぬし、サバイブすること自体が軽く奇跡めいている。自分の足ですら歩けない世界は非常に過酷である。文明に属する我々からすると恐ろしい世界に落ち込みそうになるが、登場人物たちは基本的に前向きである。彼らからしたら生きるのに必死で落ち込んでいる隙がない。基本的に今を生きて行くしかない。人間の本性は野蛮だとか、文明がなければこんなものだというような説教臭さはまったくなく、死に物狂いで生きて、それでだめならもうダメだ、という達観めいたのんきさ(これが生命力の行き着くところなのかもしれない。争いはじつは効率が悪い。)が全体を覆っていて、状況の悲惨さを緩和している。(というか悲惨さを受けれるしかない、という心構えがデフォルトになっている感じ。つまり悲惨の総量は減じてない。)究極のその日暮らしで、自分がどこに向かっているかもわからず海流任せ。人にあったらどうしても武器は構え無くてはならない。そんな世界。
主人公は「ハル」と名乗るがこれは本名ではない。無名の男でこれはつまり主人公は誰でもあるってことだ。一人の誰でもない、つまり誰でもある(あなたや私である)男の水の上のロードムービー、つまり人生の縮図が淡々とした筆致で軽やかに描かれていく。メタファーとしてのSFというよりは、見るものすべてが新しい、見慣れないという純粋な驚嘆を描くための、作者お手製のよくわからない魚達、植物たち。ここで重要なのは彼らとの関係性だ。よくわからない生き物を書くことはできても、その「よくわからない」たちとのふれあいをこうもリアルに掛けるのはおそらくこの作家だけってことはないだろうけど、やっぱり非常に稀有だと思う。「よくわからない」を捕まえて食べるのはもちろん、「よくわからない」がいっぱいの森を切り開いて歩く時に、手をついた木の幹に張り付く「よくわからない」の奇妙な感触などなどが実際に存在するかのように生々しく描写されている。やはりハードコアな旅人としての作者の経験、膨大な知識量があってこその芸当だと思う。サラリと書いているが確実に唯一無二だ。
作者本人も読みやすいと書いているし、このように素晴らしい本がなぜ長いこと絶版なのかわからない。もっと多くの人に読んでほしいのだが。別にSFに限らず、上質の人生にとっての栄養である「センス・オブ・ワンダー」を求めるなら手にとって絶対に間違いない。
椎名誠さんのSF小説はたくさんあるけど、初期の(1990年台)三部作みたいになっているのが「アド・バード」、「武装島田倉庫」、そしてこの「水域」。前の2冊に関しては賞をとったり、漫画化されたり(ちなみに何回も言っているけど「武装〜」の方は弐瓶勉さんの漫画「BLAME!」の元ネタの一つでもある。)しているので手に入りやすいのだけど「水域」だけは結構前から絶版状態。いつか読もうと思っていたけどようやく買ってみた。
地球が水に覆われた未来。当て所なく海流の赴くままに世界を旅する男。偶然手に入れた筏に書いてあるローマ字から「HARU」と名乗り、奇妙に変形した生物、そして荒廃した世界に適応した野蛮な人間たちと出会っていく。
いわゆるポスト・アポカリプスもので現在の文明はほとんど滅びている。海の水位が上昇し地球全体を覆う、というのはそういった映画があったと思う(有名な俳優が出ているやつで中身はあまり覚えていない)。椎名誠さんはたくさんのSFを書いていて、実は一貫しているような世界があるのだが、この物語はどうもその世界には属していないように思える。いわゆる「北政府」ものじゃないんじゃないかなと。あっちの世界でもやはり文明は一度崩壊しているのだが、海は油の被膜で覆われてほとんど曇天が重たくのしかかっているはず。地域が違うという可能性もあるが、「水域」では海は割ときれいで雨はどちらかと言うと珍しいみたいなので。
「つがね」や「ねご銃」などの椎名流の一風変わった(最先端だがどこか土着的な匂いのする)テクノロジーはほぼ出てこないというところも相違点の一つ。なんせほとんど海の上、と言うか水の上(場所によっては淡水だったりするのも天変地異が予想できて面白いところだ。)ということもあって余り”物”自体がない。そういう世界で人間とその生活がどうなるかというとより原始的になってくる。やはり敵性勢力(人やそれ以外)も出て来るが、争い方はより地味で生々しい。椎名さんの小説は一言で言うと「生命力」だと思う。前述のテクノロジーや特異な状況でも「生命力」は発揮されるが、SFのヴェールでやや隠れがちになってしまう。それが「水域」では存分に発揮されている。水の上なのでボートを漕ぐといっても限りがある(海流は強く、流れに逆らって漕ぐのは数時間が限度)、食べ物は魚をとるしかない(水はろ過装置がある)。こんな世界では生命力を発揮する前に魚が取れなかった死ぬし、ボートや筏から落ちたら死ぬし、サバイブすること自体が軽く奇跡めいている。自分の足ですら歩けない世界は非常に過酷である。文明に属する我々からすると恐ろしい世界に落ち込みそうになるが、登場人物たちは基本的に前向きである。彼らからしたら生きるのに必死で落ち込んでいる隙がない。基本的に今を生きて行くしかない。人間の本性は野蛮だとか、文明がなければこんなものだというような説教臭さはまったくなく、死に物狂いで生きて、それでだめならもうダメだ、という達観めいたのんきさ(これが生命力の行き着くところなのかもしれない。争いはじつは効率が悪い。)が全体を覆っていて、状況の悲惨さを緩和している。(というか悲惨さを受けれるしかない、という心構えがデフォルトになっている感じ。つまり悲惨の総量は減じてない。)究極のその日暮らしで、自分がどこに向かっているかもわからず海流任せ。人にあったらどうしても武器は構え無くてはならない。そんな世界。
主人公は「ハル」と名乗るがこれは本名ではない。無名の男でこれはつまり主人公は誰でもあるってことだ。一人の誰でもない、つまり誰でもある(あなたや私である)男の水の上のロードムービー、つまり人生の縮図が淡々とした筆致で軽やかに描かれていく。メタファーとしてのSFというよりは、見るものすべてが新しい、見慣れないという純粋な驚嘆を描くための、作者お手製のよくわからない魚達、植物たち。ここで重要なのは彼らとの関係性だ。よくわからない生き物を書くことはできても、その「よくわからない」たちとのふれあいをこうもリアルに掛けるのはおそらくこの作家だけってことはないだろうけど、やっぱり非常に稀有だと思う。「よくわからない」を捕まえて食べるのはもちろん、「よくわからない」がいっぱいの森を切り開いて歩く時に、手をついた木の幹に張り付く「よくわからない」の奇妙な感触などなどが実際に存在するかのように生々しく描写されている。やはりハードコアな旅人としての作者の経験、膨大な知識量があってこその芸当だと思う。サラリと書いているが確実に唯一無二だ。
作者本人も読みやすいと書いているし、このように素晴らしい本がなぜ長いこと絶版なのかわからない。もっと多くの人に読んでほしいのだが。別にSFに限らず、上質の人生にとっての栄養である「センス・オブ・ワンダー」を求めるなら手にとって絶対に間違いない。
2017年12月3日日曜日
Gnaw/Cutting Pieces
アメリカ合衆国はニューヨーク州ニューヨークシティのドローン・ドゥーム/ノイズバンドの3rdアルバム。
2017年にTranslation Loss Recordsからりリリースされた。
私はすでに解散済みのKhanateというバンドが大好き。メンバーはギタリストにSunn O)))などで活躍中のStephen O'Malleyに、ベースとしてアーティストだけでなくエンジニアとしても活動するJames Plotkin、ドラム担当がPlotkinとO.L.D.というバンドを組んでいたTim Wyskida、そしてボーカルがAlan Dubinである。
Khanate解散後Alanが始めたのがこのGnaw。Khanateはトーチャースラッジとして始まり、初期はそれこそGriefを叩きのめしたようなサウンドにハードコアというよりはメタル的案猟奇的な世界観をぶち込んだバンドで、後期になるに従いドローンやフリー・ジャズのようなアバンギャルドな要素の色を濃く打ち出していった。Sunn O)))はドローンの要素を色濃くKhanateから引き継いでいるが結果的に世界観は結構違う。GnawはよりわかりやすくKhanateの要素を受け継ぐバンドというイメージ。
O'MalleyとPlotkinという重量級の弦楽隊はなくなったものの、その空隙をうまく活かし、代わりにいやらしく這い回るノイズ分を充当している。Khanateも1stからノイズの要素が強かったのでそこも含めて違和感のない移行といえる。バンドアンサンブルに加えて専門のマニュピュレイターもメンバーに数える力の入れよう。
そんな最新作、基本的に前作・全前作からの流れを踏襲するものだが後半に流れるにしたがい、少しずつ音の形を変えてきているように感じる。具体的には音の数が減らされてきているように思う。1stアルバムだととにかく「Vacant」が好きなのだがこの曲はノイズが実態の重量を持って這い回るどころか屍衣のように曲を覆い尽くす、まさに重たさの塊みたいだった。今回はノイズ成分をうまくコントロールし、偏執病的に空隙をノイズで埋めていく、という作業からは幾分開放されている。khanateも活動時期の後半でも重たさ、重苦しさを別の次元に求めていたから同じような動きがこのGnawでも辿られているようだ。khanateは強烈な個性のぶつかり合いがせめぎあうバンドだった。スラッジから始まってもその範疇にとどまらないくらい(つまり文脈的にはハードコアというよりはメタル的な物語を感じさせるように)陰湿だった。猟奇的だった。病んでいた。この手のジャンルでは生命線である、”強くあること”という衣を剥ぎ取り、ソフトかつ捻くれて醜い中身をさらけ出していた。(ただスラッジは自己評価が低く、自己卑下が強い傾向にあると思う。)高い声で絶叫するAlanは、卑屈に笑みを浮かべる一見無害なやつだが、その実シリアル・キラーという物語/個性を打ち出しており、khanateもその魅力の一つとしてをそこに頼むところが大きかったように思う。その世界観をAlanは変わらず持ち続け、このバンドでも打ち出してきている。ベッドの下にばらばらになった死体を隠し持つように、透明人間が誰にも見られず溺死するように、今度のバンドでも誰かをバラバラに刻もうとしている。Alanの声にはなんとも言えない”弱さ”がある。(念のため言っているがAlan Dubinが現実的に弱い男であるというのでは断じてない。)体力で勝てない弱さ、自分の暗い欲望に屈してしまう弱さ、そんな強い世界(音楽という仮面のために作られた偽りの世界でもあることも往々にある。)では唾棄すべき弱さ、病的な性質がここではたちの悪い粘菌類のようにはびこっており、私にようなじめじめといじけた卑屈な人間はそういった場所こそが居場所がいいのだった。
壁にもたれかかり、猟奇的な夢想にふけるように、耽美な腐敗(現実ではありえない)が妙に時間を引き伸ばされているように、ぐーっと視界と思考の奥に伸びていく、そんな風景があえて音の重さを引き抜くことでもたらされている。質の悪い悪夢に囚われたような無力感に抵抗するすべもないような、どこかしら投げやりな客観性が獲得されつつあるように思える。「This can't be the right」「This must be the wrong place」と歌うように、現実に対する絶望的な違和感と、そこに育まれる正しくない感情の萌芽がこのGnawのテーマの一つではなかろうか。
思春期にサイコパス、シリアル・キラーの文献、ネットを読み漁ったような人なら確実にこの世界観にハマるのではなかろうか。拗けて間違っているが、だからこそ居心地が良いのだ。やはりAlan Dubinはかっこいい。おすすめ。
2017年にTranslation Loss Recordsからりリリースされた。
私はすでに解散済みのKhanateというバンドが大好き。メンバーはギタリストにSunn O)))などで活躍中のStephen O'Malleyに、ベースとしてアーティストだけでなくエンジニアとしても活動するJames Plotkin、ドラム担当がPlotkinとO.L.D.というバンドを組んでいたTim Wyskida、そしてボーカルがAlan Dubinである。
Khanate解散後Alanが始めたのがこのGnaw。Khanateはトーチャースラッジとして始まり、初期はそれこそGriefを叩きのめしたようなサウンドにハードコアというよりはメタル的案猟奇的な世界観をぶち込んだバンドで、後期になるに従いドローンやフリー・ジャズのようなアバンギャルドな要素の色を濃く打ち出していった。Sunn O)))はドローンの要素を色濃くKhanateから引き継いでいるが結果的に世界観は結構違う。GnawはよりわかりやすくKhanateの要素を受け継ぐバンドというイメージ。
O'MalleyとPlotkinという重量級の弦楽隊はなくなったものの、その空隙をうまく活かし、代わりにいやらしく這い回るノイズ分を充当している。Khanateも1stからノイズの要素が強かったのでそこも含めて違和感のない移行といえる。バンドアンサンブルに加えて専門のマニュピュレイターもメンバーに数える力の入れよう。
そんな最新作、基本的に前作・全前作からの流れを踏襲するものだが後半に流れるにしたがい、少しずつ音の形を変えてきているように感じる。具体的には音の数が減らされてきているように思う。1stアルバムだととにかく「Vacant」が好きなのだがこの曲はノイズが実態の重量を持って這い回るどころか屍衣のように曲を覆い尽くす、まさに重たさの塊みたいだった。今回はノイズ成分をうまくコントロールし、偏執病的に空隙をノイズで埋めていく、という作業からは幾分開放されている。khanateも活動時期の後半でも重たさ、重苦しさを別の次元に求めていたから同じような動きがこのGnawでも辿られているようだ。khanateは強烈な個性のぶつかり合いがせめぎあうバンドだった。スラッジから始まってもその範疇にとどまらないくらい(つまり文脈的にはハードコアというよりはメタル的な物語を感じさせるように)陰湿だった。猟奇的だった。病んでいた。この手のジャンルでは生命線である、”強くあること”という衣を剥ぎ取り、ソフトかつ捻くれて醜い中身をさらけ出していた。(ただスラッジは自己評価が低く、自己卑下が強い傾向にあると思う。)高い声で絶叫するAlanは、卑屈に笑みを浮かべる一見無害なやつだが、その実シリアル・キラーという物語/個性を打ち出しており、khanateもその魅力の一つとしてをそこに頼むところが大きかったように思う。その世界観をAlanは変わらず持ち続け、このバンドでも打ち出してきている。ベッドの下にばらばらになった死体を隠し持つように、透明人間が誰にも見られず溺死するように、今度のバンドでも誰かをバラバラに刻もうとしている。Alanの声にはなんとも言えない”弱さ”がある。(念のため言っているがAlan Dubinが現実的に弱い男であるというのでは断じてない。)体力で勝てない弱さ、自分の暗い欲望に屈してしまう弱さ、そんな強い世界(音楽という仮面のために作られた偽りの世界でもあることも往々にある。)では唾棄すべき弱さ、病的な性質がここではたちの悪い粘菌類のようにはびこっており、私にようなじめじめといじけた卑屈な人間はそういった場所こそが居場所がいいのだった。
壁にもたれかかり、猟奇的な夢想にふけるように、耽美な腐敗(現実ではありえない)が妙に時間を引き伸ばされているように、ぐーっと視界と思考の奥に伸びていく、そんな風景があえて音の重さを引き抜くことでもたらされている。質の悪い悪夢に囚われたような無力感に抵抗するすべもないような、どこかしら投げやりな客観性が獲得されつつあるように思える。「This can't be the right」「This must be the wrong place」と歌うように、現実に対する絶望的な違和感と、そこに育まれる正しくない感情の萌芽がこのGnawのテーマの一つではなかろうか。
思春期にサイコパス、シリアル・キラーの文献、ネットを読み漁ったような人なら確実にこの世界観にハマるのではなかろうか。拗けて間違っているが、だからこそ居心地が良いのだ。やはりAlan Dubinはかっこいい。おすすめ。
FAIRLYSOCIALPRESS presents [BOYS DON`T CRY 5]@初台WALL
たまにあることだけど12月2日(土)のライブイベントのかぶり方と行ったら豪華という水準を高く通り越し、もはや残酷だった。スケートパークで轟音に浸るというのも一興だし、killieの凄まじいライブをもう一度みたいというのもある。しかし自分は何回かライブを見たSaigan Terrorというバンドがよく消化できなかったのでその音源欲しさに初台に行くことにした。この日はSaigan TerrorとFight It Outのスプリット7インチのレコ発なのだ。日本のヒップホップのアーティストも名を連ねているので、ヒップホップのライブも見てみたいな、という気持ちもあったので。
ライブハウスにつくとすでにもうかなりの客が入っていてかなりキュウキュウだった。WALLは入り口に「〇〇(多分バンドなのだろう)の☓☓とヴィジュアル系出入り禁止」みたいな張り紙がしてあり、私はどうみてもヴィジュアル系ではないがなんというかハードコアな雰囲気がしてちょっと怖いと思う。(実際怖めの人が多かったし、私のようなオタクっぽい人がいなくてさらに怖いというのがあります。)
ステージの前が不気味に人がいなくて不穏であり、これを見るとハードコアのライブに来てしまった…という感じがする。
Super Structure
一発目はSuper Structure。私は何回か見ているけど見るたびに好きになる、このバンドに関しては。この日もかなりとんがった音を出していた。後のFriendship、Fight It Outはとにかくパワーと音量がでかい。Super Structureも音はでかいのだが曲の方はもっとカオティックだ。別にプログレッシヴだ、カオティック・ハードコアだというのではないが、もっと混沌としている。変な言い方だがどの楽器もフルスピードで鳴らしまくった音が重なると奇跡的に曲に聞こえる、みたいな雰囲気がある。この日共演するバンドと比べると音はもっとざらつき、音の数は多い。パワーバイオレンスといっても流行とは一線を画す内容でもっとラフだ。例えば地獄のようなスラッジパートがあるわけでもない。甲高い、と評しても良いボーカルが激しく細かく忙しないバンドアンサンブルにさらにカオス感を注入している。バンド名は(あとから知ったのだけど)USのニュースクール・ハードコアバンドFall Silentの2ndアルバムからとっていることもあり、ルーツとなっているのがそういった音楽なので、パワーバイオレンスたろうとするパワーバイオレンスバンドとは明確に違う音に仕上がっているのではなかろうか。まさしく鉄砲玉、それも恐ろしく命中率が悪く乱射しまくるような凶悪なバンドで、ラストにやった「Despair」(だと思う。唯一気軽に聴けるこのバンドの音源でもある。)には中盤にギターの高音を響かせる地獄のようなモッシュパートがある。非常に格好いいのだ。私がお金持ちだったら最高の環境で音源を録音してもらうのにな、といつも思う。(音源出してほしいです。)
Friendship
続いてはFriendship。今年アルバムが出てからはみたっけな?結構見る回数が多いのは色んなイベントに招かれているからだろう。全くフレンドリーではないが、普通の意味とは違うキャッチーさがあって、それがわかりやすく”ハードコア”なので少しジャンルをまたぐようなイベントに引っ張りだこになるのかな、と思う。
Super Structureの直後ということもあって両者の違いが明確になる。こちらも非常にやかましいが音の数はぐっと減る。数というか密度だろうか。とにかくキチンと音を抜くことで重苦しいのに閉塞感から適度に脱しており、過密のコントロールが上手いのか、その結果ある意味ハードコアの枠組みだけ残したみたいな音楽になるのだが、それが非常に頑強で非常に暴れられる。初めてFriendshipを見た人でも絶対すぐに「のれ」ると思う。相変わらず一切MCはなく、ボーカルはほぼフロアに降りて歌う。毎回すごいと思うのは一切一体感は演出しない。シンガロングパートはもちろんないし、フロアに降りるボーカルも急に回りの客に向けてタックルを仕掛けてくる。みんなで楽しくモッシュ!って感じでもない。曲もそうだし、こういった姿勢の作り方というのも非常によく考えられている。「策士だね〜」というのではなくて、茨の道を我が物顔で進むな〜という感心の気持ちのほうが勝ってきた。若手、というのだけでなく、例えば私のような門外漢にとってのハードコアのゲートウェイになっていてそういった意味でもすごいバンドだ。
CENJU from DMC
続いては日本は東京のラッパー。実はヒップホップのライブを見るのは初めてかな?結構楽しみにしていた。CENJUはがっしりとした高身長と体躯に恵まれた大男でかなり迫力がある。低音のラップパートを同期させてそこにラップを被せていくように進む。これは合唱で言う下のパートってことだろうか。ヒップホップのライブは(他のラッパーは違うかもだけど)こうなんだな!と面白かった。強面なのは外見だけでなく、かなりハードな内容を噛み砕いた言葉でリリックにしたためるアーティストらしく、(ストリートのなんたるかを知らない私が言うのもちょっとおかしいのだけど)”ストリート感”のあるラップを披露する。つまりリアルでアンダーグラウンドな世界観である。悪いのだ。音の洪水を通り越し、もはや壁(WALLというライブハウスの名前は非常に格好いいと思う。)になっているハードコアとは全然ちがう音の数だ。とにかくシンプルに限界まで削ぎ落としたトラックが鋭い。そして鋭いだけでなく、煙たい、ダルいを表現する。これが良い。よくヒップホップのラップでは「スキル」という言葉が浮き彫りになるが、一人でステージに立つ(そうでない場合も多いが基本的にラップをするときは一人だ。)ラッパーは露骨にその出来にごまかしが効かない。タフな役回りだ。(それ故かっこいい。)CENJUは韻を踏みつつ結構フリーに煽ってくるタイプで客席を大いに沸かせていた。見た目に反して声は少し甘い感じがあるのが個人的には良かった。
Fight It Out
危ないことになるから後ろに下がったんだけど結局ダメでした…。
続いては横浜シティのパワーバイオレンスバンドFight it Out。この日の主役の片方でもある。バイオレンスを音にしたらこうなりました、というバンドで今年発売された3rdアルバムは私のようなオタクも聞いていると何か自分が強くなったように錯覚するようなブルータルなアルバムだった。ライブはモッシュ天国(普通の基準で考えればなぜ金を払ってそんなことを?と思わずにはいられない地獄)になるのは何回か見てことがあるので私は後ろに下がった 。WALLは後ろに長いライブハウスなのだが結果から言うとこの長さを活かした縦長のピットができて、だいたいほぼほぼ安全地帯がなし。全員が当事者に。
音の作り方はFriendshipと似ているモダンで金属的で良い感じに音の数を落としたものだが、こちらはもうモッシュに特化していると言っても良いかもしれない音で、Friendshipのような黒いヴェールのようなものもない粗野な音像。激速と激遅(げきおそ)を行ったり来たりするくせに神経症的な痙攣という病的な感じではなく、暴力性の発露のような運動性が特徴。そういった意味では健康的なのだろうか。あっという間にフロアにヘイトが感染して凶悪なモッシュパートが出来上がる。ボーカルの人はほぼフロアにいたのはFriendshipと同様だが、こちらはシンプルながらシンガロングできるパートがあったりしてモッシュピットに一定の法則、というよりは一つの指向性があったように思えた。腕を振り回す人、足を振り回す人、タックルをかます人、マイクを取りに(一緒に歌おうとしてね)行く人、サーフする人(カオスなのであまり長く上に居続けられない)、もみくちゃで後ろの方にもピットの動きが人を通して伝わってくる。ライブと音源の違い、というの一つのテーマに対する回答を明確にFight It Outが示し、そしてライブ(ともするとライブのみ)がリアルである、というのもうべなるかな、という状況でした。
ILL-TEE
つづいてはILL-TEE。DJの他にもう一人ラッパー、多分MASS-HOLEという人かな?がステージに立つ三人体制。トラックの内外とわず自由にやるCENJUに比べるとこの二人のラッパーはかなりかっちりタイトにトラックにリリックをはめ込んでくる。小節頭に言葉の喋りだしが噛み合ってこれはこれで非常に格好いい。やはりリアルな感じのするリリックだったと思うけど(固くて低い声質もあってCENJUに比べるとやや聞き取りにくい場面もあった。)、もう少し言葉遊びと陰陽の陽にあたるようなリリックもあってヒップホップの楽しさ、というのがわかりやすくそして最大限に発表されるようなステージングだった。ある意味淡々と韻を踏んでいくスタイルではじめは聞き惚れるような感じなのだけど、トラックとのかみ合わせが非常に良くてどんどん気持ちよくなってくる。フックのようなものもあってわかりやすい。ハードコアという明確に違うフィールドで徐々にヒップホップの楽しさ、というのがじわじわ浸透してくるようなライブでやはりもう最終的にはかなり前の方は盛り上がっていた。トラックがシンプルでビートが強いので実は乗りやすい、というのはあると思う。真面目と言っていいほどしっかりしていて格好良かった。
Saigan Terror
続いては東京高円寺のハードコアバンドで結成は1997年(素晴らしいインタビューより)。クロスオーバー、つまりこの場合はハードコアに刻みまくるスラッシュ・メタルをかけ合わせた音楽で私は何回かライブを見たかな?格好いいんだけど言語化するのが難しいな(音源もいまでは廃盤状態なので。)と思っていた。本日はスプリット発売の主役で堂々のトリ。
改めてライブを見るとこんなに重かったっけ?となったブラストビートが冴えまくり、ブラストビートに乗って突っ走るさまはもはやTerrorizerでは!?と思うくらい凄まじかった。よくよく聴いてみるとなるほど確かにグラインドコアというには音が良い感じに抜けていて、より疾走感が強調されているけどそれでも軽薄ということはまったくない。ブラストビートにすべてを掛ける、という音楽性でもなく、シンプルな2ビートが土台を作りそこに凝ってはいるが決してスピード感を減じさせない”刻み”のスラッシュリフが乗る。この日ドラムとともにすごいなと思ったのはベースで、おそらくエフェクターを噛ませて幾つかの音をコントロールしているのだが、かなり硬質で刻みのリフと相対するようなガーンとアタックしたあとミュートしない弾き方が、硬い地面に金属が跳ね返るような強烈さで非常に格好良かった。この日前の3つのバンドは共通点があってそれはとにかく突っ走るときは突っ走る、ということだったが、Saigan Terrorは速度はあってもミュートを用いたリフにはつんのめるような独特の粘りのあるコシが生まれているところが明確に異なる。つまり何が言いたいかというと他のバンドにはない「グルーヴィ」さが生まれていた。これはとにかくピットに反映されていて、Fight It Outの殺伐としてたピットと比べると同じことをやってい人はいるのだけど、もう少し多様性があり、ステップを踏む人やそれこそ女性の人もいた。そして沢山の人が笑顔だったのが一番印象的だった。危なくないわけではないけど、それを圧倒的に上回る楽しさ。ギタリストの方のキャラクターやMCもそんな雰囲気を作り出していくことに大いに寄与していると思う。 20年の貫禄がバチバチ発揮されていた唯一無二のサウンドだった。
もちろんスプリット音源(とZine)を購入してほうほうの体で帰宅。終始激しかったけど楽しかった。ライブを見に行く醍醐味に知らないバンドを知れる、というのがあると思うがそういった意味ではハードコアとヒップホップとクロスオーバーなイベントで知らないジャンルを垣間見れてよかった。
ライブハウスにつくとすでにもうかなりの客が入っていてかなりキュウキュウだった。WALLは入り口に「〇〇(多分バンドなのだろう)の☓☓とヴィジュアル系出入り禁止」みたいな張り紙がしてあり、私はどうみてもヴィジュアル系ではないがなんというかハードコアな雰囲気がしてちょっと怖いと思う。(実際怖めの人が多かったし、私のようなオタクっぽい人がいなくてさらに怖いというのがあります。)
ステージの前が不気味に人がいなくて不穏であり、これを見るとハードコアのライブに来てしまった…という感じがする。
Super Structure
一発目はSuper Structure。私は何回か見ているけど見るたびに好きになる、このバンドに関しては。この日もかなりとんがった音を出していた。後のFriendship、Fight It Outはとにかくパワーと音量がでかい。Super Structureも音はでかいのだが曲の方はもっとカオティックだ。別にプログレッシヴだ、カオティック・ハードコアだというのではないが、もっと混沌としている。変な言い方だがどの楽器もフルスピードで鳴らしまくった音が重なると奇跡的に曲に聞こえる、みたいな雰囲気がある。この日共演するバンドと比べると音はもっとざらつき、音の数は多い。パワーバイオレンスといっても流行とは一線を画す内容でもっとラフだ。例えば地獄のようなスラッジパートがあるわけでもない。甲高い、と評しても良いボーカルが激しく細かく忙しないバンドアンサンブルにさらにカオス感を注入している。バンド名は(あとから知ったのだけど)USのニュースクール・ハードコアバンドFall Silentの2ndアルバムからとっていることもあり、ルーツとなっているのがそういった音楽なので、パワーバイオレンスたろうとするパワーバイオレンスバンドとは明確に違う音に仕上がっているのではなかろうか。まさしく鉄砲玉、それも恐ろしく命中率が悪く乱射しまくるような凶悪なバンドで、ラストにやった「Despair」(だと思う。唯一気軽に聴けるこのバンドの音源でもある。)には中盤にギターの高音を響かせる地獄のようなモッシュパートがある。非常に格好いいのだ。私がお金持ちだったら最高の環境で音源を録音してもらうのにな、といつも思う。(音源出してほしいです。)
Friendship
続いてはFriendship。今年アルバムが出てからはみたっけな?結構見る回数が多いのは色んなイベントに招かれているからだろう。全くフレンドリーではないが、普通の意味とは違うキャッチーさがあって、それがわかりやすく”ハードコア”なので少しジャンルをまたぐようなイベントに引っ張りだこになるのかな、と思う。
Super Structureの直後ということもあって両者の違いが明確になる。こちらも非常にやかましいが音の数はぐっと減る。数というか密度だろうか。とにかくキチンと音を抜くことで重苦しいのに閉塞感から適度に脱しており、過密のコントロールが上手いのか、その結果ある意味ハードコアの枠組みだけ残したみたいな音楽になるのだが、それが非常に頑強で非常に暴れられる。初めてFriendshipを見た人でも絶対すぐに「のれ」ると思う。相変わらず一切MCはなく、ボーカルはほぼフロアに降りて歌う。毎回すごいと思うのは一切一体感は演出しない。シンガロングパートはもちろんないし、フロアに降りるボーカルも急に回りの客に向けてタックルを仕掛けてくる。みんなで楽しくモッシュ!って感じでもない。曲もそうだし、こういった姿勢の作り方というのも非常によく考えられている。「策士だね〜」というのではなくて、茨の道を我が物顔で進むな〜という感心の気持ちのほうが勝ってきた。若手、というのだけでなく、例えば私のような門外漢にとってのハードコアのゲートウェイになっていてそういった意味でもすごいバンドだ。
CENJU from DMC
続いては日本は東京のラッパー。実はヒップホップのライブを見るのは初めてかな?結構楽しみにしていた。CENJUはがっしりとした高身長と体躯に恵まれた大男でかなり迫力がある。低音のラップパートを同期させてそこにラップを被せていくように進む。これは合唱で言う下のパートってことだろうか。ヒップホップのライブは(他のラッパーは違うかもだけど)こうなんだな!と面白かった。強面なのは外見だけでなく、かなりハードな内容を噛み砕いた言葉でリリックにしたためるアーティストらしく、(ストリートのなんたるかを知らない私が言うのもちょっとおかしいのだけど)”ストリート感”のあるラップを披露する。つまりリアルでアンダーグラウンドな世界観である。悪いのだ。音の洪水を通り越し、もはや壁(WALLというライブハウスの名前は非常に格好いいと思う。)になっているハードコアとは全然ちがう音の数だ。とにかくシンプルに限界まで削ぎ落としたトラックが鋭い。そして鋭いだけでなく、煙たい、ダルいを表現する。これが良い。よくヒップホップのラップでは「スキル」という言葉が浮き彫りになるが、一人でステージに立つ(そうでない場合も多いが基本的にラップをするときは一人だ。)ラッパーは露骨にその出来にごまかしが効かない。タフな役回りだ。(それ故かっこいい。)CENJUは韻を踏みつつ結構フリーに煽ってくるタイプで客席を大いに沸かせていた。見た目に反して声は少し甘い感じがあるのが個人的には良かった。
Fight It Out
危ないことになるから後ろに下がったんだけど結局ダメでした…。
続いては横浜シティのパワーバイオレンスバンドFight it Out。この日の主役の片方でもある。バイオレンスを音にしたらこうなりました、というバンドで今年発売された3rdアルバムは私のようなオタクも聞いていると何か自分が強くなったように錯覚するようなブルータルなアルバムだった。ライブはモッシュ天国(普通の基準で考えればなぜ金を払ってそんなことを?と思わずにはいられない地獄)になるのは何回か見てことがあるので私は後ろに下がった 。WALLは後ろに長いライブハウスなのだが結果から言うとこの長さを活かした縦長のピットができて、だいたいほぼほぼ安全地帯がなし。全員が当事者に。
音の作り方はFriendshipと似ているモダンで金属的で良い感じに音の数を落としたものだが、こちらはもうモッシュに特化していると言っても良いかもしれない音で、Friendshipのような黒いヴェールのようなものもない粗野な音像。激速と激遅(げきおそ)を行ったり来たりするくせに神経症的な痙攣という病的な感じではなく、暴力性の発露のような運動性が特徴。そういった意味では健康的なのだろうか。あっという間にフロアにヘイトが感染して凶悪なモッシュパートが出来上がる。ボーカルの人はほぼフロアにいたのはFriendshipと同様だが、こちらはシンプルながらシンガロングできるパートがあったりしてモッシュピットに一定の法則、というよりは一つの指向性があったように思えた。腕を振り回す人、足を振り回す人、タックルをかます人、マイクを取りに(一緒に歌おうとしてね)行く人、サーフする人(カオスなのであまり長く上に居続けられない)、もみくちゃで後ろの方にもピットの動きが人を通して伝わってくる。ライブと音源の違い、というの一つのテーマに対する回答を明確にFight It Outが示し、そしてライブ(ともするとライブのみ)がリアルである、というのもうべなるかな、という状況でした。
ILL-TEE
つづいてはILL-TEE。DJの他にもう一人ラッパー、多分MASS-HOLEという人かな?がステージに立つ三人体制。トラックの内外とわず自由にやるCENJUに比べるとこの二人のラッパーはかなりかっちりタイトにトラックにリリックをはめ込んでくる。小節頭に言葉の喋りだしが噛み合ってこれはこれで非常に格好いい。やはりリアルな感じのするリリックだったと思うけど(固くて低い声質もあってCENJUに比べるとやや聞き取りにくい場面もあった。)、もう少し言葉遊びと陰陽の陽にあたるようなリリックもあってヒップホップの楽しさ、というのがわかりやすくそして最大限に発表されるようなステージングだった。ある意味淡々と韻を踏んでいくスタイルではじめは聞き惚れるような感じなのだけど、トラックとのかみ合わせが非常に良くてどんどん気持ちよくなってくる。フックのようなものもあってわかりやすい。ハードコアという明確に違うフィールドで徐々にヒップホップの楽しさ、というのがじわじわ浸透してくるようなライブでやはりもう最終的にはかなり前の方は盛り上がっていた。トラックがシンプルでビートが強いので実は乗りやすい、というのはあると思う。真面目と言っていいほどしっかりしていて格好良かった。
Saigan Terror
続いては東京高円寺のハードコアバンドで結成は1997年(素晴らしいインタビューより)。クロスオーバー、つまりこの場合はハードコアに刻みまくるスラッシュ・メタルをかけ合わせた音楽で私は何回かライブを見たかな?格好いいんだけど言語化するのが難しいな(音源もいまでは廃盤状態なので。)と思っていた。本日はスプリット発売の主役で堂々のトリ。
改めてライブを見るとこんなに重かったっけ?となったブラストビートが冴えまくり、ブラストビートに乗って突っ走るさまはもはやTerrorizerでは!?と思うくらい凄まじかった。よくよく聴いてみるとなるほど確かにグラインドコアというには音が良い感じに抜けていて、より疾走感が強調されているけどそれでも軽薄ということはまったくない。ブラストビートにすべてを掛ける、という音楽性でもなく、シンプルな2ビートが土台を作りそこに凝ってはいるが決してスピード感を減じさせない”刻み”のスラッシュリフが乗る。この日ドラムとともにすごいなと思ったのはベースで、おそらくエフェクターを噛ませて幾つかの音をコントロールしているのだが、かなり硬質で刻みのリフと相対するようなガーンとアタックしたあとミュートしない弾き方が、硬い地面に金属が跳ね返るような強烈さで非常に格好良かった。この日前の3つのバンドは共通点があってそれはとにかく突っ走るときは突っ走る、ということだったが、Saigan Terrorは速度はあってもミュートを用いたリフにはつんのめるような独特の粘りのあるコシが生まれているところが明確に異なる。つまり何が言いたいかというと他のバンドにはない「グルーヴィ」さが生まれていた。これはとにかくピットに反映されていて、Fight It Outの殺伐としてたピットと比べると同じことをやってい人はいるのだけど、もう少し多様性があり、ステップを踏む人やそれこそ女性の人もいた。そして沢山の人が笑顔だったのが一番印象的だった。危なくないわけではないけど、それを圧倒的に上回る楽しさ。ギタリストの方のキャラクターやMCもそんな雰囲気を作り出していくことに大いに寄与していると思う。 20年の貫禄がバチバチ発揮されていた唯一無二のサウンドだった。
もちろんスプリット音源(とZine)を購入してほうほうの体で帰宅。終始激しかったけど楽しかった。ライブを見に行く醍醐味に知らないバンドを知れる、というのがあると思うがそういった意味ではハードコアとヒップホップとクロスオーバーなイベントで知らないジャンルを垣間見れてよかった。
2017年11月26日日曜日
ダン・シモンズ/エンディミオンの覚醒
アメリカの作家によるSF小説。
「ハイペリオン」サーガの最終章。どんどんボリュームも増してきて、今作では上下分冊の上それぞれが700ページある。長かったアイネイアーとロール・エンディミオンの旅路もついに終りを迎える。
宇宙と人類を統べるカトリックとその軍隊パクスの猛追から辛くも逃れ、マゼラン星雲に位置する失われたはずのオールドアースに到達した人類の救世主アイネイアーとロール、アンドロイドのべティック。謎の勢力の実験により蘇った建築家フランク・ロイド・ライトの弟子として平和な4年間が過ぎた。しかしアイネイアーは安寧の生活の終わりを告げ、エンディミオンはかつてとある惑星に隠した宇宙船を確保する命令を受ける。嫌々ながらカヌーに乗り込み転移に備えるエンディミオン。動き出したアイネイアー一行に対して再び、いよいよの追撃を掛けるパクス。そしてその背後にはもう隠しようもなく”コア”の存在が見え隠れする。人類の命運を分ける戦いがついに始まり、そして決着する。
時間の墓標に住むシュライクが活性化したため原因を探りに行く、という物語だった4部作の冒頭を飾る「ハイペリオン」から4作、物語は進み、270年の時間が流れ、人類の版図とその生活は大きく変わり、そして登場人物たちを(一部は残っているけど)一新し、そして彼らも成長させた物語もついにここで終焉。4冊を2つに分けられるが、前半で謎のままにされた幾つかの謎もついにすべてが明らかになる。長きに渡って人類を陰ながら支配していた人類自身が作り出したAI群テクノコアと全面対決をし、いよいよ人類がインターネットを発明してから失った(テクノコアはちょうとネットともに誕生したという設定)自由を再び手に入れられるか、というところと、さらには人類という種が宇宙の中でもう一段進化の階段を登るか、というSF的な命題が、一人の救世主となる助成によって復讐的に、そして革命的に実行されるという物語的なカタルシスを持った壮大なエンターテインメントSF小説だったなと、振り返って読み終えるとわかる。おおよそ目新しい設定などはないものの、既存の設定、ガジェットのみでよくもここまでSF小説の醍醐味をほぼほぼ網羅したような集大成的な大作が書け得たものだ。相変わらず道の存在しない世界への旅行記としての魅力は兼ね備えていて、特に三分構成の今作の二部の物語の中心となる、アジア系の播種船が長い年月で打ち立てた惑星天山のチベット的な世界観の描写には日本人としては心打たれるものがあるだろう。未来なのになぜかノスタルジーを感じさせる(しかも一回も言ったことない外国なのにね)描写はさすがの手腕で、1400ページ普通の小説なら寄り道として切り捨ててしかるべきところに丁寧にページをさき、そしてその緻密な描写こそがこの本の楽しさの大きな柱になっている。物語の構成も純朴なロールと言う男を狂言回しにすえることで、きになる大きな謎が最後まで明らかにされないという作りになっており、流石に物語が加速する後半はジリジリしながらページをめくる手がスピードアップした。やはりアメリカの作家からなのかかも知れないが、(といっても明らかに意図的に直接に書いていることは明白だ。)基本的には堕落したキリスト教的な世界観を、ひとりの救世主的な、つまりキリスト教的なリーダーが(さらに彼はか弱く若い女性である)不屈の精神でひっくり返していく、というストーリー。
最後まで面白く読めたのだが、のめり込めたゆえに不満があるところもあって、大きく3つかな。一つは物語の構成上仕方ないけどロールが最後までアイネイアーの使いっぱしりでしかないこと。所々で男気を見せるのだけど、あくまで字も一番普通の人間が自力で進歩してほしかったところ。一歩を踏み出すのがアイネイアーのドグマなのだが、どこかで自分なりの一歩を見せれたら良かったかな。もう一つはこれは「ハイペリオン」の時からもそうだったが、体制側がのんきすぎる。今回コアが主だったカトリックの頭たちに演説をぶつのだけど、証拠が一個もないのにも頭から信じてしまう人類側が全然だめでしょ。仮にも人類を統治しながら影で裏切ってる悪の首魁なんだからもっと賢くならないと。コアを出し抜いてほしかった。(これもアイネイアーとロールの関係と立場は違うけど構図は同じだね。)まあ聖十字架で弄くられているから、って言い訳は通りそうだが。最後はテクノコアというのが最後まで寄生体というのがいまいち納得できない。テクノコアに限らず、極度に進化したAIなら肉体に縛られないのだから、さっさとロボットでも作って人類から離れていくようなきがするのだが。SFだと必ず人類に反旗を翻すのがAIの役目なのだが、実際には肉体という檻にとらわれない彼らは思考が全く人類のそれとは異なるのでは。そうなったら人類に対する拘泥や恐れなんてあるかな??と思ってしまう。(AIがやけに人間くさすぎる。)まあこれは私のSF全般に対する思いなのであれなんだけど。
たしかに面白いSFを読みたいという人はこのシリーズを読むのが手っ取り早いかもしれない。ハードなSFだとハードルが高い、という人にはおすすめでそういう意味では入門編に良いかもしれない。ただしとにかく最後まで読むと長い、というのとこれ読むともうSFはこれで良いかになるかも(自分はならないが)ってなるかもしれないな…。
「ハイペリオン」サーガの最終章。どんどんボリュームも増してきて、今作では上下分冊の上それぞれが700ページある。長かったアイネイアーとロール・エンディミオンの旅路もついに終りを迎える。
宇宙と人類を統べるカトリックとその軍隊パクスの猛追から辛くも逃れ、マゼラン星雲に位置する失われたはずのオールドアースに到達した人類の救世主アイネイアーとロール、アンドロイドのべティック。謎の勢力の実験により蘇った建築家フランク・ロイド・ライトの弟子として平和な4年間が過ぎた。しかしアイネイアーは安寧の生活の終わりを告げ、エンディミオンはかつてとある惑星に隠した宇宙船を確保する命令を受ける。嫌々ながらカヌーに乗り込み転移に備えるエンディミオン。動き出したアイネイアー一行に対して再び、いよいよの追撃を掛けるパクス。そしてその背後にはもう隠しようもなく”コア”の存在が見え隠れする。人類の命運を分ける戦いがついに始まり、そして決着する。
時間の墓標に住むシュライクが活性化したため原因を探りに行く、という物語だった4部作の冒頭を飾る「ハイペリオン」から4作、物語は進み、270年の時間が流れ、人類の版図とその生活は大きく変わり、そして登場人物たちを(一部は残っているけど)一新し、そして彼らも成長させた物語もついにここで終焉。4冊を2つに分けられるが、前半で謎のままにされた幾つかの謎もついにすべてが明らかになる。長きに渡って人類を陰ながら支配していた人類自身が作り出したAI群テクノコアと全面対決をし、いよいよ人類がインターネットを発明してから失った(テクノコアはちょうとネットともに誕生したという設定)自由を再び手に入れられるか、というところと、さらには人類という種が宇宙の中でもう一段進化の階段を登るか、というSF的な命題が、一人の救世主となる助成によって復讐的に、そして革命的に実行されるという物語的なカタルシスを持った壮大なエンターテインメントSF小説だったなと、振り返って読み終えるとわかる。おおよそ目新しい設定などはないものの、既存の設定、ガジェットのみでよくもここまでSF小説の醍醐味をほぼほぼ網羅したような集大成的な大作が書け得たものだ。相変わらず道の存在しない世界への旅行記としての魅力は兼ね備えていて、特に三分構成の今作の二部の物語の中心となる、アジア系の播種船が長い年月で打ち立てた惑星天山のチベット的な世界観の描写には日本人としては心打たれるものがあるだろう。未来なのになぜかノスタルジーを感じさせる(しかも一回も言ったことない外国なのにね)描写はさすがの手腕で、1400ページ普通の小説なら寄り道として切り捨ててしかるべきところに丁寧にページをさき、そしてその緻密な描写こそがこの本の楽しさの大きな柱になっている。物語の構成も純朴なロールと言う男を狂言回しにすえることで、きになる大きな謎が最後まで明らかにされないという作りになっており、流石に物語が加速する後半はジリジリしながらページをめくる手がスピードアップした。やはりアメリカの作家からなのかかも知れないが、(といっても明らかに意図的に直接に書いていることは明白だ。)基本的には堕落したキリスト教的な世界観を、ひとりの救世主的な、つまりキリスト教的なリーダーが(さらに彼はか弱く若い女性である)不屈の精神でひっくり返していく、というストーリー。
最後まで面白く読めたのだが、のめり込めたゆえに不満があるところもあって、大きく3つかな。一つは物語の構成上仕方ないけどロールが最後までアイネイアーの使いっぱしりでしかないこと。所々で男気を見せるのだけど、あくまで字も一番普通の人間が自力で進歩してほしかったところ。一歩を踏み出すのがアイネイアーのドグマなのだが、どこかで自分なりの一歩を見せれたら良かったかな。もう一つはこれは「ハイペリオン」の時からもそうだったが、体制側がのんきすぎる。今回コアが主だったカトリックの頭たちに演説をぶつのだけど、証拠が一個もないのにも頭から信じてしまう人類側が全然だめでしょ。仮にも人類を統治しながら影で裏切ってる悪の首魁なんだからもっと賢くならないと。コアを出し抜いてほしかった。(これもアイネイアーとロールの関係と立場は違うけど構図は同じだね。)まあ聖十字架で弄くられているから、って言い訳は通りそうだが。最後はテクノコアというのが最後まで寄生体というのがいまいち納得できない。テクノコアに限らず、極度に進化したAIなら肉体に縛られないのだから、さっさとロボットでも作って人類から離れていくようなきがするのだが。SFだと必ず人類に反旗を翻すのがAIの役目なのだが、実際には肉体という檻にとらわれない彼らは思考が全く人類のそれとは異なるのでは。そうなったら人類に対する拘泥や恐れなんてあるかな??と思ってしまう。(AIがやけに人間くさすぎる。)まあこれは私のSF全般に対する思いなのであれなんだけど。
たしかに面白いSFを読みたいという人はこのシリーズを読むのが手っ取り早いかもしれない。ハードなSFだとハードルが高い、という人にはおすすめでそういう意味では入門編に良いかもしれない。ただしとにかく最後まで読むと長い、というのとこれ読むともうSFはこれで良いかになるかも(自分はならないが)ってなるかもしれないな…。
Wormrot/Voices
シンガポールのグラインドコアバンドの3rdアルバム。
2016年にEarache Recordsからリリースされた。
先日来日し、そのパフォーマンスで観客を魅了しまくったらしい。らしいというのはちょうど私はTDEPの公演と日程がかぶり身も心もマスコアに捧げたため彼らのステージは見ていないからだ。(平日公演もあったんだけど行けなかった。)ただ本当にちょっとやそっとの高評判ではなかったのでせめて音源だけでも、というわけで購入した次第。三人組のバンドで2007年に結成、2012年に活動を休止し、メンバーを一部入れ替えて再始動し作成したのがこのアルバム。
グラインドコアというのはデスメタルとハードコアがクロスオーバーしたジャンルで、ブラストビートが多用される、という説明は実は肝心な音楽性に対する正確な言及はない。ブラストビートを入れればなんでもグラインドコアになるかというとそれも違うわけで、そういった曖昧性もあってか”グラインド”というのは幅広く激しい音楽で使われている気がする。そんな中でピュアなグラインドコアバンド、というのは実はそういないのでは。というのもピュアであろうとすれば音楽的な選択肢の幅が広がり、強烈な個性が出しにくくなるからだ。例えば今はもうスマートフォンでも曲を作れるが、それでドラムのパートを全部叩かせると「ダダダダダダ…」となっておお!グラインドだ!となるが楽しいのは最初だけですぐににつまらなくなってしまう。ただの垂れ流しに飽きちゃうのだ。グラインドコアバンドはいかにたくさんグラインドするかというよりは、どうやってグラインドするか、どこでグラインドするか、むしろどうやってグラインドしないか、を突き詰めるようになるのではないか。前置きが長くなったが、このWormrotというバンドはそこを突き詰め、グラインドコアの表現の限界に果敢に挑もうとするバンドのようだ。
ベースレスのトリオ編成でもちろん基本的にはどの曲も異常に速く、そして短い。紛れもないグラインドコアだがその表現力が半端ない。まずはギターの音を意図的に軽くしている。重さは迫力を増すが、圧倒的に選択肢を阻めてしまう諸刃の剣ということだろうか。代わりに軽快なフットワークと流れるようななめらかな表現力がギターに付与されている。アイディアの塊のようなリフワークで、ブラストビートの上によく映える王道のスラッシュなリフはもちろん、溜めのある中速を彩るミュートを多用するリフ、ハードコア的なゴリゴリしたリフ、それからブラックメタル顔負けのトレモロリフにはやはり圧倒的に欠けているメロディの要素を補って余りある表情の豊かさ。普通ならリフとアイディアだけで4分とかそれ以上、もしかしたら複数の曲を賄えるくらいの量を1曲にそれも多くは1分前後の曲に圧縮している。なんという贅沢。なんという酔狂。だがそれが良い。代わりにともすると突っ走るだけのどんぐりの背比べに陥るグラインドコアという非常に尖ったジャンルに全く新しいバリエーションを生み出すことに成功している。
ギターに負けじと多彩な声で叫びまくるボーカル、そしてブラストを叩くだけでないドラムも三人の真剣勝負のような緊張感を煽ってくる。
”縛り”というのはあえて選択肢を絞ることだ。自らに課すルールと言っても良い。一見選択肢の削除は自殺行為に見えるが、実はルールを持ち出すことは表現を研ぎ澄ませ、出来上がってくるものを引き締めて面白くする。(例えばゲームのバイオハザードをナイフだけでクリアする、なんて緊張感のある縛りプレイですよね。逆に無限ロケットランチャーははじめはテンション上がるけど意外に面白くない。)厳格に自らを縛っているのに、こんなにも豊かな色が出せるとは非常に驚きだ。少なくとも音楽のジャンルでは何かが完成するなんてことはないんだな〜と思わせる。
ともするとどん詰まりになるようなグラインドコアというジャンルの壁をぶち壊すような快作。ライブの評判は本当すごかったからぜひまた見る機会があればな〜と思わずにはいられない。
2016年にEarache Recordsからリリースされた。
先日来日し、そのパフォーマンスで観客を魅了しまくったらしい。らしいというのはちょうど私はTDEPの公演と日程がかぶり身も心もマスコアに捧げたため彼らのステージは見ていないからだ。(平日公演もあったんだけど行けなかった。)ただ本当にちょっとやそっとの高評判ではなかったのでせめて音源だけでも、というわけで購入した次第。三人組のバンドで2007年に結成、2012年に活動を休止し、メンバーを一部入れ替えて再始動し作成したのがこのアルバム。
グラインドコアというのはデスメタルとハードコアがクロスオーバーしたジャンルで、ブラストビートが多用される、という説明は実は肝心な音楽性に対する正確な言及はない。ブラストビートを入れればなんでもグラインドコアになるかというとそれも違うわけで、そういった曖昧性もあってか”グラインド”というのは幅広く激しい音楽で使われている気がする。そんな中でピュアなグラインドコアバンド、というのは実はそういないのでは。というのもピュアであろうとすれば音楽的な選択肢の幅が広がり、強烈な個性が出しにくくなるからだ。例えば今はもうスマートフォンでも曲を作れるが、それでドラムのパートを全部叩かせると「ダダダダダダ…」となっておお!グラインドだ!となるが楽しいのは最初だけですぐににつまらなくなってしまう。ただの垂れ流しに飽きちゃうのだ。グラインドコアバンドはいかにたくさんグラインドするかというよりは、どうやってグラインドするか、どこでグラインドするか、むしろどうやってグラインドしないか、を突き詰めるようになるのではないか。前置きが長くなったが、このWormrotというバンドはそこを突き詰め、グラインドコアの表現の限界に果敢に挑もうとするバンドのようだ。
ベースレスのトリオ編成でもちろん基本的にはどの曲も異常に速く、そして短い。紛れもないグラインドコアだがその表現力が半端ない。まずはギターの音を意図的に軽くしている。重さは迫力を増すが、圧倒的に選択肢を阻めてしまう諸刃の剣ということだろうか。代わりに軽快なフットワークと流れるようななめらかな表現力がギターに付与されている。アイディアの塊のようなリフワークで、ブラストビートの上によく映える王道のスラッシュなリフはもちろん、溜めのある中速を彩るミュートを多用するリフ、ハードコア的なゴリゴリしたリフ、それからブラックメタル顔負けのトレモロリフにはやはり圧倒的に欠けているメロディの要素を補って余りある表情の豊かさ。普通ならリフとアイディアだけで4分とかそれ以上、もしかしたら複数の曲を賄えるくらいの量を1曲にそれも多くは1分前後の曲に圧縮している。なんという贅沢。なんという酔狂。だがそれが良い。代わりにともすると突っ走るだけのどんぐりの背比べに陥るグラインドコアという非常に尖ったジャンルに全く新しいバリエーションを生み出すことに成功している。
ギターに負けじと多彩な声で叫びまくるボーカル、そしてブラストを叩くだけでないドラムも三人の真剣勝負のような緊張感を煽ってくる。
”縛り”というのはあえて選択肢を絞ることだ。自らに課すルールと言っても良い。一見選択肢の削除は自殺行為に見えるが、実はルールを持ち出すことは表現を研ぎ澄ませ、出来上がってくるものを引き締めて面白くする。(例えばゲームのバイオハザードをナイフだけでクリアする、なんて緊張感のある縛りプレイですよね。逆に無限ロケットランチャーははじめはテンション上がるけど意外に面白くない。)厳格に自らを縛っているのに、こんなにも豊かな色が出せるとは非常に驚きだ。少なくとも音楽のジャンルでは何かが完成するなんてことはないんだな〜と思わせる。
ともするとどん詰まりになるようなグラインドコアというジャンルの壁をぶち壊すような快作。ライブの評判は本当すごかったからぜひまた見る機会があればな〜と思わずにはいられない。
Wolves in the Throne Room/Thrice Woven
アメリカ合衆国ワシントン州オリンピアのブラックメタルバンドの6枚目のアルバム。
2017年にArtemisia Recordsからリリースされた。
1stアルバム「Diadem of 12 Stars」を2006年にリリースするやカスカディアン・ブラックメタルというジャンルを圧倒今に打ち立てたブラックメタルバンド。カスカディアンといえば複雑な大作指向でまごうことなきアンダーグランドなジャンルだったが、アトモスフェリックな音作りはその後のブラックメタルとシューゲイザーの融合に影響を与えたのではと密かに思っている。2014年に発表された前作「Celestite」では前編ほぼシンセサイザーの音で構成された内容でファンの度肝を抜いた(おおよそネガティブな方に)バンドの3年ぶりの新作。もしやまた…というファンの不安を裏切り結論から言うと元の完全なブラックメタルなバンドサウンドに回帰している。中心となるのはNathanとAronのWeaver兄弟で、そこにKody Keyworthというメンバーが新しくギターと歌で参加している三人体制。プロデューサーにRundall Dunnを迎え自前のスタジオ(文字通り自分たちで建てたらしい。)で録音された。今でも多分そうだがWeaver兄弟はオーガニックな思想を持ち、そこに根ざすスタンスで活動している。農場で暮らし、電気を使うことに矛盾を感じつつ、ブラックメタルをやっている。
今作「Thrice Woven」は直訳すると「三回織」になる。おそらく織物の形式の一つではと思うが。バンド三人に加えてスウェーデンのシンガーAnna von Hausswolff、それから暗黒メタル界の巨人NeurosisのSteve von Tilがゲストとして参加している。
全5曲で42分。インタールード的な4曲目を除くとだいたい1曲あたり10分くらいだろうか。過去にはもっと長い曲があったが、「Celestial Lineage」から割りと(それまでに比べると)コンパクトに曲を纏める、という動きがあるように思う。そういった意味でも前前作を踏襲する流れなのだが、一通り何回か聞いた後に思うのはやはり問題作となった前作「Celestite」の影響はまだあるなと。確か前作の感想を書いた際に表現の際にブラックメタルという”やり方”がじゃまになったため、というかそのやり方だと表現しきれないため、ああいった別のアプローチを取ったのでは、と書いた。今作でもシンセサイザーは使われているが私が言いたいのはただ今作もシンセサイザーを使っているので、とか微妙にそういうことではなくて。まず今作を聞いて思ったのは曲に今までにない広がりがあることだ。大作指向だし大胆に女性ボーカルをゲストに招いたりしているが、実はこのバンド表現の幅は結構かっちりしている。どちらかと言うと多彩なのは展開であって、あくまでも愚直なまでのブラックメタル絵巻を展開してきたように思う。同じカスカディアンというジャンルに属するミネソタ州のPanopticonが「Kentucky」で大胆にバンジョーを取り入れたときは衝撃だったが(私はこのアルバムが非常に好きだ。)、実はWolves in the Throne Roomはそこまで柔軟にジャンルをまたいでいなかった。今作「Thrice Woven」ではさすがにバンジョーやその他の楽器を取り入れることはないものの、今までの彼らからするとかなり新しい要素を取り入れていると思う。女性ボーカルや複雑な構成という強靭な縦糸に、フォークの要素、シンセサイザーの浮遊感、アンビエントパートなどの横糸を噛まして、強靭かつ今までにない色彩豊かな織物を描き出した。それが今作だ。
ある意味相当アヴァンギャルドだった前作がマンネリからの脱却や、第一人者としての重圧からの逃げを打った失敗作とするのではなく、自分たちの本質がどこにあり、どこまで行けるか、ということを確かめる作品だったとすると、全くバンドサウンドを用いないという「Celestite」という作品を経て、改めてブラックメタルの形に回帰し、そしてその幅を大胆不敵に広げてきたのが今作「Thrice Woven」ではと思う。
複雑なバンドだが、私はやはりメロディの残滓の上を紙を引き裂くようなイヴィルなボーカルが疾駆する、ストレートなパートがWolves in the Throne Roomの醍醐味だと思うので(そういった意味ではEP「Malevolent Grain」はすごーく好きな音源。)、今作でもその鋭さが遺憾なく発揮されているのが嬉しい。やはり芯はぶれていない。普通のブラックメタルなら「冬は死につつある、太陽が戻ってきている」と春を称える歌を歌わない。これはやはり野菜を育て豊かな春の訪れの本当の豊穣さ、ありがたみを知っている人でなくてはつくりだせないだろう。崇高な何かに対する畏怖と畏敬の念が詰まっているように思う。そういった意味ではやはり、温かい、血の通ったブラックメタル、という稀有な音楽だ。
ひたすら風格を見せつける最新作。前作に否定的な感想を持った人にこそ聞いてほしいと思う。非常に格好良い。おすすめ。
2017年にArtemisia Recordsからリリースされた。
1stアルバム「Diadem of 12 Stars」を2006年にリリースするやカスカディアン・ブラックメタルというジャンルを圧倒今に打ち立てたブラックメタルバンド。カスカディアンといえば複雑な大作指向でまごうことなきアンダーグランドなジャンルだったが、アトモスフェリックな音作りはその後のブラックメタルとシューゲイザーの融合に影響を与えたのではと密かに思っている。2014年に発表された前作「Celestite」では前編ほぼシンセサイザーの音で構成された内容でファンの度肝を抜いた(おおよそネガティブな方に)バンドの3年ぶりの新作。もしやまた…というファンの不安を裏切り結論から言うと元の完全なブラックメタルなバンドサウンドに回帰している。中心となるのはNathanとAronのWeaver兄弟で、そこにKody Keyworthというメンバーが新しくギターと歌で参加している三人体制。プロデューサーにRundall Dunnを迎え自前のスタジオ(文字通り自分たちで建てたらしい。)で録音された。今でも多分そうだがWeaver兄弟はオーガニックな思想を持ち、そこに根ざすスタンスで活動している。農場で暮らし、電気を使うことに矛盾を感じつつ、ブラックメタルをやっている。
今作「Thrice Woven」は直訳すると「三回織」になる。おそらく織物の形式の一つではと思うが。バンド三人に加えてスウェーデンのシンガーAnna von Hausswolff、それから暗黒メタル界の巨人NeurosisのSteve von Tilがゲストとして参加している。
全5曲で42分。インタールード的な4曲目を除くとだいたい1曲あたり10分くらいだろうか。過去にはもっと長い曲があったが、「Celestial Lineage」から割りと(それまでに比べると)コンパクトに曲を纏める、という動きがあるように思う。そういった意味でも前前作を踏襲する流れなのだが、一通り何回か聞いた後に思うのはやはり問題作となった前作「Celestite」の影響はまだあるなと。確か前作の感想を書いた際に表現の際にブラックメタルという”やり方”がじゃまになったため、というかそのやり方だと表現しきれないため、ああいった別のアプローチを取ったのでは、と書いた。今作でもシンセサイザーは使われているが私が言いたいのはただ今作もシンセサイザーを使っているので、とか微妙にそういうことではなくて。まず今作を聞いて思ったのは曲に今までにない広がりがあることだ。大作指向だし大胆に女性ボーカルをゲストに招いたりしているが、実はこのバンド表現の幅は結構かっちりしている。どちらかと言うと多彩なのは展開であって、あくまでも愚直なまでのブラックメタル絵巻を展開してきたように思う。同じカスカディアンというジャンルに属するミネソタ州のPanopticonが「Kentucky」で大胆にバンジョーを取り入れたときは衝撃だったが(私はこのアルバムが非常に好きだ。)、実はWolves in the Throne Roomはそこまで柔軟にジャンルをまたいでいなかった。今作「Thrice Woven」ではさすがにバンジョーやその他の楽器を取り入れることはないものの、今までの彼らからするとかなり新しい要素を取り入れていると思う。女性ボーカルや複雑な構成という強靭な縦糸に、フォークの要素、シンセサイザーの浮遊感、アンビエントパートなどの横糸を噛まして、強靭かつ今までにない色彩豊かな織物を描き出した。それが今作だ。
ある意味相当アヴァンギャルドだった前作がマンネリからの脱却や、第一人者としての重圧からの逃げを打った失敗作とするのではなく、自分たちの本質がどこにあり、どこまで行けるか、ということを確かめる作品だったとすると、全くバンドサウンドを用いないという「Celestite」という作品を経て、改めてブラックメタルの形に回帰し、そしてその幅を大胆不敵に広げてきたのが今作「Thrice Woven」ではと思う。
複雑なバンドだが、私はやはりメロディの残滓の上を紙を引き裂くようなイヴィルなボーカルが疾駆する、ストレートなパートがWolves in the Throne Roomの醍醐味だと思うので(そういった意味ではEP「Malevolent Grain」はすごーく好きな音源。)、今作でもその鋭さが遺憾なく発揮されているのが嬉しい。やはり芯はぶれていない。普通のブラックメタルなら「冬は死につつある、太陽が戻ってきている」と春を称える歌を歌わない。これはやはり野菜を育て豊かな春の訪れの本当の豊穣さ、ありがたみを知っている人でなくてはつくりだせないだろう。崇高な何かに対する畏怖と畏敬の念が詰まっているように思う。そういった意味ではやはり、温かい、血の通ったブラックメタル、という稀有な音楽だ。
ひたすら風格を見せつける最新作。前作に否定的な感想を持った人にこそ聞いてほしいと思う。非常に格好良い。おすすめ。
2017年11月19日日曜日
Iron Monkey/9-13
イギリスはイングランド、ノッティンガムのスラッジコアバンドの3rdアルバム。
2017年にRelapse Recordsからリリースされた。
Iron Monkeyは1994年に結成されたバンド。Earacheから2枚のオリジナルアルバムと日本のChurch of Miseryとのスプリットなど幾つかの音源をリリースして後、1999年に解散。その後2002年にはボーカル担当のJohnny Morrowが心臓発作により逝去。Iron Monkeyといえばこのボーカル、ってこともあり再結成は絶望的に。ところが今年になって再結成して作った音源がこちら。ギターを弾いていたオリジナルメンバーJim Rushbyが真っ白い覆面マスクをかぶってボーカルを担当(ギターも弾く)。解散前に脱退したギタリストであるSteve Watsonがベースに転向。ドラムにScott Briggsを迎えた三人編成。Briggsはアーティスト写真でただならぬ存在感を漂わせているな…と思ったらハードコアパンクバンドChaos U.K.のドラマーとのこと。ボーカル不在という難しい状況をオリジナルメンバーを主体に再結成ということでこれはかなり期待が煽られるというもの。私はだいぶ遅れてオリジナルアルバム2枚セットの音源を買った周回遅れの後追いで、多分それが起因して今回の音源は結論から言うと非常に楽しめています。(オリジナルのボーカリストの魅力が…という意見もあるようで、やはり思い入れのある方はそういう感想を持ってしまうこともあるよなと。私も当時から聴いていたら多分そうだったと思う。)
イギリスと言うと紳士の国だが、ドゥームの国でもあるというのは半ば常識であって、そもそもからBlack Sabbathがイングランド出身ということもあり、現行ではやはりElectric Wizardや解散してしまったけどCathedral(とRise Above Records)などなど、激しいだけでなく怪しい、不穏である、剣呑な、退廃的な、そんな形容詞のよく似合うドゥームバンドをたくさん排出しております。私は激しさの探求からスラッジコアにたどり着いてやはりEyehategod(アメリカ、ニューオーリンズのバンド)を聴いてわかりやすく「やべー」となった口。Iron Monkeyを聴いたときはその一見するとの聞きやすさにびっくりしたものの、すぐにその軽快かつだるくて不穏な音世界にハマったものだ。
音質的には確実に2010年台の洗練されて迫力のある音にアップデートされている。ジリジリした感じは消えて非常にクリアだ。ただ中身的にはやはりIron Monkeyだ。バンドが存続していたらなるほどこういう音を出していただろうと言う感じ。スラッジコア/サイケ・ドゥームを自称することもあってただただ遅く陰惨なスラッジとは一線を画す音と曲作り。ヴィンテージ感のあるロックからの由来を感じさせる溜めのある、ひっぱるようなリフが特徴でゴリゴリ圧殺系とは明らかに異なるうねりのあるリズム感が魅力。決して音の数は多くないのに魔術のような空間を組み立てるリフ。もっと危険な音を出すバンドはあるが、このIron Monkeyの現実的なヤバさというのはジャンルは異なるがUNSANEなんかに似ているかも。ひょっとしたらストリート感と言っても良いかもしれない。不敵に微笑む危険な男、という感じで余裕がある感じが逆に不穏だ。酩酊しきって酔歩するように経過なロック/ドゥームの境界を超えて、明らかに行き過ぎた/やりすぎた感のあるスラッジの世界に足を突っ込むところが最高。前半のノリの良さがゲートウェイでヤバみが増してくる後半に気づくと案内されている、というかケツを足蹴にされて悪夢の陥穽に落ちたような非道な感じ。ラスト「Moreland St.Hammervortex」は大団円という感じ。
そしてやはりボーカルが一番気になるところ。なくなったJohnny Morrowという人はほんとう危険な感じのする声の持ち主で混沌とした悪徳を声で表現した、みたいな魅力の持ち主だった。このバンドの(当時の)看板はMorrowの独特なボーカリゼーションということは残されたメンバーも自覚するところであって、全く異なる系統のボーカルを載せるというよりはMorrowの歌唱法をなぞるようにJimがマイクを取る。前のボーカリストは上手い下手とかではない次元で人を魅了したが、その魅力は声質によるところもあって、異常なしゃがれ声だった。さすがにJimは体格と喉も別物なのでそのしゃがれの妙味というのはほぼない。ただぐしゃっと潰したようなこもった高音がよく出た耳障りな下品な、というところはかなり良い味を出している。ナチュラルに歌い上げる、もしくは叫ぶ(Morrowはかなりナチュラルに思える。)というよりはやはり演技力というのは明らかに酷だけど装飾性を感じるのは確か。ただし個人的にはこのくらいくどい方がいかがわしさがあって良いと思う。私的にはIron Monkeyの今のボーカルはJimで全く問題ない。思い入れのある方はまた違うのだろうが。
Iron Monkeyは名前だけしか知らないな〜という人はまずこの音源から買ってみたら時代のギャップはないと思う。Iron MonkeyといえばJohnny Morrowでしょ!という人も気持ちはわかるが、一旦通して聴いてほしい。やはり他に類を見ないバランスの”悪い”スラッジコアを鳴らすバンドだと思う。
どうでもいいけどとにかくあのお猿のロゴが格好良すぎてパーカーとLPのバンドルを買った上にT-シャツも購入した。もったいなくて着れないくらいかっこいい。
2017年にRelapse Recordsからリリースされた。
Iron Monkeyは1994年に結成されたバンド。Earacheから2枚のオリジナルアルバムと日本のChurch of Miseryとのスプリットなど幾つかの音源をリリースして後、1999年に解散。その後2002年にはボーカル担当のJohnny Morrowが心臓発作により逝去。Iron Monkeyといえばこのボーカル、ってこともあり再結成は絶望的に。ところが今年になって再結成して作った音源がこちら。ギターを弾いていたオリジナルメンバーJim Rushbyが真っ白い覆面マスクをかぶってボーカルを担当(ギターも弾く)。解散前に脱退したギタリストであるSteve Watsonがベースに転向。ドラムにScott Briggsを迎えた三人編成。Briggsはアーティスト写真でただならぬ存在感を漂わせているな…と思ったらハードコアパンクバンドChaos U.K.のドラマーとのこと。ボーカル不在という難しい状況をオリジナルメンバーを主体に再結成ということでこれはかなり期待が煽られるというもの。私はだいぶ遅れてオリジナルアルバム2枚セットの音源を買った周回遅れの後追いで、多分それが起因して今回の音源は結論から言うと非常に楽しめています。(オリジナルのボーカリストの魅力が…という意見もあるようで、やはり思い入れのある方はそういう感想を持ってしまうこともあるよなと。私も当時から聴いていたら多分そうだったと思う。)
イギリスと言うと紳士の国だが、ドゥームの国でもあるというのは半ば常識であって、そもそもからBlack Sabbathがイングランド出身ということもあり、現行ではやはりElectric Wizardや解散してしまったけどCathedral(とRise Above Records)などなど、激しいだけでなく怪しい、不穏である、剣呑な、退廃的な、そんな形容詞のよく似合うドゥームバンドをたくさん排出しております。私は激しさの探求からスラッジコアにたどり着いてやはりEyehategod(アメリカ、ニューオーリンズのバンド)を聴いてわかりやすく「やべー」となった口。Iron Monkeyを聴いたときはその一見するとの聞きやすさにびっくりしたものの、すぐにその軽快かつだるくて不穏な音世界にハマったものだ。
音質的には確実に2010年台の洗練されて迫力のある音にアップデートされている。ジリジリした感じは消えて非常にクリアだ。ただ中身的にはやはりIron Monkeyだ。バンドが存続していたらなるほどこういう音を出していただろうと言う感じ。スラッジコア/サイケ・ドゥームを自称することもあってただただ遅く陰惨なスラッジとは一線を画す音と曲作り。ヴィンテージ感のあるロックからの由来を感じさせる溜めのある、ひっぱるようなリフが特徴でゴリゴリ圧殺系とは明らかに異なるうねりのあるリズム感が魅力。決して音の数は多くないのに魔術のような空間を組み立てるリフ。もっと危険な音を出すバンドはあるが、このIron Monkeyの現実的なヤバさというのはジャンルは異なるがUNSANEなんかに似ているかも。ひょっとしたらストリート感と言っても良いかもしれない。不敵に微笑む危険な男、という感じで余裕がある感じが逆に不穏だ。酩酊しきって酔歩するように経過なロック/ドゥームの境界を超えて、明らかに行き過ぎた/やりすぎた感のあるスラッジの世界に足を突っ込むところが最高。前半のノリの良さがゲートウェイでヤバみが増してくる後半に気づくと案内されている、というかケツを足蹴にされて悪夢の陥穽に落ちたような非道な感じ。ラスト「Moreland St.Hammervortex」は大団円という感じ。
そしてやはりボーカルが一番気になるところ。なくなったJohnny Morrowという人はほんとう危険な感じのする声の持ち主で混沌とした悪徳を声で表現した、みたいな魅力の持ち主だった。このバンドの(当時の)看板はMorrowの独特なボーカリゼーションということは残されたメンバーも自覚するところであって、全く異なる系統のボーカルを載せるというよりはMorrowの歌唱法をなぞるようにJimがマイクを取る。前のボーカリストは上手い下手とかではない次元で人を魅了したが、その魅力は声質によるところもあって、異常なしゃがれ声だった。さすがにJimは体格と喉も別物なのでそのしゃがれの妙味というのはほぼない。ただぐしゃっと潰したようなこもった高音がよく出た耳障りな下品な、というところはかなり良い味を出している。ナチュラルに歌い上げる、もしくは叫ぶ(Morrowはかなりナチュラルに思える。)というよりはやはり演技力というのは明らかに酷だけど装飾性を感じるのは確か。ただし個人的にはこのくらいくどい方がいかがわしさがあって良いと思う。私的にはIron Monkeyの今のボーカルはJimで全く問題ない。思い入れのある方はまた違うのだろうが。
Iron Monkeyは名前だけしか知らないな〜という人はまずこの音源から買ってみたら時代のギャップはないと思う。Iron MonkeyといえばJohnny Morrowでしょ!という人も気持ちはわかるが、一旦通して聴いてほしい。やはり他に類を見ないバランスの”悪い”スラッジコアを鳴らすバンドだと思う。
どうでもいいけどとにかくあのお猿のロゴが格好良すぎてパーカーとLPのバンドルを買った上にT-シャツも購入した。もったいなくて着れないくらいかっこいい。
ラベル:
Iron Monkey,
イギリス,
スラッジコア,
ドゥームメタル,
音楽
DS-13/UMEÅ HARDCORE FOREVER, FOREVER UMEÅ HARDCORE
スウェーデンはヴェステルボッテン県(調べるとスウェーデンの上の方)、ウメオのハードコアバンドのディスコグラフィー盤。
2017年にLPやCDの形式で複数のレーベルからリリースされた。私が買ったのは日本のCrew for Life Recordsからリリースされた日本盤。(CD形式は日本盤だけみたい。)
DS-13はDemon System 13の意味で1996年に結成、本国だけでなくアメリカ、ヨーロッパ、日本なども含めて世界的に活動したが2002年に一度解散。2012年に再結成し、また精力的に活動している。Pusheadのイラストを使った音源は聞いたことない私でもなんとなーく知っていた。おそらく来日を記念してという意味もあってのこのディスコグラフィー日本盤だろうと思う。私は再来日ライブには行けなかった。この音源とても内容が素晴らしいので非常に残念。
この音源はアルバムを除く1997年から2000年までのスプリット音源や、EP、コンピレーションに収録、提供した音源を集めたもの。全部で67曲あり、リマスターが施されている。
最近日本のハードコアバンドのインタビューを読むと一昔前は本当にハードコアを聞く人が少なくて大変だったようだ。最近は(自分が興味を持ったことも大きいだろうけど)一昔前に比べるとやや盛り上がってきたのかな?という感じ。
このDS-13は1996年から活動しているバンドだから現行スタイルにはむしろ影響を与えた方のバンド。67曲を聞いてて思ったのは非常に聞きやすいってこと。(とくにパワーバイオレンスなどの激しいタイプの)ハードコアバンドは1曲が短いからアルバム全体も短くなる傾向にある。短くても中身的には結構重たくて濃いので、濃厚な家系ラーメンのように短い尺がちょうどよいくらいなのだけど、このバンドに関しては67曲がすっと聴ける!それもあとに残らない軽さではなく、これはいい曲、これもいい曲という感じに耳を通して脳にガツガツくる。こういうのはなかなかない。ディスコグラフィーだから良い曲のみを集めたベスト盤ってわけでもないし。この聞きやすさの秘密は今のところ3つくらいあって、一つは音がおもたすぎないこと。低音をバリバリ強調して不穏でノイジーなフィードバックノイズを添えた昨今の音とは一線を画す、ハードコアパンクの延長線上にある中音域の厚みがあたたかみすらある音が非常に気持がよい。もう一つは曲によって聞き所がきちんと用意されていること。たしかにとんでもない速度で突っ走る曲がほとんどなのだが、スラッシュ一辺倒でなくて結構コード感のある聞きやすいパンクな曲構成になっていたりもする。シンガロングに彩られたメロディが出て来る曲もある。(「Degenerated Generation」や「(I'm Not Your)Steppin' Stone」なんかは歌えるくらいキャッチー。)強烈な速度とその極端にある急停止からの鈍足、というスタイルが(もちろん良いことでもある)一つのやり方になっている昨今は特に、こういうふうに脇道にそれているというか、いろいろな試行錯誤が、結果的に勢いのある曲を主体とした音源の中でいい感じに異彩をはなちつつ凹凸を作っている。そして最後の要素は全体を覆うポジティブ感。ぬるいポップパンクだというのではないし「死んだ警官だけが良い警官だ!」と叫ぶ過激さ、攻撃性がありながらも、音的には陰惨にならないでエネルギッシュでありながら創造的だ。聴いていて単純に元気が出てくる。
演奏の感じやボーカルの親しみやすさからCharles Bronsonにちょっとだけ似ているかな?なんて思った。非常に格好良くこのDS-13というバンドを紹介しているディスコグラフィーだと思う。現行のパワーバイオレンスのようなキレッキレのハードコアが好きな人も、きっちりとしたハードコアパンクが好きなのだという人にも進められる音源では…なんて思ったりする。非常におすすめ。
2017年にLPやCDの形式で複数のレーベルからリリースされた。私が買ったのは日本のCrew for Life Recordsからリリースされた日本盤。(CD形式は日本盤だけみたい。)
DS-13はDemon System 13の意味で1996年に結成、本国だけでなくアメリカ、ヨーロッパ、日本なども含めて世界的に活動したが2002年に一度解散。2012年に再結成し、また精力的に活動している。Pusheadのイラストを使った音源は聞いたことない私でもなんとなーく知っていた。おそらく来日を記念してという意味もあってのこのディスコグラフィー日本盤だろうと思う。私は再来日ライブには行けなかった。この音源とても内容が素晴らしいので非常に残念。
この音源はアルバムを除く1997年から2000年までのスプリット音源や、EP、コンピレーションに収録、提供した音源を集めたもの。全部で67曲あり、リマスターが施されている。
最近日本のハードコアバンドのインタビューを読むと一昔前は本当にハードコアを聞く人が少なくて大変だったようだ。最近は(自分が興味を持ったことも大きいだろうけど)一昔前に比べるとやや盛り上がってきたのかな?という感じ。
このDS-13は1996年から活動しているバンドだから現行スタイルにはむしろ影響を与えた方のバンド。67曲を聞いてて思ったのは非常に聞きやすいってこと。(とくにパワーバイオレンスなどの激しいタイプの)ハードコアバンドは1曲が短いからアルバム全体も短くなる傾向にある。短くても中身的には結構重たくて濃いので、濃厚な家系ラーメンのように短い尺がちょうどよいくらいなのだけど、このバンドに関しては67曲がすっと聴ける!それもあとに残らない軽さではなく、これはいい曲、これもいい曲という感じに耳を通して脳にガツガツくる。こういうのはなかなかない。ディスコグラフィーだから良い曲のみを集めたベスト盤ってわけでもないし。この聞きやすさの秘密は今のところ3つくらいあって、一つは音がおもたすぎないこと。低音をバリバリ強調して不穏でノイジーなフィードバックノイズを添えた昨今の音とは一線を画す、ハードコアパンクの延長線上にある中音域の厚みがあたたかみすらある音が非常に気持がよい。もう一つは曲によって聞き所がきちんと用意されていること。たしかにとんでもない速度で突っ走る曲がほとんどなのだが、スラッシュ一辺倒でなくて結構コード感のある聞きやすいパンクな曲構成になっていたりもする。シンガロングに彩られたメロディが出て来る曲もある。(「Degenerated Generation」や「(I'm Not Your)Steppin' Stone」なんかは歌えるくらいキャッチー。)強烈な速度とその極端にある急停止からの鈍足、というスタイルが(もちろん良いことでもある)一つのやり方になっている昨今は特に、こういうふうに脇道にそれているというか、いろいろな試行錯誤が、結果的に勢いのある曲を主体とした音源の中でいい感じに異彩をはなちつつ凹凸を作っている。そして最後の要素は全体を覆うポジティブ感。ぬるいポップパンクだというのではないし「死んだ警官だけが良い警官だ!」と叫ぶ過激さ、攻撃性がありながらも、音的には陰惨にならないでエネルギッシュでありながら創造的だ。聴いていて単純に元気が出てくる。
演奏の感じやボーカルの親しみやすさからCharles Bronsonにちょっとだけ似ているかな?なんて思った。非常に格好良くこのDS-13というバンドを紹介しているディスコグラフィーだと思う。現行のパワーバイオレンスのようなキレッキレのハードコアが好きな人も、きっちりとしたハードコアパンクが好きなのだという人にも進められる音源では…なんて思ったりする。非常におすすめ。
ダン・シモンズ/エンディミオン
アメリカの作家のSF小説。
「ハイペリオン」シリーズの第3弾。順調に読み進めてまいりました。
上巻は新品で買えたのだが、下巻が品切れて中古で購入。
7人の巡礼たちの物語が終わって300年。人類はテクノコアと決別し、瞬間転移などテクノコア由来の技術の多くが使用できなくなり、人類の統合組織は崩壊。恒星間の距離が再び絶対的なものになり、移動に時間が掛かる分各惑星は断絶状態になり、独自の進歩を続けていくことになった。そんな第二期の宇宙史でヘゲモニー時代は虫の息だったカトリック教会がテクノコアの技術、人体を組成させる十字架の改良に成功。蘇生の際の人体劣化を克服し、人類にほぼ完全な不死を提供することであっという間に宇宙における人類の領域を征服していく。巡礼たちの物語も過去の伝説めいたものになりつつある”今”、伝説の舞台になった惑星ハイペリオンに生まれたロール・エンディミオンはなんとなく気に入らない、という理由からカトリックの洗礼(つまり不死)を拒否。自由気ままに暮らしていたが、ある日冤罪で死刑の憂き目に合うことに。窮地の彼を救ったのは伝説の巡礼のうち一人、「詩篇」を書いたマーティン・サイリーナスだった。彼はロールに対して人類の救世主となる巡礼の一人の子供である少女を守って銀河を救えという。
「ハイペリオン」シリーズは全部で4つの物語があるが(文庫だと全部上下分冊だから全部で8冊。)、一旦前作「ハイペリオンの没落」で物語的には一区切り。登場人物や設定は引き継ぎつつ、大きなブレイクスルー(人類の不死の獲得)と時間の経過(300年)を間にはさみつつ、また新しい物語がこの「エンディミオン」と続く「エンディミオンの覚醒」で書かれることになる。
読んでみると前作までとは色々変わっていて面白い。まず設定だけど転移ゲートがもたらす、瞬間転移技術(これはその仕組は人類は結局わからなかったけど便利だから使い続けていた、という設定が人類らしく適当で良い。)がなくなったこともあり、人類同士の連携が取れずに宇宙にいながら文明は大きく後退している。技術の間断ない共有というのが進歩に大きく有効であるということがよく分かる。前作ではヘゲモニーという組織が人類の音頭を取っていたが、これが崩壊し、とっくに捨て去ったはずの神権政治が取って代わっている。それも不死をちらつかせての反映だから(ココらへんにも人間の弱さ、都合の善さが表現されている)、実際ろくなもんでもないことははじめからわかっている。前作ではつましい求道者だったキリスト教徒は醜い権力者になっている。
それから物語の構造も変わっていて、過去の因縁がある7人の巡礼が集まり、過去を語りながら宇宙の欺瞞を暴きつつ、その後の世界を変える戦いに結実した重たい(もちろん褒め言葉で)前二作に比較すると、今回新しい主人公は良くも悪くも軽い男で重たい過去も因縁もなく、いわば巻き込まれ型と言うかたちで物語に参加することになる。小さい女の子と給仕のようなアンドロイド(彼は典型的な執事キャラで肌は真っ青という物語的な個性がある。スターウォーズにも通じる典型的な感じがある。)と悪い奴ら、つまりカトリック教会からただひたすら逃げていく、というシンプルな物語になっている。これによって娯楽性が大いにましており、あとがきにも書かれているとおり本当にただただ若者二人+アンドロイドの逃避行、ってことになっている。物語の面白さはその構造的な複雑さや逆に単純さにはよらない、というのは非常に面白い。逃避行は惑星巡り、と言うかたちになっており、全く道の新世界という要素と、現代のつまり読む人がいる今の世界に通じる基地の要素がうまく混ぜ合わさり、地球とは異なる環境(その中の幾つかは非常に極端、つまりすごく寒いとか、呼吸ができないとか)で再現されている。この物語はなんといってもこの異星、異世界といっていいほどの魅力がある別世界の描写が素晴らしい。想像力の限界に挑む、という新奇さだけでなくなんとなくノスタルジックな現代の残り香があるところがその魅力の秘密かと思う。
敵を張るカトリック教会サイドのキャラクターも魅力的で(ただし一部不満もあってそれは今読んでいる「エンディミオンの覚醒」の時に書くと思う。)物語を盛り上げる。
どうやら4部作でこの物語が一番好きだという人もいるらしい。多分前二作を読まなくてもわかると思うけど、可能だったらやはり「ハイペリオン」から読んだほうが良いと思う。
2017年11月5日日曜日
V.A./Twin Peaks:Music From The Limited Event Series
アメリカのTVドラマのサウンドトラック。
2017年にRhino Entertainment Company、a Warner Music Group Companyからリリースされた。
今年ハマったものがあってそれがアメリカのTVドラマ「Twin Peaks」。鬼才デヴィッド・リンチがマーク・フロストとタッグを組んで作成したドラマで1990年に放送開始され、その後日本でもブームになった。私はたしか秋本治さんの漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」でその名前が出てきたのを覚えているが、当時ドラマは見たことがなかった。今年25年ぶりに新作「Twin Peaks The Return」が放送されるということで、「へー」くらいに思っていたが私の上司が「Twin Peaks」のファンで「見れるなら絶対見ろ!」ってことなので(「Twin Peaks」はいまんとこwowowでしか見れない状態で私の家はwowowが見れる。)、新シーズン前に放送された旧シリーズを見たらこれがまたすごい面白いくてどっぷりハマったわけ。
新シリーズは面白いことにエンディングの曲が毎回異なる。劇中でロードハウスと呼ばれるバー(正式名称はバンバンバー(Bang Bang Bar))で様々なアーティストがライブを披露する、という体裁でエンディング曲が流れるのだ。(これ子供の頃に例えば自分アニメとかの監督になったら毎回好きな曲流したいな!とか誰でも妄想すると思う。)その曲がいちいち格好いいので個別に買うよりは、と思ってそのエンディング曲を集めたサウンドトラックを購入したわけ。(別に劇中の曲を収録したサントラもある。)
なんといっても目玉は第8話にでてくるnine inch nailsの「She's Gone Away」かな。曲自体はもうバンドの「Not Actual Events」というEPで聴いていたのだが、なんとこの曲はリンチの要望でこのドラマのために描き下ろしたものとは知らなかったな。しかも一回作ったものをリンチが「明るいな〜、こういうのじゃないんだよな〜」ってボツにしたんだって。ninに曲作ってもらったらどんな曲でも「すげー曲っす!もちOKす!!」って普通はなると思うのだけど、さすが監督すげーなと思います。
「Twin Peaks」はとある少女の殺害事件から端を発する、冒頭はわりとかっちりした犯罪捜査者かなと思いきや、回を重ねるごとに怪しい世界に入り込んでいく作品。リンチ監督も御年70歳を超えてくるということでもっとおとなしめの、ぼやーっとした曲が多いのかと思いきやninもそうだけどかなりしっかりとした、多彩な曲が並んでいるのが印象的。びく皆曲もあるけど、明るい曲も多い。やはりアメリカということでカントリー調の曲もそれなりにある。「Twin Peaks」はただ殺人を、ただ不気味さを書いている作品ではなくて、ワシントン州にある架空の小さい町ツイン・ピークスとその子に住む様々な人々の生活の模様を書いている作品である。ロードハウスというのはそんなツイン・ピークスに住む人がやすらぎや、楽しみを求めに来る場所なので当然、架空の登場人物、主人公たちだけでなく街に住む普通の人々が好んで毎日聞きそうな曲が選ばれているのだと思う。恐れる曲もあれば、しっとり聞ける曲もあるが、通して聴いてみるとどれも没入感のある、かなり力のこもった曲ばかり選ばれているように思う。安易に日本のテレビ番組を批判するのもちょっとどうかと思うが、例えば主役を張るアイドルの男の子、女の子が所属する、とにかくポップで名だたるプロデューサーが手がけたよくも悪くも軽い曲、というのとは一線を画す内容でどれも非常に重たく、濃い。毎日がただ良いことの連続で内容に、架空の、存在すらしない人々の気持ちを反映したかのような豊かな感情が、バリエーションの有る楽曲に現れているのだと思う。ドラマを見ていない人がこのアルバムを聞いてどう思うのかは気になるところだけど、ドラマを見ると最後の曲が毎回違う、曲の雰囲気も輪ごとにガラリと変わるというのは「Twin Peaks The Return」の場合は非常にしっくり来る。見た人ならわかるだろうがリンチ監督は尺を贅沢に、普通の監督なら省くような人の動きをゆっくり、じっくり、執拗に時間をかけて画面に映し出す。そこには喜怒哀楽というシンプルな4つの元素に分解できない何かに対する強いこだわりがある。それ故何が言いたいのかわかりにくいと批判されることもあるだろう。ちなみにデヴィッド・リンチは音楽に対して非常にこだわりのある人でたしか自分でも作曲をするはずだ。そんな監督のこだわりが選曲にも表れているなと。
個人的に気に入ったのはどっしりとしたラテンのリズムに半端ない声量と技量がのっかるRebekah Del Rioの「No Stars」。重厚なのに歌いたくなるくらいポップなのがすげー。ひたすらクールなロックンロールZZ Topの「Sharp Dressed Man」。むかし車のCMとかで目にしたZZ TOP初めて聴いた。声がすごくセクシー。アメリカ!のイメージをそのまま曲にしたような爽快さ。
「Twin Peaks」はとても面白いドラマなので是非オススメしたいが、やはり新旧合わせるとそれなりにボリュームがあるので躊躇する人もいるだろう。まずはサントラ聴いて雰囲気を掴んでは、ってのは難しいか。私は本編に好感があるからそれがサントラにも反映されていると思うが、それを抜きにしても良いアルバムだと思うので気になった人は是非どうぞ。
ninが出た8話放送時はやっぱり興奮した!
2017年にRhino Entertainment Company、a Warner Music Group Companyからリリースされた。
今年ハマったものがあってそれがアメリカのTVドラマ「Twin Peaks」。鬼才デヴィッド・リンチがマーク・フロストとタッグを組んで作成したドラマで1990年に放送開始され、その後日本でもブームになった。私はたしか秋本治さんの漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」でその名前が出てきたのを覚えているが、当時ドラマは見たことがなかった。今年25年ぶりに新作「Twin Peaks The Return」が放送されるということで、「へー」くらいに思っていたが私の上司が「Twin Peaks」のファンで「見れるなら絶対見ろ!」ってことなので(「Twin Peaks」はいまんとこwowowでしか見れない状態で私の家はwowowが見れる。)、新シーズン前に放送された旧シリーズを見たらこれがまたすごい面白いくてどっぷりハマったわけ。
新シリーズは面白いことにエンディングの曲が毎回異なる。劇中でロードハウスと呼ばれるバー(正式名称はバンバンバー(Bang Bang Bar))で様々なアーティストがライブを披露する、という体裁でエンディング曲が流れるのだ。(これ子供の頃に例えば自分アニメとかの監督になったら毎回好きな曲流したいな!とか誰でも妄想すると思う。)その曲がいちいち格好いいので個別に買うよりは、と思ってそのエンディング曲を集めたサウンドトラックを購入したわけ。(別に劇中の曲を収録したサントラもある。)
なんといっても目玉は第8話にでてくるnine inch nailsの「She's Gone Away」かな。曲自体はもうバンドの「Not Actual Events」というEPで聴いていたのだが、なんとこの曲はリンチの要望でこのドラマのために描き下ろしたものとは知らなかったな。しかも一回作ったものをリンチが「明るいな〜、こういうのじゃないんだよな〜」ってボツにしたんだって。ninに曲作ってもらったらどんな曲でも「すげー曲っす!もちOKす!!」って普通はなると思うのだけど、さすが監督すげーなと思います。
「Twin Peaks」はとある少女の殺害事件から端を発する、冒頭はわりとかっちりした犯罪捜査者かなと思いきや、回を重ねるごとに怪しい世界に入り込んでいく作品。リンチ監督も御年70歳を超えてくるということでもっとおとなしめの、ぼやーっとした曲が多いのかと思いきやninもそうだけどかなりしっかりとした、多彩な曲が並んでいるのが印象的。びく皆曲もあるけど、明るい曲も多い。やはりアメリカということでカントリー調の曲もそれなりにある。「Twin Peaks」はただ殺人を、ただ不気味さを書いている作品ではなくて、ワシントン州にある架空の小さい町ツイン・ピークスとその子に住む様々な人々の生活の模様を書いている作品である。ロードハウスというのはそんなツイン・ピークスに住む人がやすらぎや、楽しみを求めに来る場所なので当然、架空の登場人物、主人公たちだけでなく街に住む普通の人々が好んで毎日聞きそうな曲が選ばれているのだと思う。恐れる曲もあれば、しっとり聞ける曲もあるが、通して聴いてみるとどれも没入感のある、かなり力のこもった曲ばかり選ばれているように思う。安易に日本のテレビ番組を批判するのもちょっとどうかと思うが、例えば主役を張るアイドルの男の子、女の子が所属する、とにかくポップで名だたるプロデューサーが手がけたよくも悪くも軽い曲、というのとは一線を画す内容でどれも非常に重たく、濃い。毎日がただ良いことの連続で内容に、架空の、存在すらしない人々の気持ちを反映したかのような豊かな感情が、バリエーションの有る楽曲に現れているのだと思う。ドラマを見ていない人がこのアルバムを聞いてどう思うのかは気になるところだけど、ドラマを見ると最後の曲が毎回違う、曲の雰囲気も輪ごとにガラリと変わるというのは「Twin Peaks The Return」の場合は非常にしっくり来る。見た人ならわかるだろうがリンチ監督は尺を贅沢に、普通の監督なら省くような人の動きをゆっくり、じっくり、執拗に時間をかけて画面に映し出す。そこには喜怒哀楽というシンプルな4つの元素に分解できない何かに対する強いこだわりがある。それ故何が言いたいのかわかりにくいと批判されることもあるだろう。ちなみにデヴィッド・リンチは音楽に対して非常にこだわりのある人でたしか自分でも作曲をするはずだ。そんな監督のこだわりが選曲にも表れているなと。
個人的に気に入ったのはどっしりとしたラテンのリズムに半端ない声量と技量がのっかるRebekah Del Rioの「No Stars」。重厚なのに歌いたくなるくらいポップなのがすげー。ひたすらクールなロックンロールZZ Topの「Sharp Dressed Man」。むかし車のCMとかで目にしたZZ TOP初めて聴いた。声がすごくセクシー。アメリカ!のイメージをそのまま曲にしたような爽快さ。
「Twin Peaks」はとても面白いドラマなので是非オススメしたいが、やはり新旧合わせるとそれなりにボリュームがあるので躊躇する人もいるだろう。まずはサントラ聴いて雰囲気を掴んでは、ってのは難しいか。私は本編に好感があるからそれがサントラにも反映されていると思うが、それを抜きにしても良いアルバムだと思うので気になった人は是非どうぞ。
ninが出た8話放送時はやっぱり興奮した!
THE DONOR/ALL BLUES
日本は石川県金沢市のハードコアバンドの2ndアルバム。
2017年にTill Your Death Recordsからリリースされた。
前作「AGONY」からコンピレーションアルバムの参加などを経て3年ぶりにリリースされた新作。真っ黒いイメージが印象的だった前作から打って変わって白を貴重としたアートワークになっている。ギタリストは同じ金沢のGreenMachineでも活動している。このアルバムのアートワークに使われている写真も多分GreenMachineのメンバーが撮ったものだと思う。
全部で10曲を22分で駆け抜けるわけだからだいたいその音楽性はわかると思う。今年リリースされた3LAのコンピレーションにも曲を提供していたが、いわゆるネオクラスト、激情とは一線を画する音楽性。もともと内省的な音楽性を日本の激情バンドたちはさらに激化させた内容にアップデートして悩み苦しむハードコアにしている印象もあるが(批判しているわけではない)、THE DONORはその流れにはあまり与しないようだ。悩みがない人間は私が知っている限り存在しないが、その内省的な葛藤をこのバンドはすべて攻撃力と機動力のパラメータに振り切っているようだ。多分に感情的だが、叙情的とはいえない。音楽ジャンルとしてのエモーショナルなハードコアとは距離をおいた荒涼としたハードコアを演奏している。
とにかくささくれだって重量感のある、錆びついた金属のようなギターの音質はたわんだ北欧のメタル/ハードコアを彷彿とさせる。はじめ聞いたときは前作以上に例えばTrap Themのようなバンドの出すサウンドに通じるところがあると思う。速さの逆を行く遅さ、つまりスラッジ成分も取り込んでいるところもその手のハードコアに通じるところがある。いわゆるアンビエント、アトモスフェリック、ポストといった形容詞が表現するともすると冗長、高尚になってしまう要素に関してはこれを余計な夾叉物として一切を排除する。いわば極悪非道なハードコアなのだが、よくよく考えてみるとこういったピュアなバンドというのはなかなか日本にはいないかもしれない。もっと先鋭化してパワーバイオレンスの荒涼とした地平にひたすら残虐性とヘイトを求めるか、もしくは日本人の真面目さを反映した悩み多き鬱屈さを追求するエモバイオレンス方面のハードコアに舵を切るか、その二択のいずれかを選択するようなバンドが多い気がする中、あえてピュアなハードコアを鳴らすというのは結構稀有ではと思う。
ただまったくもって北欧スタイルを金沢で再生したのがTHE DONORかというとそこが少し違くて、そしてそこがこのバンドの面白いところ。激しい音楽に抒情性を混ぜ込む、というのは陳腐な言い回しだが、実際にやるとなるとある程度手法は決まっていて、そういった意味では日本の激情はその手の表現が得意である。THE DONORはここを別の手法で攻めていて、感覚的にはトレモロに感情を込めるブラックメタルに似ているが、そこまでわかり易くないのが、チャレンジンクで面白いし、仕上がりが絶妙に格好いい。そういった意味では3LAのコンピ「ろくろ」に提供した「kagerou」はやはり白眉の出来では。コンピとアルバムでは別バージョンになっており違いを楽しむことができる。とにかくアウトロの放り出すような、ヤケクソめいた表現が曲の終わりってことで最高のクライマックスになっている。
いわゆるジャパニーズスタイルのハードコアが激しい音楽性にいろいろな形で豊かな表現を取り入れたとしたら、やはりこのバンドもその系譜にあるということだろうか。
前作をまっとうにアップデートさせた素晴らしい内容でこの手の音楽が好きなら聞き逃す手はない非常におすすめしたい音源。この音源とそれに伴うライブの後、THE DONORは年内での活動休止をアナウンスしている。非常に残念なことだ。視聴できるところが見つからなかったので買って聴いてください。
2017年にTill Your Death Recordsからリリースされた。
前作「AGONY」からコンピレーションアルバムの参加などを経て3年ぶりにリリースされた新作。真っ黒いイメージが印象的だった前作から打って変わって白を貴重としたアートワークになっている。ギタリストは同じ金沢のGreenMachineでも活動している。このアルバムのアートワークに使われている写真も多分GreenMachineのメンバーが撮ったものだと思う。
全部で10曲を22分で駆け抜けるわけだからだいたいその音楽性はわかると思う。今年リリースされた3LAのコンピレーションにも曲を提供していたが、いわゆるネオクラスト、激情とは一線を画する音楽性。もともと内省的な音楽性を日本の激情バンドたちはさらに激化させた内容にアップデートして悩み苦しむハードコアにしている印象もあるが(批判しているわけではない)、THE DONORはその流れにはあまり与しないようだ。悩みがない人間は私が知っている限り存在しないが、その内省的な葛藤をこのバンドはすべて攻撃力と機動力のパラメータに振り切っているようだ。多分に感情的だが、叙情的とはいえない。音楽ジャンルとしてのエモーショナルなハードコアとは距離をおいた荒涼としたハードコアを演奏している。
とにかくささくれだって重量感のある、錆びついた金属のようなギターの音質はたわんだ北欧のメタル/ハードコアを彷彿とさせる。はじめ聞いたときは前作以上に例えばTrap Themのようなバンドの出すサウンドに通じるところがあると思う。速さの逆を行く遅さ、つまりスラッジ成分も取り込んでいるところもその手のハードコアに通じるところがある。いわゆるアンビエント、アトモスフェリック、ポストといった形容詞が表現するともすると冗長、高尚になってしまう要素に関してはこれを余計な夾叉物として一切を排除する。いわば極悪非道なハードコアなのだが、よくよく考えてみるとこういったピュアなバンドというのはなかなか日本にはいないかもしれない。もっと先鋭化してパワーバイオレンスの荒涼とした地平にひたすら残虐性とヘイトを求めるか、もしくは日本人の真面目さを反映した悩み多き鬱屈さを追求するエモバイオレンス方面のハードコアに舵を切るか、その二択のいずれかを選択するようなバンドが多い気がする中、あえてピュアなハードコアを鳴らすというのは結構稀有ではと思う。
ただまったくもって北欧スタイルを金沢で再生したのがTHE DONORかというとそこが少し違くて、そしてそこがこのバンドの面白いところ。激しい音楽に抒情性を混ぜ込む、というのは陳腐な言い回しだが、実際にやるとなるとある程度手法は決まっていて、そういった意味では日本の激情はその手の表現が得意である。THE DONORはここを別の手法で攻めていて、感覚的にはトレモロに感情を込めるブラックメタルに似ているが、そこまでわかり易くないのが、チャレンジンクで面白いし、仕上がりが絶妙に格好いい。そういった意味では3LAのコンピ「ろくろ」に提供した「kagerou」はやはり白眉の出来では。コンピとアルバムでは別バージョンになっており違いを楽しむことができる。とにかくアウトロの放り出すような、ヤケクソめいた表現が曲の終わりってことで最高のクライマックスになっている。
いわゆるジャパニーズスタイルのハードコアが激しい音楽性にいろいろな形で豊かな表現を取り入れたとしたら、やはりこのバンドもその系譜にあるということだろうか。
前作をまっとうにアップデートさせた素晴らしい内容でこの手の音楽が好きなら聞き逃す手はない非常におすすめしたい音源。この音源とそれに伴うライブの後、THE DONORは年内での活動休止をアナウンスしている。非常に残念なことだ。視聴できるところが見つからなかったので買って聴いてください。
ダン・シモンズ/ハイペリオンの没落
アメリカの作家によるSF小説。
「ハイペリオン」から始まる4部作の第2弾。一応この4部作は2つに分けることができるので、ここで一旦「ハイペリオン」から始まった物語に片がつく。
意を決して時間の墓標に足を踏み入れた6人の巡礼たち。しかし肝心のシュライクは顕現しない。やきもきする一行をよそに惑星はるか上空での連邦ヘゲモニーと宇宙の蛮族アウスターとの決戦は激化の一途をたどる。思いがけない方法によってウェブ内にアウスターが進行していることがわかり、連邦はその存続の危機に立たされることになる。
大団円に向かう前にとにかく大風呂敷を広げまくるダン・シモンズ。矢継ぎ早に連邦は危機に立たされることになる。前作では巡礼6人がそれぞれ別個の物語を旅の途中で語る、という形式だったため、作者があえて6つの物語を異なるジャンルと言ってほどのバリエーションを持たせて1冊の本にした入れ子構造がまるで「ハイペリオン」という本を連作短編集のようにしていた趣があったが、今作では過去が一通り語られたあとで物語が未来に向かって一直線に動き始める。視点の転換はさすがにあるものの、概ね主人公というのが巡礼とその他に設定されており、ある程度固定化された視座から物語を読者が俯瞰できる。
また合う人類属する連邦対アウスターの宇宙を舞台にした戦争が物語の中心を貫いており、スケール感がアップ。巨大な連邦が窮地に陥っていくさまはなかなかのスリルがある。
とにかく物語よく練られていて最近ありがちなどんでん返しだけで目を引く、オチだけで長いページを持たせる系のとんでもSF(謎がいっこしないのはいいとしても、それありきのストーリーが予定調和でむりがあって全然しっくりこない)やセンセーショナルな状況ややたらと個人の判断が世界の行く末を判断する、薄っぺらい残酷さなどで悪目立ちする軽薄な小説群とは明らかに異なる、非常にしっかりとして骨組みのある”物語”がある。この物語にどっぷり浸れるのが読書の醍醐味の一つだと思うがそれをもう120%以上満たしてくれる濃厚さ。大森望さんの解説でも書かれているとおり、実はこの「ハイペリオン」というのは全く革新性がない物語なのだが、それでも面白さというのは抜群だ。
思うに人間というのは誰かに操られている、と考えてしまってそれが許せない性質があるらしい。登場人物の一人ソルの例もあるし、「ハイペリオン」でも裏で人類を操る何者かからの開放というのが物語的なカタルシスとして働いている。シュライクというのは特定の登場人物たちによって神の立場崇め奉られているという点も興味深い。実際今息災にやれているなら一体誰に操られていようと気にしなくてもよいのでは?と怠惰な私は思うのだ。西遊記の孫悟空のごとく、お釈迦様の手のひらの上でもかまわないというのが私なのだが、それが仏なら良いが悪鬼羅刹だとかなわないというのはわかる。しかし最終的に偶然を擬人化して暴君のレッテルを貼るのも無理な話で、今自分が何者かに操られている、以内の判断はどうしたら?とも思うわけで、そう考えると宇宙に拡大した人類から一掃されない号の深さのようなものも感じられて面白い。やはり良い物語というのはそのスケールや舞台に関係なく、普遍性というのがその核に閉じ込められていると思う。
数々の謎にもきれいに答えが並べられており、決してハッタリや虚仮威しではない物語の完成度に感服する4部作の前編のフィナーレ。ぜひ「ハイペリオン」からどうぞ。私はもちろん「エンディミオン」からの後半も楽しむつもりである。
「ハイペリオン」から始まる4部作の第2弾。一応この4部作は2つに分けることができるので、ここで一旦「ハイペリオン」から始まった物語に片がつく。
意を決して時間の墓標に足を踏み入れた6人の巡礼たち。しかし肝心のシュライクは顕現しない。やきもきする一行をよそに惑星はるか上空での連邦ヘゲモニーと宇宙の蛮族アウスターとの決戦は激化の一途をたどる。思いがけない方法によってウェブ内にアウスターが進行していることがわかり、連邦はその存続の危機に立たされることになる。
大団円に向かう前にとにかく大風呂敷を広げまくるダン・シモンズ。矢継ぎ早に連邦は危機に立たされることになる。前作では巡礼6人がそれぞれ別個の物語を旅の途中で語る、という形式だったため、作者があえて6つの物語を異なるジャンルと言ってほどのバリエーションを持たせて1冊の本にした入れ子構造がまるで「ハイペリオン」という本を連作短編集のようにしていた趣があったが、今作では過去が一通り語られたあとで物語が未来に向かって一直線に動き始める。視点の転換はさすがにあるものの、概ね主人公というのが巡礼とその他に設定されており、ある程度固定化された視座から物語を読者が俯瞰できる。
また合う人類属する連邦対アウスターの宇宙を舞台にした戦争が物語の中心を貫いており、スケール感がアップ。巨大な連邦が窮地に陥っていくさまはなかなかのスリルがある。
とにかく物語よく練られていて最近ありがちなどんでん返しだけで目を引く、オチだけで長いページを持たせる系のとんでもSF(謎がいっこしないのはいいとしても、それありきのストーリーが予定調和でむりがあって全然しっくりこない)やセンセーショナルな状況ややたらと個人の判断が世界の行く末を判断する、薄っぺらい残酷さなどで悪目立ちする軽薄な小説群とは明らかに異なる、非常にしっかりとして骨組みのある”物語”がある。この物語にどっぷり浸れるのが読書の醍醐味の一つだと思うがそれをもう120%以上満たしてくれる濃厚さ。大森望さんの解説でも書かれているとおり、実はこの「ハイペリオン」というのは全く革新性がない物語なのだが、それでも面白さというのは抜群だ。
思うに人間というのは誰かに操られている、と考えてしまってそれが許せない性質があるらしい。登場人物の一人ソルの例もあるし、「ハイペリオン」でも裏で人類を操る何者かからの開放というのが物語的なカタルシスとして働いている。シュライクというのは特定の登場人物たちによって神の立場崇め奉られているという点も興味深い。実際今息災にやれているなら一体誰に操られていようと気にしなくてもよいのでは?と怠惰な私は思うのだ。西遊記の孫悟空のごとく、お釈迦様の手のひらの上でもかまわないというのが私なのだが、それが仏なら良いが悪鬼羅刹だとかなわないというのはわかる。しかし最終的に偶然を擬人化して暴君のレッテルを貼るのも無理な話で、今自分が何者かに操られている、以内の判断はどうしたら?とも思うわけで、そう考えると宇宙に拡大した人類から一掃されない号の深さのようなものも感じられて面白い。やはり良い物語というのはそのスケールや舞台に関係なく、普遍性というのがその核に閉じ込められていると思う。
数々の謎にもきれいに答えが並べられており、決してハッタリや虚仮威しではない物語の完成度に感服する4部作の前編のフィナーレ。ぜひ「ハイペリオン」からどうぞ。私はもちろん「エンディミオン」からの後半も楽しむつもりである。
2017年10月29日日曜日
THE DILLINGER ESCAPE PLAN FINAL JAPAN TOUR 2017@渋谷Cyclone
The Dillinger Escape Planというバンド名の元ネタは私もはじめは勘違いしていたのだが、(セクシーな女スパイが隠し持っている)小さい銃のデリンジャー(Derringer)ではなくて、1930年台のアメリカの銀行強盗John Dillingerのこと。この人はFBIからは公共の敵を意味するPublic Enemy(同名のヒップホップユニットの創始者Chuck Dはここからグループ名を取った)と称されたくらいの凄腕の強盗で、義賊ということで民間にもすごく人気があったそうな。とくに逃げ際が彼の持ち味で指名手配されて多額の賞金がかけられているのに全然捕まらなかった。The Dillinger Escape Planはそんな「デリンジャーの逃亡計画」と意味。(完全に余談だが、スティーブン・キングがジョン・デリンジャーの落陽を書いた短編小説がとても面白いので興味のある人は「第四解剖室」という短編集をどうぞ。)TDEPの音楽は破天荒でスタイリッシュで、カオティックで親しみやすく私も大音量で聞きながら彼らと迫りくる警官から来るまで逃亡するような気持ち(妄想)に浸ったものだ。
さて台風が接近してまたしても荒天に見舞われる日本列島、The Dillinger Escape Plan最後の日本公演二日目に。今度のライブハウスは20週年を迎えるという老舗の渋谷サイクロン。ハロウィンで浮かれる渋谷の街は二重の意味で私のようなオタクには歩きにくいがなんとか到着。ライブハウスのハキハキとして対応も丁寧。キャパシティは300人。前売りはソールドだが、当日券で30人位入れたとのこと。(雨の中せっかく来てくれたので、ということでした。)というわけでさすがにパンパン。サイクロンはステージは一段高いところにあるものの、ほぼフロアとの隙間がない。この日は客演なしの一本勝負ということで前日以上の荒れ模様が予想され、やはり主催Realising Mediaの今西さんから怪我人ゼロでいきましょう!とアナウンス。
The Dillinger Escape Plan
期待感からか「デーリンジャー!デーリンジャー!」とコールも始まる。相変わらずちょっと焦らしてからメンバーが登場。この日も圧縮が半端なかった。死ぬとか思ったけどそれどころではなかった。死んでいる場合ではない。1曲めは前日から異なり5thアルバム「One of Us is Killer」から冒頭「Prancer」。そこから順当に「When I Lost My Bet」。からの4th「Ire Works」からの「MIlk Lizard」なのでもう0から100に一気に加速したフロアが沸点を超えて煮え立っている。ステージが近い、狭いライブハウスなのでサーフの数が半端ない。後ろから飛び出して人の頭の上を転がって、ステージ前面に行くわけだけど、Cyclamenのメンバーお二人に加えてボーカルのGregが太い腕でぐっとサーファーを捕まえて押し出していく、またはステージに上げると、華麗にさばいていく。私はと言うとぎゅうぎゅうで手を挙げると下げる隙間もない、のでほぼ腕をうえに振り上げっぱなし。ダイバーの何かが顔面にぶち当たり、早々にコンタクトレンズが脱落したのでほぼ半目でステージを見上げることに。Gregは相変わらずライブハウスの中を縱橫に動き回る。アンプの上、人の上どころか最終的には人の頭の上を通って、はるかステージ後方2回のPAスペースの作にぶら下がっっていた。(その間ももちろん叫ぶし、歌う。)Gregはとにかく終始笑顔で楽しそうだった。ちなみに客もほとんど笑顔。いかついお兄さんもすごい笑顔。唯一のオリジナルメンバーであるBenは笑顔は見せないのだけどやっぱり動き回りアンプの上に登り、ジャンプし、最終的にはなぜか客の頭の上に直立でとどまり、ギターを引いていた。天草四郎ですら水の上を歩いたのに、なぜか微動だにしないBen。どういう仕組なのでしょうか。Gregと二人で1本のマイクにシャウトを決めたり、とても良いコンビ。
演奏は相変わらず劇的にタイトで「Prancer」でもその魅力を発揮していたが、休符の使い方がとんでもなく大胆で外すと露骨にミスが目立ってしまうところをきっちり決めていく。音質は流石に前日のLiquidroomに譲るものの、この日はベースの出音がでかくて個人的には荒々しい迫力が良かった。セットリストも抑えるところは抑えつつ、やや変更してきたイメージ。看板の二人以外のメンバーも良い感じにはっちゃけていた。(もう一人のギタリストKevin Antreassianの黒いボディに蛍光緑のピックアップのギター存在感あったな〜〜。Vigierというブランドみたい。)とにかく正確性の上に快楽がある、というドグマのもとに荒々しくもかっちりとした楽曲を披露していく。メンバーは各々暴れて目配せとかもしてないようだが、よくまああんなにきっちり合っていくものだ。パワーバイオレンスとは全く異なる極端性、つまり速い遅いの二元論に加えて、ジャズを意識させるアンビエントパート、特にコアな音楽界隈では軟弱と切り捨てられかねないわかりやすいメロディという別次元を加えた多次元宇宙的な世界観を高尚さ、そしてメタルっぽさと明確に切り離したハードコアのフォーマットで繰り出していく。まさに不可能への挑戦、無限を計算し続ける艱難辛苦の果にある、お手軽に音楽が作れる現代における時代の徒花めいた非効率的な音楽にこそ、そんな複雑さ、考え抜かれた思考と試行錯誤の先に、その先にこそThe Dillinger Escape Planにしか出せない、頭のおかしいくらい複雑な曲なのに一体感のある音楽がある。音源で聞く正確性、そしてフロアとステージの高さをなくす親しみのあるステージング。”ヤバさ”が取り上げられがちだが、要するに演者と客という両者の柵を取っ払う、演者からの観客に対する接近こそが一体感の秘密かもしれない。盛り上げたいならまず自分からを地で行くステージングだ。客が拳を振り上げ、一緒にメロディを歌う(叫ぶ)というフロアの状態は、危険なピットができるハードコアとは異なり、日本のkamomekamomeのライブにちょっと似ているなと思った。インタビューによるとボーカルのGregは思い注意欠陥障害(ADHDのこと)でステージに上ると頭が真っ白になるそうなのだけど、この過激なステージングは彼にとっては世界の付き合い方の一つなのだろうか。
Gregから「今回のツアーで最高のライブだ」とアナウンスがあり、アンコールでは初日にやらなかった「Mullent Burden」を披露。爆速。その後1stからの「43%Burnt」で〆。やはり1st「Calculating Infinity」の曲はまだニュースクール的なハードコアリフがあってめちゃかっこいい。かなりゴリッゴリきて気持ちよい。
終わってみると私は本当に汚い話で申し訳ないのですがパンツまで汗びっしょり。おそらく重篤な怪我人は出なかったのではなかろうか。フロアに明かりがつくとみんな名残惜しそうにそれでも笑顔だったのが印象的だった。
主催の今西さんに握手して、また渋谷の浮かれた人混みをビショビショで帰ったのですが、今ならマスコアパンチが打てそうないい気分だったので問題なし。
バスから降りて家まで歩いている時に急にバンドが解散したらあの素晴らしい楽曲群をもう誰も演奏しないのかと思って悲しくなり泣けてくる。(私は愚かなので人が死ぬときもその後に残される知識や本とかのことを考えないとその喪失が実感できない。)私がもうずっと大好きだったバンドがなくなってしまうのである。そうしたら音源を聴いて一人で拳を突き上げようと思う。彼らの曲は永遠だ。この日は本当に破天荒なデリンジャー・ギャングたちが運転する車の後部座席に乗って派手で荒々しくも華麗な逃走劇を楽しんでいるような感じだった。当局の銃弾が飛び交う中、猛スピードで車がバウンドしていく。ばかみたいなスピードで窓の外を風景が流れていく。彼らの笑顔がすぐ先にあって、おこがましくも私もその悪事に一枚噛んでいるような背徳感のある楽しさがそこにあった。そうして時間が来ると、彼らは私を真っ黒いフォードから下ろし、またあっという間にまた駆け抜けていった。そうしてきっともう今年の終わりにはこの世界からあっという間に、そして華麗に脱出していくのだろう。ありがとう。The Dillinger Escape Plan。
主催のRealising Mediaの皆様本当にありがとうございました。
さて台風が接近してまたしても荒天に見舞われる日本列島、The Dillinger Escape Plan最後の日本公演二日目に。今度のライブハウスは20週年を迎えるという老舗の渋谷サイクロン。ハロウィンで浮かれる渋谷の街は二重の意味で私のようなオタクには歩きにくいがなんとか到着。ライブハウスのハキハキとして対応も丁寧。キャパシティは300人。前売りはソールドだが、当日券で30人位入れたとのこと。(雨の中せっかく来てくれたので、ということでした。)というわけでさすがにパンパン。サイクロンはステージは一段高いところにあるものの、ほぼフロアとの隙間がない。この日は客演なしの一本勝負ということで前日以上の荒れ模様が予想され、やはり主催Realising Mediaの今西さんから怪我人ゼロでいきましょう!とアナウンス。
The Dillinger Escape Plan
期待感からか「デーリンジャー!デーリンジャー!」とコールも始まる。相変わらずちょっと焦らしてからメンバーが登場。この日も圧縮が半端なかった。死ぬとか思ったけどそれどころではなかった。死んでいる場合ではない。1曲めは前日から異なり5thアルバム「One of Us is Killer」から冒頭「Prancer」。そこから順当に「When I Lost My Bet」。からの4th「Ire Works」からの「MIlk Lizard」なのでもう0から100に一気に加速したフロアが沸点を超えて煮え立っている。ステージが近い、狭いライブハウスなのでサーフの数が半端ない。後ろから飛び出して人の頭の上を転がって、ステージ前面に行くわけだけど、Cyclamenのメンバーお二人に加えてボーカルのGregが太い腕でぐっとサーファーを捕まえて押し出していく、またはステージに上げると、華麗にさばいていく。私はと言うとぎゅうぎゅうで手を挙げると下げる隙間もない、のでほぼ腕をうえに振り上げっぱなし。ダイバーの何かが顔面にぶち当たり、早々にコンタクトレンズが脱落したのでほぼ半目でステージを見上げることに。Gregは相変わらずライブハウスの中を縱橫に動き回る。アンプの上、人の上どころか最終的には人の頭の上を通って、はるかステージ後方2回のPAスペースの作にぶら下がっっていた。(その間ももちろん叫ぶし、歌う。)Gregはとにかく終始笑顔で楽しそうだった。ちなみに客もほとんど笑顔。いかついお兄さんもすごい笑顔。唯一のオリジナルメンバーであるBenは笑顔は見せないのだけどやっぱり動き回りアンプの上に登り、ジャンプし、最終的にはなぜか客の頭の上に直立でとどまり、ギターを引いていた。天草四郎ですら水の上を歩いたのに、なぜか微動だにしないBen。どういう仕組なのでしょうか。Gregと二人で1本のマイクにシャウトを決めたり、とても良いコンビ。
演奏は相変わらず劇的にタイトで「Prancer」でもその魅力を発揮していたが、休符の使い方がとんでもなく大胆で外すと露骨にミスが目立ってしまうところをきっちり決めていく。音質は流石に前日のLiquidroomに譲るものの、この日はベースの出音がでかくて個人的には荒々しい迫力が良かった。セットリストも抑えるところは抑えつつ、やや変更してきたイメージ。看板の二人以外のメンバーも良い感じにはっちゃけていた。(もう一人のギタリストKevin Antreassianの黒いボディに蛍光緑のピックアップのギター存在感あったな〜〜。Vigierというブランドみたい。)とにかく正確性の上に快楽がある、というドグマのもとに荒々しくもかっちりとした楽曲を披露していく。メンバーは各々暴れて目配せとかもしてないようだが、よくまああんなにきっちり合っていくものだ。パワーバイオレンスとは全く異なる極端性、つまり速い遅いの二元論に加えて、ジャズを意識させるアンビエントパート、特にコアな音楽界隈では軟弱と切り捨てられかねないわかりやすいメロディという別次元を加えた多次元宇宙的な世界観を高尚さ、そしてメタルっぽさと明確に切り離したハードコアのフォーマットで繰り出していく。まさに不可能への挑戦、無限を計算し続ける艱難辛苦の果にある、お手軽に音楽が作れる現代における時代の徒花めいた非効率的な音楽にこそ、そんな複雑さ、考え抜かれた思考と試行錯誤の先に、その先にこそThe Dillinger Escape Planにしか出せない、頭のおかしいくらい複雑な曲なのに一体感のある音楽がある。音源で聞く正確性、そしてフロアとステージの高さをなくす親しみのあるステージング。”ヤバさ”が取り上げられがちだが、要するに演者と客という両者の柵を取っ払う、演者からの観客に対する接近こそが一体感の秘密かもしれない。盛り上げたいならまず自分からを地で行くステージングだ。客が拳を振り上げ、一緒にメロディを歌う(叫ぶ)というフロアの状態は、危険なピットができるハードコアとは異なり、日本のkamomekamomeのライブにちょっと似ているなと思った。インタビューによるとボーカルのGregは思い注意欠陥障害(ADHDのこと)でステージに上ると頭が真っ白になるそうなのだけど、この過激なステージングは彼にとっては世界の付き合い方の一つなのだろうか。
Gregから「今回のツアーで最高のライブだ」とアナウンスがあり、アンコールでは初日にやらなかった「Mullent Burden」を披露。爆速。その後1stからの「43%Burnt」で〆。やはり1st「Calculating Infinity」の曲はまだニュースクール的なハードコアリフがあってめちゃかっこいい。かなりゴリッゴリきて気持ちよい。
終わってみると私は本当に汚い話で申し訳ないのですがパンツまで汗びっしょり。おそらく重篤な怪我人は出なかったのではなかろうか。フロアに明かりがつくとみんな名残惜しそうにそれでも笑顔だったのが印象的だった。
主催の今西さんに握手して、また渋谷の浮かれた人混みをビショビショで帰ったのですが、今ならマスコアパンチが打てそうないい気分だったので問題なし。
バスから降りて家まで歩いている時に急にバンドが解散したらあの素晴らしい楽曲群をもう誰も演奏しないのかと思って悲しくなり泣けてくる。(私は愚かなので人が死ぬときもその後に残される知識や本とかのことを考えないとその喪失が実感できない。)私がもうずっと大好きだったバンドがなくなってしまうのである。そうしたら音源を聴いて一人で拳を突き上げようと思う。彼らの曲は永遠だ。この日は本当に破天荒なデリンジャー・ギャングたちが運転する車の後部座席に乗って派手で荒々しくも華麗な逃走劇を楽しんでいるような感じだった。当局の銃弾が飛び交う中、猛スピードで車がバウンドしていく。ばかみたいなスピードで窓の外を風景が流れていく。彼らの笑顔がすぐ先にあって、おこがましくも私もその悪事に一枚噛んでいるような背徳感のある楽しさがそこにあった。そうして時間が来ると、彼らは私を真っ黒いフォードから下ろし、またあっという間にまた駆け抜けていった。そうしてきっともう今年の終わりにはこの世界からあっという間に、そして華麗に脱出していくのだろう。ありがとう。The Dillinger Escape Plan。
主催のRealising Mediaの皆様本当にありがとうございました。
The Dillinger Escape Plan Final Japan Tour 2017@恵比寿Liquidroom
音楽好きなら自分の既存の世界観をぶち壊して、興味を次の次元に持ち上げてくれたアルバムというのがかならずあると思う。手にとって聴いたときは「なんじゃこら??」となって全然わからないのだが、しばらく聴いているとこんな世界があったのか!!と虜になる。そしてそのアルバムがゲートウェイになってまた様々な音楽を掘っていく。私は中学生の時に買ったnin inch nails「The Fragile」、それから大学生の時に買ったThe Dillinger Escape Planの「Miss Machine」がそれだ。出会ってからそれぞれ15年以上、10年以上たっても未だによく聴く私の音楽の救世主だ。
そんなThe Dillinger Escape Planは今年の年末での解散を発表している。多くのベテランバンドをディスるつもりは毛頭ないが、長いキャリアでなかなか初期の名作群を超越しながら新作を出すというのはとても難しい。ジャンルは違うが「シャッター・アイランド」などで有名なアメリカの作家デニス・ルヘインもそういう趣旨で人気シリーズに幕を下ろしていた。だから全盛期で解散、というのはなんとも潔く、そして格好良い、気持ちはわかる。そんな彼らが解散直前に日本に来ることになった。TDEPは来日経験は何回かあるのだが私は見たことがないので今回が初めての機会ということで2つの公演のチケットをとった。
招聘しているのはRealising Mediaで過去に色々な海外のバンドの来日公演を手がけ、なんと招聘率は100%だ。これは海外のライブ行く人なら結構驚異的な数値だとわかると思う。大きな会社でなくDIYでやっているところでなんせ連絡先が個人的っぽいGmailなんだよね、本当すごいです。
1日目は恵比寿Liquidroomだ。収容人数は900人と大きめだが、ほぼ前売りは売り切れ寸前だったようだ。私は初めて行くライブハウスだがきれいで、それなりに大きさのあるトイレが有るのは良いな〜と思った。
前の方で見るから物販は終演後にしようと思ったのだが、これが間違いで終演後には私の着れるサイズはほとんど売り切れておった。前売りもあったのでこれを使っとくべきだったと後悔。
Cyclamen
この日は対バンがあってそれが日本(結成はイギリスでメンバーのうち一人は半分タイに住んでいるんだけど)のCyclamen。主催者の今西さんのバンドである。
2日間のライブの段取りも完璧だったと思うし、そんな情熱が柔らかい言葉にでるMCを披露し、ライブがスタート。ドラムにギターが二人、そしてボーカルの4人組。(少なくとも曲によっては)ベースの音を同期させていたと思う。
いわゆるDjentと呼ばれるカテゴリーの属するバンドだと思うが、非常にプログレッシブでテクニカルなメタルを演奏する。まずは変拍子を含めた曲展開の複雑さ、それを支えるタッピングを始めとする(もっと他にもすごいテクがあると思うんだけど)テクニック。ボーカルもウィスパー、裏声からスクリーム、シャウトなどを多彩にこなしていく。歌詞はおそらく日本語でハード一辺倒ではなく、(最近発表された女性ボーカルを大胆にフィーチャーした曲はとても格好良い)アンビエントなパートの導入や、キャッチーなメロディーを取り入れたりしている。ハードコア感は希薄だが、こういった要素は紛れもなくTDEPからの影響も大きいはず。結構な曲数をポンポンこなしていくが終わってみると30分しか立ってない。プログレッシブになると曲が長くなりがちだが、Cyclamenは多分非常にコンパクトに纏めることにこだわりがあるみたいで、結果私にような門外漢でも楽しめた。終盤の方でやった曲間でゆったりとしたテンポ、音になる曲が個人的には良かった。タッピングってうるさいフォーマットでしか聴いたことがないので、ああいうゆったりとしたクリーンでもかっこいいというのは驚きだった。
The Dillinger Escape Plan
いよいよ本命の登場となる。私は特に意識せずに空いているところを探してステージの下手、ギタリストのBen側に。とにかく事前に主催者から相当激しいことになるから気をつけてくれとアナウンスされ、twitterでは運動会などと揶揄されている。ちなみにこの日はいかつい黒人のセキュリティがステージ全面に控えていた。前は相当きついことになるだろうが、やはりこれは前に行かねば。サウンドチェックの人が出てきたりしてなかなか始まらない。ライブが始まる前はいつも軽い緊張感があるのだが、この日は速く始めるか、もしくはいっそ中止になったからとアナウンスしてほしいくらい、期待感で心臓に負担がかかる始末。ロン毛の細身のスタッフ(ライブ中は写真を取っていた)がバンド準備OKという意味のライトをチカチカやった瞬間は一生忘れられないだろう。脳から出たアドレナリンが一瞬で体に充填されていくあの感じ。ステージが暗くなり、メンバーが登場。すかさず最新作にして最終作の「Dissociation」から冒頭の「Limerent Death」。開放された真空に空気が殺到するようにステージに客が詰めかけ圧縮される。私はここから終演後までほぼ頭が真っ白になった。ぎゅうぎゅうどころの騒ぎでない乗車率300%オーバーの中飛んだり跳ねたりの運動会である。
TDEPはとにかくハードコアにしては楽曲が複雑すぎるが、それでもどこまで言ってもハードコアでしかないというバンドで、明らかに演奏がタイトである。ライブハウスの非常に優良な音環境もあって音質はほぼ完璧だ。複雑な曲がいっぺんの狂いもない(ように思える)状態で再現される。一見盛り上がりとは無縁の様相が想像されがちだが、全く逆なのがとにかく面白い。バンドのメンバーは客に劣らず動き回る。アンプの上に登る、その上で歌うもしくは演奏する、飛び降りると。こんなに動きつつも演奏は劇的にタイト。
クラウドサーファーが大挙として発生し、ステージ全面に落ちては捌かれていく。何人かはステージの到達してからのダイブを披露していた(ように思う)。Gregもアンプの上から何メートルしたかにめがけてダイブをかまし、サーフしながらも途切れることなく歌い続けステージに復帰する荒業をやってのけていた。
私本当メロディアスなパートがある曲ほとんど歌える事に気がついた。(なんちゃって英語だけど。)ということですげー歌ってしまった。本当すごい音痴なので周りにいた人には申し訳ない気持ちがあるんだけど、多分みんな歌ってたから大丈夫。Milk Lizardとか大合唱でした。
新旧アルバムからかなりまんべんなくプレイしていたように思う。みんなもそうだと思うけど「Setting Fire to the Sleeping Giant」は最近のセットリストにはあまりないようだったのでまったくもって心躍るサプライズだった。
最終的にはドラムのBilly Rymerがシンバルを持ったまま客席にダイブし、サーフしながらシンバルを叩いていた。お祭りか。
TDEPはマスコアと称されることもあって、複雑な曲展開を持っており、激しいパートは激しく、ジャズの要素を取り入れたアンビエントパートに、一転メロディアスなパートも持っている。それをめまぐるしい速度で1曲の中で演奏していく。だからカオティックと呼ばれるわけなんだけど、じつは非常に整合性の取れたかっちりとした世界で異常な技術に支えられた演奏力でカオスを再現している(時点で正確には混沌とは言えないわけなんだけど)バンド。この日思ったのはとにかくリアルであること。弦楽器の音は非常にバリエーションが有るのだけど、どれもわかりやすい重低音などに偏向していない。どれも楽器のもとの音が生き残っている感じ。ジャギジャギしているところは非常に生々しい。メチャクチャな速さでうるさいパートを演奏していても、ギターの音は程よく中音がきいた生々しい音だったりする。これはすごい。ハードコア(のある分野の特性)はどんどんタフになっていくけど、TDEPはそうでない。本当にタフならある意味それを証明する必要はないから、いわばタフであるという物語になってくるのがハードコアの一側面である(実際にはタフでないと言っているわけではないです。)としたら、TDEPはその運動には寄与していない。じゃあハードコアじゃないじゃんって人がいたらこのステージを見てくれよ!と思う。(無理を承知で。)別に派手に人が暴れるからハードコアで、だから(ボーカルが人の頭の上を歩いて行く動画などで注目されがちだけど)TDEPはハードコアバンドだというのではない。それ(ライブ)は結果です。そもそも今MInor Threat聴いて音がしょぼいのでハードコアじゃないという人はいないのではないでしょうか。つまり音や曲(だけ)でハードコアはできてないってことが言いたい。向上心があるのが(現状を変えたいと思うのが)ハードコアだと私は思うんですけど、TDEPは複雑な曲を演奏するけど、音自体は非常に飾りっ気のないもので声もメロディも別に特別な飛び道具を使っているわけではない。手元にあるものを研ぎすませて限界に挑戦していくのがこのバンドで、だからどこまで言っても”リアル”なハードコアなのだ。一体無限を計算しきれるわけはないだろう?1stからこのバンドの精神性は一貫していますね。メンバーはタイトさが高尚さを持たないように腐心して(天然かもしれない)、ステージ上でもそのように振る舞う、そして結果一体感のあるライブになるのでは。
ぼろぼろになって物販に行くとほとんどSかMが売り切れで仕方なくパーカーのMだけ購入。頭の中がお花畑状態で帰宅。
恵比寿の駅に私より年下のおしゃれなスーツきた男性がモデルみたいな女性と歩いていてこんな世界あるのか!と思いながら帰宅。
2017年10月22日日曜日
Jlin/Black Origami
アメリカ合衆国はインディアナ州ゲイリーの女性プロデューサーの2ndアルバム。
2017年にMike ParadinasのPlanet Muからリリースされた。
ジューク/フットワークというテクノのジャンルがあり、私は日本のCRZKNYというアーティストからたまたま知ったのだが、それに属するのが彼女。2015年リリースの1stアルバムがWIREというイギリスの雑誌で年間ベストに選出されたり、日本盤が出たりとかなり注目されている人のようだ。たまたま目にしたアルバムのジャケットが良かったので購入した次第。ジューク/フットワークはシカゴで生まれたジャンルらしく、その中でもRP Booという人がとても有名、このJlinという人はそのBooが取りまとめるD'Dynamicsという集団に属しているらしい。(クルーってやつらしい。)
ジューク/フットワークは足技を中心とするダンスとの切り離すことのできない関連性(ダンスバトルの伴奏としての役割があるそうな)がある複雑で速い(一拍三連のリズムが特徴らしい)テクノ音楽。よく「ゲットー」という言葉がでてくる。
なんせCRZKNYしか聞いたことが無いから、彼の作り出す音楽と比較するしかないんだけどCRZKNYの目下の最新作「Meridian」とは結構音楽性は異なるな〜という印象。
結構色々要素はあるのだが、まずJlinは結構音の数が多い。ほぼほぼビートしかないような音楽で、つまりわかりやすいメロディラインがほぼ皆無なので、そういった意味では低音が高調された無骨な音楽のだが、Jlinの場合はそんな中でも結構音の数が多い。細かく多い感じ。金属質の小さい物体転がっていくような、速くて軽いビートはなんとも心地よい。(バスドラムの)キックがあまり多用されていない、というか主眼に置かれていないのもこの手のジャンルでは珍しい(のかな?)。これはようするにフットワークというジャンルゆえだろうと思う。面白いのはミニマルでありながらも結構展開があって曲が動いていく。これもやはりダンスミュージックゆえなのではと思う。展開があるのでダンサーにとっては縛りでもあり、新しい動きのきっかけにもなるだろうからこういった曲を使えば、きっと面白いダンスバトルになるだろうと思う。
もう一つの特徴は声のサンプリング。とにかく不気味なくらいサンプリングを重ねてくる。子供がふざけてサンプラーを叩いているみたいな無邪気さなのだが、結果的に声から感情が失われていき、無機質かつ不気味になってくるのが面白い。
全体的にはなんとも言えない異国的な情緒にあふれている。表題曲なんてちょっと和風なテイストがあるかな?と思ったけど全体的には、金属質なビートが特にもっとアフリカンだ。孫引きになってしまうのだがこの記事によると「フットワークのルーツはアフリカにある」とおっしゃっているようでなるほどな〜という感じ。アフリカという広大な大地を暗く、冷たくパッケージした感じ。こういう書き方だと悪いイメージだけど、きっとそうじゃない。ただ情熱を前出しすれば愛情が大きいわけではないと思う。
暗くて冷徹なのだが、忙しないビートが癖になる感じ。例えばハードかつミニマルなテクノとは部分部分共通項があっても、仕上がりは結構別物。ちょっとダルい感じを演出するのは最近の音楽という感じ。
2017年にMike ParadinasのPlanet Muからリリースされた。
ジューク/フットワークというテクノのジャンルがあり、私は日本のCRZKNYというアーティストからたまたま知ったのだが、それに属するのが彼女。2015年リリースの1stアルバムがWIREというイギリスの雑誌で年間ベストに選出されたり、日本盤が出たりとかなり注目されている人のようだ。たまたま目にしたアルバムのジャケットが良かったので購入した次第。ジューク/フットワークはシカゴで生まれたジャンルらしく、その中でもRP Booという人がとても有名、このJlinという人はそのBooが取りまとめるD'Dynamicsという集団に属しているらしい。(クルーってやつらしい。)
ジューク/フットワークは足技を中心とするダンスとの切り離すことのできない関連性(ダンスバトルの伴奏としての役割があるそうな)がある複雑で速い(一拍三連のリズムが特徴らしい)テクノ音楽。よく「ゲットー」という言葉がでてくる。
なんせCRZKNYしか聞いたことが無いから、彼の作り出す音楽と比較するしかないんだけどCRZKNYの目下の最新作「Meridian」とは結構音楽性は異なるな〜という印象。
結構色々要素はあるのだが、まずJlinは結構音の数が多い。ほぼほぼビートしかないような音楽で、つまりわかりやすいメロディラインがほぼ皆無なので、そういった意味では低音が高調された無骨な音楽のだが、Jlinの場合はそんな中でも結構音の数が多い。細かく多い感じ。金属質の小さい物体転がっていくような、速くて軽いビートはなんとも心地よい。(バスドラムの)キックがあまり多用されていない、というか主眼に置かれていないのもこの手のジャンルでは珍しい(のかな?)。これはようするにフットワークというジャンルゆえだろうと思う。面白いのはミニマルでありながらも結構展開があって曲が動いていく。これもやはりダンスミュージックゆえなのではと思う。展開があるのでダンサーにとっては縛りでもあり、新しい動きのきっかけにもなるだろうからこういった曲を使えば、きっと面白いダンスバトルになるだろうと思う。
もう一つの特徴は声のサンプリング。とにかく不気味なくらいサンプリングを重ねてくる。子供がふざけてサンプラーを叩いているみたいな無邪気さなのだが、結果的に声から感情が失われていき、無機質かつ不気味になってくるのが面白い。
全体的にはなんとも言えない異国的な情緒にあふれている。表題曲なんてちょっと和風なテイストがあるかな?と思ったけど全体的には、金属質なビートが特にもっとアフリカンだ。孫引きになってしまうのだがこの記事によると「フットワークのルーツはアフリカにある」とおっしゃっているようでなるほどな〜という感じ。アフリカという広大な大地を暗く、冷たくパッケージした感じ。こういう書き方だと悪いイメージだけど、きっとそうじゃない。ただ情熱を前出しすれば愛情が大きいわけではないと思う。
暗くて冷徹なのだが、忙しないビートが癖になる感じ。例えばハードかつミニマルなテクノとは部分部分共通項があっても、仕上がりは結構別物。ちょっとダルい感じを演出するのは最近の音楽という感じ。
2017年10月21日土曜日
デニス・リーマン/囚人同盟
アメリカの作家による長編小説。
1998年に出版された小説で、原題は「The Getback of Mother Superior」。
Mother Superiorとは聞き慣れない言葉だが、これは邦訳すると「女子修道院長」となるそうだ。
これはいわゆる塀の中、つまり監獄の中を舞台にした小説でそういった意味では、ピカレスク小説ということができる。
この手のジャンルでは”リアル”であること(というよりは”リアルらしく見えること”)が、その小説の中身を保証する指針というか、もっというとハクになるわけだけど、この小説に関しては著者のデニス・リーマンはの輝かしい経歴でとんでもないハクがついている。
というのもリーマンその人は武装強盗などで都合53年の実刑判決がでているからだ。執筆当時は保釈の予定もなかったので当然この本は塀の中で書かれたものになるわけだ。
犯罪者が書いた小説というと、私が好きなジェイムズ・エルロイだか彼は投獄歴があるがプロの犯罪者ではなかったはずだ。この間呼んだエドワード・バンカーはれっきとしたプロの犯罪者だった。
デニス・リーマンはあとがきを読むにプロの犯罪者かは議論の余地があるが、少なくとも重大な犯罪歴があるというのは間違いない。つまりこの本は重犯歴のある犯罪者が書いたリアルな犯罪小説だったことだ。
俺ことフラット・ストアはワシントン州タコマ市にあるマクニール島刑務所で刑期を務める元犯罪者だ。罪状は詐欺など。同じ牢屋には他にも個性的な面々が揃っている。
刑務官を除けば犯罪者しかいない刑務所で五体満足で生き残るのは難しい。なんてったって殺しも日常茶飯事だ。
そして刑務所長一派は立場を利用して私腹を肥やすことしか考えていない。
俺ことフラット・ストアも仲間たちもそんな世界で更生とは無縁な生き方をして、出所の日を待ちわびている。そんな房に変わった新入りが入ることになった。ガッシリとした体躯、ハンサムな顔立ち、知性を伺わせる立ち居振る舞い、軽やかな弁舌、全てが刑務所に似つかわしくないこの男は当初刑務所が派遣したスパイかと疑われたが、どうも違うらしい。マザーとあだ名されたこの男には何かしらの計画があるらしい。フラット・ストアたち同房の仲間はマザーの計画に巻き込まれていくことになる。
およそ刑務所で計画といったら脱獄計画に間違いない。
名作と名高い「ショーシャンクの空に」(原題は「塀の中のリタ・ヘイワース」というスティーブン・キングの小説だ)もそうだったし、「プリズン・ブレイク」もそうだった。
ところがこの話はそうではない。もう一度原題に戻るけど、Getbackとは復讐という意味もある。だから邦題は「女子修道院長の復讐」ってことになる。
この女子修道院長というのは謎の登場人物、通称マザーのことだ。このマザーという男が俺含め犯罪者の面々を彼の復讐に巻き込んでいくのだ。これがすごく面白い。
始めに言ってしまうとこの本には一つ短所があってそれは長いってことなんだな。なんせ著者は刑務所に入っているから時間はすごくあるのでそれもあってか結構長い小説になっている。600ページあって、無駄なシーンが多いわけではないけど、結果的に前半のテンポがやや悪くなっている感は否めないと思う。
ただしそれ以外は本当に面白い。
幾つか理由がある。(というか私にもある程度説明できると思う。)
まず一つ、登場人物が面白い。
全員犯罪者でそれもあまり学がない(マザーを除くと一人だけ例外がいる)低所得者、低学歴という犯罪者の累計のような人が登場人物の大半である。
シンナーだったりギャンブルだったりに中毒になっている奴らもいる。
ルールがないのが怖いのではなくて、常人には理解できないルールが怖いのだ。
そういった意味では一件理屈の合わないルールで動く囚人たちは魅力的で、恐ろしい(恐ろしいゆえに魅力的だ。)
主人公サイドの犯罪者に関してははっきり明言されていないが、おそらく殺人者はいないはずだから読者が嫌悪感をいだきにくいというのもある。(これは人によるだろうが。)
そしてもう一つは世界が面白い。
この話は殆どが塀の中で進行する。
刑務所というのは(それもアメリカの)常人には理解できない場所だ。
登場人物同様ここも特別ルールで動いている。
ジョジョの奇妙な冒険ストーン・オーシャンを読んだことのある人なら刑務所内の貸し借りの厳格さを知っているだろうが、あんなルールが厳格にある。
タバコが通貨のように扱われ、男色行為が存在し、ルールを破ったやつは死ぬことになる。
刑務所内で殺人なんて馬鹿な、と思う人もいるかもしれなし、今はどうだかわからないが、きっと昔は当たり前のようにあったのだろう。
犯罪者が死んで誰が気にするのだ?
刑務所の中ではもっと暴力がわかりやすく支配している。外から見たら馬鹿らしいが、命がけで虚勢を張らないと行きていけない世界なのだ。
ここは更生する場所ではなくゴミ溜めであって、刑務官はゴミが溢れないように檻の外をうろついては警棒の一撃をくれるくらいなのだ。
ただしなかには魅力的な刑務官もいるのが魅力的で、ステレオタイプでなくこの小説が面白いところなのだ。
デニス・リーマンにとってはこの異様な世界が彼の家であって、世界なのだ。
考えてみてほしい、大の男が6人で一つの監房に入れられ、用を足すにも全員の目の前でだ。最初っからまともな世界とは全く異なる。
それから話の筋が面白い。
異様な世界で異様な男たちが奮闘する話なのだが、構図的にはこうだ。
マザー率いる社会の底辺が、そんな彼らをカモにする上層構造と対決する。
びっくりすることに勧善懲悪の筋になっていて、核になっているのが「復讐」である。
忠臣蔵を始め一体日本人というやつは復讐譚が好きだが、巌窟王を引き合いに出すまでもなく外国に住む人々もそうらしい。
エドワード・バンカーは悪辣な人間が悪辣なことをするというアタリマエのことを書いたが、
リーマンは違う。塀の中で無限と思われる時間(繰り返すが懲役53年)の中で育まれた一種の夢みたいなものを真っ白いページに書きつけたのだ。
いわばファンタジーなわけだが、ゴミみたいな奴らが集まり、ちょっとずつ変わりながら、悪を打ち倒すとなればこれはもう人々が大好きな物語である。
物語の類型というか、基本的にバリエーションなんてこれしかないというくらいの、いわば物語そのものの核である。
落ちこぼれがラグビーとか野球やる話、すきでしょ?
私はそういうの全然好きじゃなかったけどこの「囚人同盟」は面白い。
特に後半の所長とのやり取りはまさに手に汗握る。
またもやジョジョに例えるなら、ジョジョリオン冒頭から引用して「呪いを解」く物語でもある。
犯罪者に生まれ、犯罪者にしかなれなかった者たちが、身に染み付いた悪という呪いを自力で解くのがこの物語なのだ。熱くないわけがない。そして同時に優しい物語でもある。
なるほど有名になるにはあまりに粗野で、あまりに汚すぎる。
リーマンはきっと素直な人で、もしくは非常に皮肉な諧謔のある人で囚人という立場を存分に利用して物語を綴った。
物語自体は典型的だが、結果非常にアクのある個性の強い物語になっていることは確かだ。
ただし、おためごかしが鼻につく人だっているはずだ。
あるいは悪という概念(仮想の、本質ではない)に惹かれる人もいるかも知れない。
ひねくれた自己評価の低い人間なら、ありがちな成功譚にはたとえフィクションでもつばを吐きかけるだろう。
しかしこの本は違うかもしれない。
「囚人同盟」という本はそんな一部の人に深く刺さるかもしれない。
心当たりがある人は是非読んでみていただきたい。非常におすすめ!
1998年に出版された小説で、原題は「The Getback of Mother Superior」。
Mother Superiorとは聞き慣れない言葉だが、これは邦訳すると「女子修道院長」となるそうだ。
これはいわゆる塀の中、つまり監獄の中を舞台にした小説でそういった意味では、ピカレスク小説ということができる。
この手のジャンルでは”リアル”であること(というよりは”リアルらしく見えること”)が、その小説の中身を保証する指針というか、もっというとハクになるわけだけど、この小説に関しては著者のデニス・リーマンはの輝かしい経歴でとんでもないハクがついている。
というのもリーマンその人は武装強盗などで都合53年の実刑判決がでているからだ。執筆当時は保釈の予定もなかったので当然この本は塀の中で書かれたものになるわけだ。
犯罪者が書いた小説というと、私が好きなジェイムズ・エルロイだか彼は投獄歴があるがプロの犯罪者ではなかったはずだ。この間呼んだエドワード・バンカーはれっきとしたプロの犯罪者だった。
デニス・リーマンはあとがきを読むにプロの犯罪者かは議論の余地があるが、少なくとも重大な犯罪歴があるというのは間違いない。つまりこの本は重犯歴のある犯罪者が書いたリアルな犯罪小説だったことだ。
俺ことフラット・ストアはワシントン州タコマ市にあるマクニール島刑務所で刑期を務める元犯罪者だ。罪状は詐欺など。同じ牢屋には他にも個性的な面々が揃っている。
刑務官を除けば犯罪者しかいない刑務所で五体満足で生き残るのは難しい。なんてったって殺しも日常茶飯事だ。
そして刑務所長一派は立場を利用して私腹を肥やすことしか考えていない。
俺ことフラット・ストアも仲間たちもそんな世界で更生とは無縁な生き方をして、出所の日を待ちわびている。そんな房に変わった新入りが入ることになった。ガッシリとした体躯、ハンサムな顔立ち、知性を伺わせる立ち居振る舞い、軽やかな弁舌、全てが刑務所に似つかわしくないこの男は当初刑務所が派遣したスパイかと疑われたが、どうも違うらしい。マザーとあだ名されたこの男には何かしらの計画があるらしい。フラット・ストアたち同房の仲間はマザーの計画に巻き込まれていくことになる。
およそ刑務所で計画といったら脱獄計画に間違いない。
名作と名高い「ショーシャンクの空に」(原題は「塀の中のリタ・ヘイワース」というスティーブン・キングの小説だ)もそうだったし、「プリズン・ブレイク」もそうだった。
ところがこの話はそうではない。もう一度原題に戻るけど、Getbackとは復讐という意味もある。だから邦題は「女子修道院長の復讐」ってことになる。
この女子修道院長というのは謎の登場人物、通称マザーのことだ。このマザーという男が俺含め犯罪者の面々を彼の復讐に巻き込んでいくのだ。これがすごく面白い。
始めに言ってしまうとこの本には一つ短所があってそれは長いってことなんだな。なんせ著者は刑務所に入っているから時間はすごくあるのでそれもあってか結構長い小説になっている。600ページあって、無駄なシーンが多いわけではないけど、結果的に前半のテンポがやや悪くなっている感は否めないと思う。
ただしそれ以外は本当に面白い。
幾つか理由がある。(というか私にもある程度説明できると思う。)
まず一つ、登場人物が面白い。
全員犯罪者でそれもあまり学がない(マザーを除くと一人だけ例外がいる)低所得者、低学歴という犯罪者の累計のような人が登場人物の大半である。
シンナーだったりギャンブルだったりに中毒になっている奴らもいる。
ルールがないのが怖いのではなくて、常人には理解できないルールが怖いのだ。
そういった意味では一件理屈の合わないルールで動く囚人たちは魅力的で、恐ろしい(恐ろしいゆえに魅力的だ。)
主人公サイドの犯罪者に関してははっきり明言されていないが、おそらく殺人者はいないはずだから読者が嫌悪感をいだきにくいというのもある。(これは人によるだろうが。)
そしてもう一つは世界が面白い。
この話は殆どが塀の中で進行する。
刑務所というのは(それもアメリカの)常人には理解できない場所だ。
登場人物同様ここも特別ルールで動いている。
ジョジョの奇妙な冒険ストーン・オーシャンを読んだことのある人なら刑務所内の貸し借りの厳格さを知っているだろうが、あんなルールが厳格にある。
タバコが通貨のように扱われ、男色行為が存在し、ルールを破ったやつは死ぬことになる。
刑務所内で殺人なんて馬鹿な、と思う人もいるかもしれなし、今はどうだかわからないが、きっと昔は当たり前のようにあったのだろう。
犯罪者が死んで誰が気にするのだ?
刑務所の中ではもっと暴力がわかりやすく支配している。外から見たら馬鹿らしいが、命がけで虚勢を張らないと行きていけない世界なのだ。
ここは更生する場所ではなくゴミ溜めであって、刑務官はゴミが溢れないように檻の外をうろついては警棒の一撃をくれるくらいなのだ。
ただしなかには魅力的な刑務官もいるのが魅力的で、ステレオタイプでなくこの小説が面白いところなのだ。
デニス・リーマンにとってはこの異様な世界が彼の家であって、世界なのだ。
考えてみてほしい、大の男が6人で一つの監房に入れられ、用を足すにも全員の目の前でだ。最初っからまともな世界とは全く異なる。
それから話の筋が面白い。
異様な世界で異様な男たちが奮闘する話なのだが、構図的にはこうだ。
マザー率いる社会の底辺が、そんな彼らをカモにする上層構造と対決する。
びっくりすることに勧善懲悪の筋になっていて、核になっているのが「復讐」である。
忠臣蔵を始め一体日本人というやつは復讐譚が好きだが、巌窟王を引き合いに出すまでもなく外国に住む人々もそうらしい。
エドワード・バンカーは悪辣な人間が悪辣なことをするというアタリマエのことを書いたが、
リーマンは違う。塀の中で無限と思われる時間(繰り返すが懲役53年)の中で育まれた一種の夢みたいなものを真っ白いページに書きつけたのだ。
いわばファンタジーなわけだが、ゴミみたいな奴らが集まり、ちょっとずつ変わりながら、悪を打ち倒すとなればこれはもう人々が大好きな物語である。
物語の類型というか、基本的にバリエーションなんてこれしかないというくらいの、いわば物語そのものの核である。
落ちこぼれがラグビーとか野球やる話、すきでしょ?
私はそういうの全然好きじゃなかったけどこの「囚人同盟」は面白い。
特に後半の所長とのやり取りはまさに手に汗握る。
またもやジョジョに例えるなら、ジョジョリオン冒頭から引用して「呪いを解」く物語でもある。
犯罪者に生まれ、犯罪者にしかなれなかった者たちが、身に染み付いた悪という呪いを自力で解くのがこの物語なのだ。熱くないわけがない。そして同時に優しい物語でもある。
なるほど有名になるにはあまりに粗野で、あまりに汚すぎる。
リーマンはきっと素直な人で、もしくは非常に皮肉な諧謔のある人で囚人という立場を存分に利用して物語を綴った。
物語自体は典型的だが、結果非常にアクのある個性の強い物語になっていることは確かだ。
ただし、おためごかしが鼻につく人だっているはずだ。
あるいは悪という概念(仮想の、本質ではない)に惹かれる人もいるかも知れない。
ひねくれた自己評価の低い人間なら、ありがちな成功譚にはたとえフィクションでもつばを吐きかけるだろう。
しかしこの本は違うかもしれない。
「囚人同盟」という本はそんな一部の人に深く刺さるかもしれない。
心当たりがある人は是非読んでみていただきたい。非常におすすめ!
skillkills presents 「The Shape of Dope to Come Release Tour Final」@Club Asia
この日ありがちなことにライブがかぶっていたが、私が行ったのはこのライブ。
Zazen Boysのライブが見たいというのが第一で、Skillkillsはよく目にするものの訊いたことも見たこともないバンドなのでこれは良い機会と思ったわけ。この日はSkillkillsの新作のリリースツアーのファイナル日。
なんとか仕事を放り出して会場に当日券で文字通り潜り込むと、Zazen Boysのライブがまさに始まったところだった。
Zazen Boys
ベーシストの吉田が今年限りで脱退することがアナウンスされたが、ステージングは落ち着いたものだった。照明をほぼ全開にしたステージは明るくそしてあけっぴろげであった。
私は30を半ばなのだから、思春期に洋楽の洗礼を受けてもNumber GirlとスーパーカーはOKという謎の方程式により、よくよくNumber Girlの音楽を聞いていた。(こういう輩は多いのでは。)初めて接したときの印象が強いのは音というよりMutomaJapanでみたフロントマン向井による手書きのMVの漫画テイストだったんだが。
このZazen Boysというのは完全に周囲とは隔たった音楽を追求するバンドで、私はこの手のジャンルに詳しくないのでよくわからないが、ロックをベースにプログレやファンクやジャズなどが引き合いに出されるようだ。(要するにNumber Girlとは異なる音楽性でそれ故私は少し敬遠していた。)
複雑ってことなのだが、音源聞いても分かる通り非常に肉体的な音楽だ。楽曲全体がリズムでできているようになっていて、相当ややこしいのだが私のような音楽的な知識がない輩でも踊りたくなっちゃうような音楽だ。生で見て思うのはとにかくZazen Boysの音楽は身軽である。難解になると技術の鎧がどんどん分厚くなるが、このバンドは音をどんどん抜いていっている。結果的に難解なリズムの骨組みのみが残っている。音の数は決して多くないが、余計に間が重要になってきてそしてそれらがとにかくきっちりあってくる。ドラム一つとっても今拍子はなんだろう?ってくらいで、楽器隊がそれぞれ別に何かやっているのが、何かわからんが偶然合っちゃって曲ができているような感じすらする。めちゃくちゃ緊張感があるのだが、ユーモアを交えたゆるさ(演奏以外の)があって、高尚な音楽にならずにあくまでも楽しい音楽にとどまり続ける。私が音源で聞いている曲も一回ばらばらにして再構築しているように、もはや別の曲では?というくらいの再現度。即興性も取り入れつつ、コールアンドレスポンスを取り込んだり(「Whisky&Unbubore」という曲、途中なんとなくNumber Girlの「Eight Beater」を彷彿とさせる)、酩酊の楽しさがにじみ出るようなステージングを進めていく。ステージの後ろの方でゆらゆら体をしているのが楽しかった。次はもっと前でみたいな。
Killer-Bong
続いてはBlack Smokerの首魁Killer-Bong。見るのは2回めで前回はコントラバス奏者とのコラボレーションだったので、単独を見るのは今回が初めて。
卓の上に据えられたサンプラー(?)2台位とマイクのみ。照明は落とされているが、プロジェクターを使った強烈な光線が暗闇を線上に切り裂いていく。この日のVJはENDONのライブでもおなじみのロカペニス。
このKiller-Bongという人はおそらく即興をやる方で、予めサンプラーに閉じ込めた膨大な料の元ネタをその場で曲に組み立てて、それにラップを載せていく。いわばその場でつくるヒップホップだ。(ただし既存の曲も演奏する。)ヒップホップというカルチャーで言うまでもなくサンプリングは重要な要素だから、実は基本に忠実なラップミュージックをプレイしているのだが、あまりこういうやり方を演る人というのは聞いたことが無い。元ネタはキックやハイハットなど単発のビートの部品、ジャズなどから引っ張ったピアノやホーンなどのリフなん小節か。これを組み合わせてあっという間にトラックを作っていく。Killer-Bongは低音の聞いた独特の声質をしていて、それが言葉の継ぎ目をあえて明確にしない、唸るようなラップをやっているものだから、おそらくリリックは日本語なのだろうが、よく聞こえない。ただ一本調子に呻吟するのではなく、節回しのようなラップも披露して、めっぽう格好良い。どうも酩酊しているようなトリップ感がある。そして自分の声すらその場でサンプリングしてオーバーダブを繰り返していく。ヒューマンビートボックスほど明快に音楽化されていないので、相当前衛的な仕上がりのトラックになる。この日は「うわあ〜、よんよんよん」みたいな叫び声をサンプリングして繰り返し流していた。
始まっていきなり卓をひっくり返すKiller-Bong。卓の上にはなみなみと注がれた飲み物があったのだが、機材と一緒にグチャー。スタッフが袖から何人も集まってきて必死に直しているのだが、本人は気にした様子もなくいま出る音で演奏し続ける。機材が壊れるのでは…とハラハラするが、本人はあまりそこら辺に頓着がないようだ。(なんかのインタビューで自分の部屋にものがほとんど何もない、と言っていたと思う。)マイクから音が出なければ叫び出す、というはっちゃけぶり。とにかく余裕のある人でトラブル感まったくなく、機材が元通りになってからも言葉を拾いながら演奏を続けていく。最後の方ではSimi LabのトラックメイカーHi'Specとの共作「やくそくのうた」を披露。リリックは変えてくるが、繰り返される「歌うんじゃねえ、ただ歌うんだ〜」というフレーズが即興的な自分のスタイルを象徴しているように思う。かっこよかった。
Skillkills
最後はこの日主役のSkillkills。名前はよく耳にするけど聴いたことないバンド。ドラム、ベース、ラップからなる三人組で、生音のヒップホップを演奏する。とにかくベーシストががっしりとした体躯に、横を刈り込んだ爆発頭にサングラスという出で立ちでよく目立つな〜と思った。見た目にパワーが有る。
三人のバンドだが、ビートの上に上モノを同期させる。”ラップ”ミュージックというくらいだから、トラックがすごくかっこよくてもやはりいちばん目立つのはラップなのだが、Skillkillsはバックトラックが(サンプリングに対して)ライブなのでその強みを活かしてよく動く、音も大きい。ただし「やかましいヒップホップ」という表現は半分しか当たってない。生で聴いてみるとその音のデカさにびっくりするものの、よくよく聴いてみるとやはりヒップホップに忠実であることもわかる。まずヒップホップなので音の数は決して多くない。例えばラップ・メタルなんかとは明確に異なる。Skillkillsの演奏はどこまでいってもヒップホップのトラックであり続ける。鳴らし方が違うだけだ。なのでビートは非常にタイトだ。この2つは人が演奏しているが、まさにマシンのようなタイトさ。この日Zazen Boysも激タイトだったが、あちらはバカテクが楽器それぞれ独立しているのになぜか一つの曲ができました、という感じだが、Skillkillsはドラムとベースの一体感が半端でない。日本の伝統建築のようにオーガニックな要素がガッチリはまって、粘りの強い強烈なビートを作り出している。Skillkillsも”間を抜”くことによってグルーヴのあるビートを生み出していて、特にドラムの人の「ここぞ」ってときの遅らせ方が絶妙。そこ絶対叩くよね?ってところを一つか2つ送らせてくるような感じ。とにかく気持ちよくて、前半の曲ははくの終わりを告げるシンバルのクラッシュが本当必殺!という感じだったし、後半シンバルメインの決めにスネアを叩く、というリフも非常にかっこよかった。
そしてここに乗るラップの正確さ!びっくりするくらいここもタイトに決めてくる。もっとルーズなのかと思ったが、たゆまぬ努力を感じさせる言葉のビートへの落とし方よ。ガチガチ合致する。それでいて即興要素をいれてリリックをいじってくる。これは気持ち良い。リリックも独自の世界観を構築するものでユーモアを交えつつ、一体感を煽ってくるポジティブさ。ロックフォーマットは良くも悪くもわかりやすく、感情の高まりをシャウトによって吐き出せるが、Skillkillsはずっとラップで感情をじわじわ上げてくる。フックもすごく格好良いが、フックのためのバースにならずにバースで上げてフックに持ち込むというヒップホップの格好良さがギュッと詰まった演奏だった。
途中のMCもシンプルかつ素直で本人たちがとても楽しい、という気持ちが伝わってくる良いものだった。今までのツアーでは(本人たちがいないので)できなかったという、Killer-Bong、それからZazenの向井さんを迎えた曲は一つのクライマックスでフロアが前にギュッと圧縮されていた。
結構思いつきでふらっと行ってしまったんだが非常に楽しかった。普段見ているジャンルとちょっと異なるのでそういった意味でも新鮮だった。Skillkillsの新作「The Shape of Dope to Come」を購入して帰宅。
Zazen Boysのライブが見たいというのが第一で、Skillkillsはよく目にするものの訊いたことも見たこともないバンドなのでこれは良い機会と思ったわけ。この日はSkillkillsの新作のリリースツアーのファイナル日。
なんとか仕事を放り出して会場に当日券で文字通り潜り込むと、Zazen Boysのライブがまさに始まったところだった。
Zazen Boys
ベーシストの吉田が今年限りで脱退することがアナウンスされたが、ステージングは落ち着いたものだった。照明をほぼ全開にしたステージは明るくそしてあけっぴろげであった。
私は30を半ばなのだから、思春期に洋楽の洗礼を受けてもNumber GirlとスーパーカーはOKという謎の方程式により、よくよくNumber Girlの音楽を聞いていた。(こういう輩は多いのでは。)初めて接したときの印象が強いのは音というよりMutomaJapanでみたフロントマン向井による手書きのMVの漫画テイストだったんだが。
このZazen Boysというのは完全に周囲とは隔たった音楽を追求するバンドで、私はこの手のジャンルに詳しくないのでよくわからないが、ロックをベースにプログレやファンクやジャズなどが引き合いに出されるようだ。(要するにNumber Girlとは異なる音楽性でそれ故私は少し敬遠していた。)
複雑ってことなのだが、音源聞いても分かる通り非常に肉体的な音楽だ。楽曲全体がリズムでできているようになっていて、相当ややこしいのだが私のような音楽的な知識がない輩でも踊りたくなっちゃうような音楽だ。生で見て思うのはとにかくZazen Boysの音楽は身軽である。難解になると技術の鎧がどんどん分厚くなるが、このバンドは音をどんどん抜いていっている。結果的に難解なリズムの骨組みのみが残っている。音の数は決して多くないが、余計に間が重要になってきてそしてそれらがとにかくきっちりあってくる。ドラム一つとっても今拍子はなんだろう?ってくらいで、楽器隊がそれぞれ別に何かやっているのが、何かわからんが偶然合っちゃって曲ができているような感じすらする。めちゃくちゃ緊張感があるのだが、ユーモアを交えたゆるさ(演奏以外の)があって、高尚な音楽にならずにあくまでも楽しい音楽にとどまり続ける。私が音源で聞いている曲も一回ばらばらにして再構築しているように、もはや別の曲では?というくらいの再現度。即興性も取り入れつつ、コールアンドレスポンスを取り込んだり(「Whisky&Unbubore」という曲、途中なんとなくNumber Girlの「Eight Beater」を彷彿とさせる)、酩酊の楽しさがにじみ出るようなステージングを進めていく。ステージの後ろの方でゆらゆら体をしているのが楽しかった。次はもっと前でみたいな。
Killer-Bong
続いてはBlack Smokerの首魁Killer-Bong。見るのは2回めで前回はコントラバス奏者とのコラボレーションだったので、単独を見るのは今回が初めて。
卓の上に据えられたサンプラー(?)2台位とマイクのみ。照明は落とされているが、プロジェクターを使った強烈な光線が暗闇を線上に切り裂いていく。この日のVJはENDONのライブでもおなじみのロカペニス。
このKiller-Bongという人はおそらく即興をやる方で、予めサンプラーに閉じ込めた膨大な料の元ネタをその場で曲に組み立てて、それにラップを載せていく。いわばその場でつくるヒップホップだ。(ただし既存の曲も演奏する。)ヒップホップというカルチャーで言うまでもなくサンプリングは重要な要素だから、実は基本に忠実なラップミュージックをプレイしているのだが、あまりこういうやり方を演る人というのは聞いたことが無い。元ネタはキックやハイハットなど単発のビートの部品、ジャズなどから引っ張ったピアノやホーンなどのリフなん小節か。これを組み合わせてあっという間にトラックを作っていく。Killer-Bongは低音の聞いた独特の声質をしていて、それが言葉の継ぎ目をあえて明確にしない、唸るようなラップをやっているものだから、おそらくリリックは日本語なのだろうが、よく聞こえない。ただ一本調子に呻吟するのではなく、節回しのようなラップも披露して、めっぽう格好良い。どうも酩酊しているようなトリップ感がある。そして自分の声すらその場でサンプリングしてオーバーダブを繰り返していく。ヒューマンビートボックスほど明快に音楽化されていないので、相当前衛的な仕上がりのトラックになる。この日は「うわあ〜、よんよんよん」みたいな叫び声をサンプリングして繰り返し流していた。
始まっていきなり卓をひっくり返すKiller-Bong。卓の上にはなみなみと注がれた飲み物があったのだが、機材と一緒にグチャー。スタッフが袖から何人も集まってきて必死に直しているのだが、本人は気にした様子もなくいま出る音で演奏し続ける。機材が壊れるのでは…とハラハラするが、本人はあまりそこら辺に頓着がないようだ。(なんかのインタビューで自分の部屋にものがほとんど何もない、と言っていたと思う。)マイクから音が出なければ叫び出す、というはっちゃけぶり。とにかく余裕のある人でトラブル感まったくなく、機材が元通りになってからも言葉を拾いながら演奏を続けていく。最後の方ではSimi LabのトラックメイカーHi'Specとの共作「やくそくのうた」を披露。リリックは変えてくるが、繰り返される「歌うんじゃねえ、ただ歌うんだ〜」というフレーズが即興的な自分のスタイルを象徴しているように思う。かっこよかった。
Skillkills
最後はこの日主役のSkillkills。名前はよく耳にするけど聴いたことないバンド。ドラム、ベース、ラップからなる三人組で、生音のヒップホップを演奏する。とにかくベーシストががっしりとした体躯に、横を刈り込んだ爆発頭にサングラスという出で立ちでよく目立つな〜と思った。見た目にパワーが有る。
三人のバンドだが、ビートの上に上モノを同期させる。”ラップ”ミュージックというくらいだから、トラックがすごくかっこよくてもやはりいちばん目立つのはラップなのだが、Skillkillsはバックトラックが(サンプリングに対して)ライブなのでその強みを活かしてよく動く、音も大きい。ただし「やかましいヒップホップ」という表現は半分しか当たってない。生で聴いてみるとその音のデカさにびっくりするものの、よくよく聴いてみるとやはりヒップホップに忠実であることもわかる。まずヒップホップなので音の数は決して多くない。例えばラップ・メタルなんかとは明確に異なる。Skillkillsの演奏はどこまでいってもヒップホップのトラックであり続ける。鳴らし方が違うだけだ。なのでビートは非常にタイトだ。この2つは人が演奏しているが、まさにマシンのようなタイトさ。この日Zazen Boysも激タイトだったが、あちらはバカテクが楽器それぞれ独立しているのになぜか一つの曲ができました、という感じだが、Skillkillsはドラムとベースの一体感が半端でない。日本の伝統建築のようにオーガニックな要素がガッチリはまって、粘りの強い強烈なビートを作り出している。Skillkillsも”間を抜”くことによってグルーヴのあるビートを生み出していて、特にドラムの人の「ここぞ」ってときの遅らせ方が絶妙。そこ絶対叩くよね?ってところを一つか2つ送らせてくるような感じ。とにかく気持ちよくて、前半の曲ははくの終わりを告げるシンバルのクラッシュが本当必殺!という感じだったし、後半シンバルメインの決めにスネアを叩く、というリフも非常にかっこよかった。
そしてここに乗るラップの正確さ!びっくりするくらいここもタイトに決めてくる。もっとルーズなのかと思ったが、たゆまぬ努力を感じさせる言葉のビートへの落とし方よ。ガチガチ合致する。それでいて即興要素をいれてリリックをいじってくる。これは気持ち良い。リリックも独自の世界観を構築するものでユーモアを交えつつ、一体感を煽ってくるポジティブさ。ロックフォーマットは良くも悪くもわかりやすく、感情の高まりをシャウトによって吐き出せるが、Skillkillsはずっとラップで感情をじわじわ上げてくる。フックもすごく格好良いが、フックのためのバースにならずにバースで上げてフックに持ち込むというヒップホップの格好良さがギュッと詰まった演奏だった。
途中のMCもシンプルかつ素直で本人たちがとても楽しい、という気持ちが伝わってくる良いものだった。今までのツアーでは(本人たちがいないので)できなかったという、Killer-Bong、それからZazenの向井さんを迎えた曲は一つのクライマックスでフロアが前にギュッと圧縮されていた。
結構思いつきでふらっと行ってしまったんだが非常に楽しかった。普段見ているジャンルとちょっと異なるのでそういった意味でも新鮮だった。Skillkillsの新作「The Shape of Dope to Come」を購入して帰宅。
ラベル:
Killer-Bong,
Skillkills,
ZAZEN BOYS,
オルタナティブ,
テクノ,
ヒップホップ,
ライブレポート,
音楽,
日本
2017年10月15日日曜日
UNSANE/Sterilize
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークのノイズロックバンドの8thアルバム。
2017年にSouthern Lord Recordsからリリースされた。
メンバーチェンジや活動休止などもありつつ1988年から一貫してノイズロックを鳴らし続けるバンドUNSANE。中心となるのは唯一のオリジナルメンバーでボーカルとギターを務めるChris Spencer。前作「Wreck」から5年ぶりの新作。オリジナルアルバムのカバーアートは常に血まみれで、今作でもそれは健在。
UNSANEを聴いてて思うのは彼らが演奏するノイズ・ロックというのは文字通り「うるさいロック」であって、ここでいうノイズと言うのはハーシュノイズに代表されるノイズミュージックとは一線を画す。ジャンルとしてのノイズと言うのは常にメイン、オーバーグラウンドに対するアンダーグラウンド、カウンターであって、それをロックやハードコアや、メタルなどに要素の一つとして取り込むやり方も今では珍しくない。今年リリースされた作品だけ見てもFull of Hell、本邦のENDONなどはノイズの影響を受けたうるさい(ロック)バンドだが、本質的なノイズ・ロックとは異なる。UNSANEの場合はそういった意味でのノイズは一切用いない。核となるのは骨太なロックで、芯が太く、ぶれない。ガッツリ硬質な音はオルタナティブ・ロック、メタルにとても良く似ている。例えばHelmetなんかには結構共通したものがあると思がもっとプリミティブだ。ノイズというのはブレみたいなものだから、かっちりしたそういったロックにノイズと言う形容詞をつけるのは面白いが、つまりは極端にうるさいのがUNSANE。
ガシャガシャした質感が残りつつも重量感のあるギター。それと対をなすカッチカチにハードに固めたベース。突っ走り勝ちになる危うさを溜めのある連撃で引き締めるドラム。そして飾りっ気がないが、真に迫ったシャウト主体のボーカル。曲速はミドルでだいたい3分程度。余計なものは一切なく、淡々とロックを演奏していく。ロックから派生したハードコア、メタルは先代の衣鉢を注ぎながら、着々と武器も増やして武装してきているが、UNSANEに関しては流石に音に関しては重たくそしてクリアだが、その他は基本的に装飾が殆ど無い。最小限のメンバーでいわば徒手空拳で勝負を挑んでくる。特にこの音源を聞いて思うのは、ある種のルーズさ。UNSANEより力強く、凶暴そうな音楽はほかにもあるが、UNSANEを聴いているとなんとも言えない居心地の悪さを感じるものだ。まずは不穏さが一つ。油をよくさした工業機械に囲まれているような、居心地の悪さ。そしてもう一つはシニカルなユーモアである。張り詰めているところは異常に張り詰めているのだが、どうも薄ら笑いのような酷薄さ、皮肉さ、空虚さがその背後にあってそれが熱量のある曲を同時に薄ら寒いものにしている。ここらへんはもうすぐ30年を戦い続けるベテランゆえの力配分の妙なのだろうか。
個人的には5曲目「Lung」から7曲目「Distance」までの中盤がたまらない。特に「Distance」はコーラスのところも良いが曲の最後になかなかつかみにくい感情がむき出しになっているようで震える。
ある意味ではノイズ+ロックの本命というか。オルタナティブ世代がかつての栄光の本質が死ぬどころか強靭に生き残り続けることに感涙の涙を流してもよし。最新鋭のサブカルとしてのノイズ世代が、ぶっというるささにぶん殴られて恍惚とした血の味を口の中に感じるのもよし。無慈悲な音に目がない人はぜひどうぞ。
2017年にSouthern Lord Recordsからリリースされた。
メンバーチェンジや活動休止などもありつつ1988年から一貫してノイズロックを鳴らし続けるバンドUNSANE。中心となるのは唯一のオリジナルメンバーでボーカルとギターを務めるChris Spencer。前作「Wreck」から5年ぶりの新作。オリジナルアルバムのカバーアートは常に血まみれで、今作でもそれは健在。
UNSANEを聴いてて思うのは彼らが演奏するノイズ・ロックというのは文字通り「うるさいロック」であって、ここでいうノイズと言うのはハーシュノイズに代表されるノイズミュージックとは一線を画す。ジャンルとしてのノイズと言うのは常にメイン、オーバーグラウンドに対するアンダーグラウンド、カウンターであって、それをロックやハードコアや、メタルなどに要素の一つとして取り込むやり方も今では珍しくない。今年リリースされた作品だけ見てもFull of Hell、本邦のENDONなどはノイズの影響を受けたうるさい(ロック)バンドだが、本質的なノイズ・ロックとは異なる。UNSANEの場合はそういった意味でのノイズは一切用いない。核となるのは骨太なロックで、芯が太く、ぶれない。ガッツリ硬質な音はオルタナティブ・ロック、メタルにとても良く似ている。例えばHelmetなんかには結構共通したものがあると思がもっとプリミティブだ。ノイズというのはブレみたいなものだから、かっちりしたそういったロックにノイズと言う形容詞をつけるのは面白いが、つまりは極端にうるさいのがUNSANE。
ガシャガシャした質感が残りつつも重量感のあるギター。それと対をなすカッチカチにハードに固めたベース。突っ走り勝ちになる危うさを溜めのある連撃で引き締めるドラム。そして飾りっ気がないが、真に迫ったシャウト主体のボーカル。曲速はミドルでだいたい3分程度。余計なものは一切なく、淡々とロックを演奏していく。ロックから派生したハードコア、メタルは先代の衣鉢を注ぎながら、着々と武器も増やして武装してきているが、UNSANEに関しては流石に音に関しては重たくそしてクリアだが、その他は基本的に装飾が殆ど無い。最小限のメンバーでいわば徒手空拳で勝負を挑んでくる。特にこの音源を聞いて思うのは、ある種のルーズさ。UNSANEより力強く、凶暴そうな音楽はほかにもあるが、UNSANEを聴いているとなんとも言えない居心地の悪さを感じるものだ。まずは不穏さが一つ。油をよくさした工業機械に囲まれているような、居心地の悪さ。そしてもう一つはシニカルなユーモアである。張り詰めているところは異常に張り詰めているのだが、どうも薄ら笑いのような酷薄さ、皮肉さ、空虚さがその背後にあってそれが熱量のある曲を同時に薄ら寒いものにしている。ここらへんはもうすぐ30年を戦い続けるベテランゆえの力配分の妙なのだろうか。
個人的には5曲目「Lung」から7曲目「Distance」までの中盤がたまらない。特に「Distance」はコーラスのところも良いが曲の最後になかなかつかみにくい感情がむき出しになっているようで震える。
ある意味ではノイズ+ロックの本命というか。オルタナティブ世代がかつての栄光の本質が死ぬどころか強靭に生き残り続けることに感涙の涙を流してもよし。最新鋭のサブカルとしてのノイズ世代が、ぶっというるささにぶん殴られて恍惚とした血の味を口の中に感じるのもよし。無慈悲な音に目がない人はぜひどうぞ。
Ben Frost/The Centre Cannot Hold
オーストラリアのメルボルン出身で今はアイスランドのレイキャビークを活動の拠点としているアーティストの5thアルバム。
2017年にMuteからリリースされた。
前作「A U R O R A」から3年ぶりのリリース。間には英国の作家イアン・バンクスによる小説「蜂工場」に影響を受けたコンセプトアルバム「The Wasp Factory」をリリースしているが、これは戯曲というか大胆にボーカルをフィーチャーした異色作になっている。今回はSteve Albiniがレーコでィングを担当している。アルバムに先立ち「Threshold of Faith」というEPもリリースしている。
私は前作「A U R O R A」から入った口で容赦のないノイズに同居する美しさ、いわば荘厳なノイズに痛く感動したものだった。今作もそんな彼の特色が遺憾なく発揮されているが、個人的には前作ほどわかり易い内容にはなっていないと思う。前作の路線を踏襲しつつ、より曖昧に抽象的になったのが今作という感じだろうか。ビリビリ震えながら流動的にその姿を変えていく、いわば生きている轟音、ハーシュノイズを中心に据えながら、黒い絵の具のように排他的ですべてをただ”ノイズ”一色に染め上げてしまう強烈なパワーを制御しつつ、別の要素を主役たるノイズの魅力を減じさせることなく同居させるのが彼の強みで、前作収録の「Nolan」などはノイズとほぼ融合したような凍てつくような美麗なメロディがガリガリとその実体感を増していく素晴らしい楽曲で、まさに魔術師たるBen Frostの魅力がつまりまくった曲だった。今作でもノイズ以外の要素に力を割いており、わかりやすいのはビートの導入、それからノイズにかぶさるメロディ、リフ、ぶれない輪郭を持った明確でソリッドの音使いなど。ノイズアーティストながらどこかしら透明感のあるような美しい風景を作り出してくる。それがあざといくらいの美しさ、メロディとは距離をおいたやはりどこか北の方の極寒の厳しさを同時にはらむコールドなもの、というところがまた良い。コールドかつ背後の美メロという意味ではやはりブラックメタルに通じるところがあるかもしれない。
今作は中盤を過ぎたあたりからノイズの登場頻度と言うか、使い方がちょっと変わってきて、ボリュームレベルを下げて底流に這わせるような使い方をしている。いわばノイズの氷塊がとけだしてそれ以外の要素が顕になっているわけで、そこにあるのは非常に繊細かつアンビエントな曖昧な世界であった。てっきりノイズがなければ美しさが残るかと思えば、果たしてそこにあったのはもっと曖昧ななにかであった。ドローンめいた、僅かな光のような。相反するものをぶつけることがBen Frostの醍醐味かと勝手に解釈していたが、どうやらそれは違うらしく、この人は足し算というよりは掛け算で曲を作っているのだろう。
今作では緩急をつけることでまた新しいことをやっている。とにかくうるさいのがノイズでしょ〜というとちょっと驚くかもしれないが、一旦自分の曲をバラバラにして要素を一つ一つ吟味した上で再構築しているような、チャレンジ精神を感じる。そういった意味ではやや実験的な内容になっているかもしれない。曲単位で見れば彼の醍醐味が遺憾なく発揮されている曲もあるので、前作が気に入った人なら大丈夫だと思う。
2017年にMuteからリリースされた。
前作「A U R O R A」から3年ぶりのリリース。間には英国の作家イアン・バンクスによる小説「蜂工場」に影響を受けたコンセプトアルバム「The Wasp Factory」をリリースしているが、これは戯曲というか大胆にボーカルをフィーチャーした異色作になっている。今回はSteve Albiniがレーコでィングを担当している。アルバムに先立ち「Threshold of Faith」というEPもリリースしている。
私は前作「A U R O R A」から入った口で容赦のないノイズに同居する美しさ、いわば荘厳なノイズに痛く感動したものだった。今作もそんな彼の特色が遺憾なく発揮されているが、個人的には前作ほどわかり易い内容にはなっていないと思う。前作の路線を踏襲しつつ、より曖昧に抽象的になったのが今作という感じだろうか。ビリビリ震えながら流動的にその姿を変えていく、いわば生きている轟音、ハーシュノイズを中心に据えながら、黒い絵の具のように排他的ですべてをただ”ノイズ”一色に染め上げてしまう強烈なパワーを制御しつつ、別の要素を主役たるノイズの魅力を減じさせることなく同居させるのが彼の強みで、前作収録の「Nolan」などはノイズとほぼ融合したような凍てつくような美麗なメロディがガリガリとその実体感を増していく素晴らしい楽曲で、まさに魔術師たるBen Frostの魅力がつまりまくった曲だった。今作でもノイズ以外の要素に力を割いており、わかりやすいのはビートの導入、それからノイズにかぶさるメロディ、リフ、ぶれない輪郭を持った明確でソリッドの音使いなど。ノイズアーティストながらどこかしら透明感のあるような美しい風景を作り出してくる。それがあざといくらいの美しさ、メロディとは距離をおいたやはりどこか北の方の極寒の厳しさを同時にはらむコールドなもの、というところがまた良い。コールドかつ背後の美メロという意味ではやはりブラックメタルに通じるところがあるかもしれない。
今作は中盤を過ぎたあたりからノイズの登場頻度と言うか、使い方がちょっと変わってきて、ボリュームレベルを下げて底流に這わせるような使い方をしている。いわばノイズの氷塊がとけだしてそれ以外の要素が顕になっているわけで、そこにあるのは非常に繊細かつアンビエントな曖昧な世界であった。てっきりノイズがなければ美しさが残るかと思えば、果たしてそこにあったのはもっと曖昧ななにかであった。ドローンめいた、僅かな光のような。相反するものをぶつけることがBen Frostの醍醐味かと勝手に解釈していたが、どうやらそれは違うらしく、この人は足し算というよりは掛け算で曲を作っているのだろう。
今作では緩急をつけることでまた新しいことをやっている。とにかくうるさいのがノイズでしょ〜というとちょっと驚くかもしれないが、一旦自分の曲をバラバラにして要素を一つ一つ吟味した上で再構築しているような、チャレンジ精神を感じる。そういった意味ではやや実験的な内容になっているかもしれない。曲単位で見れば彼の醍醐味が遺憾なく発揮されている曲もあるので、前作が気に入った人なら大丈夫だと思う。
2017年10月11日水曜日
Various Artists/ろくろ
日本のレーベルLongLegsLongArms Recordsのコンピレーションアルバム。2017年に同レーベルからリリースされた。
参加しているアーティストと収録曲は以下の通り。(レーベルHPからコピペ。)
1. ILIAS - 存在と理由
2. The Donor - Kagerou
3. KUGURIDO - 桃源郷夜想曲
4. KLONNS - KNIVES
5. KLONNS - SODOM
6. SWARRRM - march
7. unfaded - 漆黒
8. PRIZE OF RUST - Decade
9. PRIZE OF RUST - Spectator
10. ENSLAVE - Killing Me Softly
11. Pterion - Schwein
12. ungodly - 蝕
13. Yvonxhe - Incessant Mournful Tale
14. Vertraft - MEMORIZE
すべて日本のバンドで、バンドの活動拠点は東京、関東にとどまらず関西・金沢・四国と様々。レーベルオーナーが実際にあったバンドからセレクトされている。
LongLegsLongArms Recordsは主にハードコアを取り扱うレーベルだが、主にネオクラストと呼ばれるジャンルをメインに紹介している。ハードコアのなかのサブジャンル、クラスト(コア)のさらにサブジャンルであるネオクラストだからまあ結構マニアックな音楽だと思う。このネオクラストというのが(個人的には)かなり難しいジャンルで説明するのが難しい。説明する時に「ブラッケンド」「激情」「クラスト」「エモ」「エモバイオレンス」なんかの単語を使うとうまくいくような気がする。そんなに歴史のあるジャンルではないと思うので、おそらく私だけでなく演奏する方も難しいな〜とは思っているのではなかろうか。というのも真性のネオクラストバンドというのはまだ日本にはそうそういないのではなかろうか。この音源だとネオクラストを自称している(=明確に指向している)バンドは多分姫路のKUGURIDOだけではなかろうか。その他のバンドはネオクラストという言葉が浸透する前にそういった音楽をやっていたバンド、要素としてネオクラストを取り込んでいるバンド、一聴したところ(ネオ)クラスト感のあまりなさそうなバンドなど。おそらくより浸透性のあるジャンルで言うと、ハードコア、ニュースクール、カオティック、グラインド、ブラックメタル、エモバイオレンス、激情などにカテゴライズされるのではなかろうか。要するにその中にネオクラストの影響(意図的なものと無意識的なもの、両方)を感じ取ったレーベルが、少なくとも日本では未だ黎明期にあるネオクラストシーンにこれだ!と押すのがこのコンピレーションなのではと個人的には思う。まだ良くも悪くも混沌としているネオクラストという概念をそれを取り巻く周辺含めてすくい取ったのがこの「ろくろ」という一つの音源なのではなかろうかと。
レーベルはサンプラーと称してそれに所属するバンドを紹介する音源を作ることがあるが、まさにこの「ろくろ」は紹介する意味合いが強い。(ただ既存の曲を集めたわけではないからサンプラーとは呼べないだろうが。)全部で4万字を超える各バンドへのインタビューもその紹介、もっというと収録するバンドを理解し、咀嚼してそれを第三者(リスナー)に伝えようというレーベル姿勢の表れと見て取ることができる。(私の感想は作品を理解しようという試みなので(つまり読書感想文と同じ一つの解釈にしかならないのです。)、こういった姿勢は非常に共感できるのです。)
収録されている音を聴いてみると前述のような状況なので統一感がありつつもバリエーションの有る個性的な音楽が矢継ぎ早に展開される。(おおむね1曲あたりの収録時間は短め。)ニュースクール・ハードコアに日本なりのハードコアの伝統を融合させた音、ブラックメタルの影響色濃いいわゆるブラッケンドと称されるハードコア、もはやブラックメタルにしか聞こえないブラックメタルなど。このオムニバスの面白いところのもう一つは全国から収録バンドを集めたこと。音楽を語る上で切っても切れないのが”シーン”という言葉だけど、これが横というか平面上で語られるのが地域で、もはや結線されてもいないネットで結ばれた社会では情報が均質化されるが、それでも地方ごとのシーンというものは健在であるようである。その地方ごとの特色がきっとバンドの出す音に表れているのであろう。一言に激情と言ってもテンプレート的な激情の影響を収録曲に見出すことは困難である。(バンドの個性なのかシーンの特色なのかはちょっと判断できないのだけど。)
レーベル名は足長手長(手長足長とも)という妖怪なので「ろくろ」ときくと「これはろくろっ首のことに違いない!」と早合点したのだが、どうも陶芸を作るときのろくろという意味もあるらしい。面白いと思ったのは新しいものを作る際にはたいてい土を捏ねる、という言い方をするが、ろくろはある程度形になっているものを整形するのに使う。多分日本でのネオクラストの土台はである程度出来上がったので、3LAとしてはそれを集めて形を整え、全国にお届けするよ、ということなのだろう。「ネオクラストはわしが育てた」という居丈高の態度ではないのが非常に謙虚だと思う。
まだこれからのジャンルだと思うので、耳が早いひとはチェックしてみると面白いのではなかろうか。降って湧いた進行ジャンルではなく、静かに進行した音楽的傾向を「ネオクラスト」としてすくい取ったイメージだ。なので妙な作為性や違和感は皆無である。
参加しているアーティストと収録曲は以下の通り。(レーベルHPからコピペ。)
1. ILIAS - 存在と理由
2. The Donor - Kagerou
3. KUGURIDO - 桃源郷夜想曲
4. KLONNS - KNIVES
5. KLONNS - SODOM
6. SWARRRM - march
7. unfaded - 漆黒
8. PRIZE OF RUST - Decade
9. PRIZE OF RUST - Spectator
10. ENSLAVE - Killing Me Softly
11. Pterion - Schwein
12. ungodly - 蝕
13. Yvonxhe - Incessant Mournful Tale
14. Vertraft - MEMORIZE
すべて日本のバンドで、バンドの活動拠点は東京、関東にとどまらず関西・金沢・四国と様々。レーベルオーナーが実際にあったバンドからセレクトされている。
LongLegsLongArms Recordsは主にハードコアを取り扱うレーベルだが、主にネオクラストと呼ばれるジャンルをメインに紹介している。ハードコアのなかのサブジャンル、クラスト(コア)のさらにサブジャンルであるネオクラストだからまあ結構マニアックな音楽だと思う。このネオクラストというのが(個人的には)かなり難しいジャンルで説明するのが難しい。説明する時に「ブラッケンド」「激情」「クラスト」「エモ」「エモバイオレンス」なんかの単語を使うとうまくいくような気がする。そんなに歴史のあるジャンルではないと思うので、おそらく私だけでなく演奏する方も難しいな〜とは思っているのではなかろうか。というのも真性のネオクラストバンドというのはまだ日本にはそうそういないのではなかろうか。この音源だとネオクラストを自称している(=明確に指向している)バンドは多分姫路のKUGURIDOだけではなかろうか。その他のバンドはネオクラストという言葉が浸透する前にそういった音楽をやっていたバンド、要素としてネオクラストを取り込んでいるバンド、一聴したところ(ネオ)クラスト感のあまりなさそうなバンドなど。おそらくより浸透性のあるジャンルで言うと、ハードコア、ニュースクール、カオティック、グラインド、ブラックメタル、エモバイオレンス、激情などにカテゴライズされるのではなかろうか。要するにその中にネオクラストの影響(意図的なものと無意識的なもの、両方)を感じ取ったレーベルが、少なくとも日本では未だ黎明期にあるネオクラストシーンにこれだ!と押すのがこのコンピレーションなのではと個人的には思う。まだ良くも悪くも混沌としているネオクラストという概念をそれを取り巻く周辺含めてすくい取ったのがこの「ろくろ」という一つの音源なのではなかろうかと。
レーベルはサンプラーと称してそれに所属するバンドを紹介する音源を作ることがあるが、まさにこの「ろくろ」は紹介する意味合いが強い。(ただ既存の曲を集めたわけではないからサンプラーとは呼べないだろうが。)全部で4万字を超える各バンドへのインタビューもその紹介、もっというと収録するバンドを理解し、咀嚼してそれを第三者(リスナー)に伝えようというレーベル姿勢の表れと見て取ることができる。(私の感想は作品を理解しようという試みなので(つまり読書感想文と同じ一つの解釈にしかならないのです。)、こういった姿勢は非常に共感できるのです。)
収録されている音を聴いてみると前述のような状況なので統一感がありつつもバリエーションの有る個性的な音楽が矢継ぎ早に展開される。(おおむね1曲あたりの収録時間は短め。)ニュースクール・ハードコアに日本なりのハードコアの伝統を融合させた音、ブラックメタルの影響色濃いいわゆるブラッケンドと称されるハードコア、もはやブラックメタルにしか聞こえないブラックメタルなど。このオムニバスの面白いところのもう一つは全国から収録バンドを集めたこと。音楽を語る上で切っても切れないのが”シーン”という言葉だけど、これが横というか平面上で語られるのが地域で、もはや結線されてもいないネットで結ばれた社会では情報が均質化されるが、それでも地方ごとのシーンというものは健在であるようである。その地方ごとの特色がきっとバンドの出す音に表れているのであろう。一言に激情と言ってもテンプレート的な激情の影響を収録曲に見出すことは困難である。(バンドの個性なのかシーンの特色なのかはちょっと判断できないのだけど。)
レーベル名は足長手長(手長足長とも)という妖怪なので「ろくろ」ときくと「これはろくろっ首のことに違いない!」と早合点したのだが、どうも陶芸を作るときのろくろという意味もあるらしい。面白いと思ったのは新しいものを作る際にはたいてい土を捏ねる、という言い方をするが、ろくろはある程度形になっているものを整形するのに使う。多分日本でのネオクラストの土台はである程度出来上がったので、3LAとしてはそれを集めて形を整え、全国にお届けするよ、ということなのだろう。「ネオクラストはわしが育てた」という居丈高の態度ではないのが非常に謙虚だと思う。
まだこれからのジャンルだと思うので、耳が早いひとはチェックしてみると面白いのではなかろうか。降って湧いた進行ジャンルではなく、静かに進行した音楽的傾向を「ネオクラスト」としてすくい取ったイメージだ。なので妙な作為性や違和感は皆無である。
3LA-LongLegsLongArms Records-Presents『ろくろ』@新宿Nine Spices
よくあることなんだけど10月8日は面白そうなライブがかぶって困る日だった。そんな中でも足を運んだのはこちら。このライブは日本のLongLegsLongArms Recordsが主催するもので、先日リリースされたレーベル初めてのコンピレーションアルバムの発売を記念してのもの。アルバムに曲を提供しているアーティストが出演する。さすがにアルバム収録全アーティストとは行かないが、出演陣は下記の通り。
PRIZE OF RUST (茨城)
ungodly (香川)
unfaded (奈良)
SWARRRM (神戸)
ILIAS (神奈川)
ご覧の通り東京のバンドが一つしかない。奈良、神戸、京都、香川と普段はなかなか見れないような地域で活動しているバンドが名を連ねており、それならこの機会に見るべき!と思ったわけ。もちろんコンピレーションアルバム「ろくろ」の内容が素晴らしいことも理由の一つ。
この日会場のSEではHelmetが流れていた。アメリカのオルタナティブ・ロック(メタル)バンドである。この3LAというレーベルは一風変わったハードコアを世に紹介するレーベルで、もう一つの可能性という意味で「オルタナティブ」という言葉がよく似合う。その集大成の一つが日本全国からバンドを集めて作った「ろくろ」なわけで、それが眼前で見れるということで期待が高まる。
例によって道に迷ったので(馴染みのない駅を使うとかならずぜんぜん違う出口を選択するのが私)私がおっとり刀で会場にたどり着くとすでに一番手が始まっているところだった。
PRIZE OF RUST
茨城(いばらき)のハードコアバンド。この間見たときも同じ3LA企画でやはり同じ会場だった。4人組のバンドでコンピレーションアルバムでもお気に入りだったので二回目に見るのが楽しみだった。改めてライブで見るとニュースークール・ハードコア!という感じ。音が非常にゴツゴツしている。音が非常にメタリックで、ミュートを使った刻み込んでくるリフをあまり多様せず、滑らかにつややかなリフを弾きまくる。このリフが非常にメロディックで、ツインボーカルはシャウトしかしないのでその対比が本当に”叙情的”という感じ。低音低速で力任せにぶん回すモッシュパートみたいなのもあって非常に暴力的だが、歌詞は多分日本語で、モッシュ用ハードコア(それはそれで好きだけど)ではなくて訴えかける何かがある。マイクにかぶりつくように歌う様もそうだが、前のめりにメッセージ性がある感じは日本の激情系からの流れを感じさせる。個人的には日本ならではのニュースクール・ハードコアという感じで、どうしても悩みすぎている激情に比較すると、懊悩はあるけどアクセルを踏み切っているような潔さが魅力。重量感があるけど滑るようなメロディアスなリフを低音で急ブレーキ掛けるところが非常にかっこよかった。
ungodly (香川)
続いては香川のバンド3ピースでボーカルの方がボーカルを取る。「ろくろ」収録の曲しか知らないものでどんな音なのか?白塗りにしている動画があったようだしブラックメタルよりの(ブラッケンドな)ハードコアかな?と思っていたら、結構想像と違った。まずはリフの音の数が多い。刻みまくるような密度濃く詰め込んだリフは、相当テクニカルでかっちりしたスラッシュの影響色濃いデス/ブラックだった。トレモロにそこまで比重をおいているわけではないというか、印象ではもっと刻みまくっていたようなのでボーカルの喉に引っ掛けるようなイーヴィルなシャウト意外はわかりやすいブラックメタルの要素はないし、塊をぶん回すのがハードコアの真髄の一つだとするとそういった意味ではハードコア感はほぼない。ただ(間違っているかもだが)ドラムはツービート主体だったり、曲もアルペジオをなどを効果的に導入しつつ起伏に飛んでいるが、ダラダラ長くないし、あまり耽美/アーティステックな雰囲気もしないので終始殺伐としてて個人的にはそこが良かった。
unfaded (奈良)
つづいては奈良のバンドで、MCでいっていたのだが10年位は活動しているが県外でライブをするのは2回めで東京はこの日が初めてだったらしい。「ろくろ」ではとにかく攻撃的でメロディアスな楽曲がかっこよかったのでこの日楽しみだった。
スリーピースで基本的にギタリストの方がボーカルを取る。この日一番”激情”という感じだったのでなかろうか。内省的な歌詞をうずまきのような轟音にのせて送り出すあのスタイルである。ただいわゆる激情というよりはむしろエモバイオレンスという感じで、具体的には激情でありがちな静かなパートは必要最小限にとどめて勢いとスピードを殺さないように、そして飾らないシンプルさでほとばしる激情を披露していた。歌詞に関しては演奏の合間に吐き出す、というようなスタイルで演奏のよく練られた細やかさが感じられた。うるさいバンドだが、なんとなく寡黙でいぶし銀なスタイル。ギタリストの方はDeath SideのT-シャツを着ていたが、envyからの激情というよりはむしろジャパニーズ・ハードコアの流れを強く感じた。音源を購入したのだがシンプルだが力強い歌詞も勿体つけない音楽性とあいまってシンプルかつ力強いハードコアの進化系という方がしっくり来る。ドラムがやたらと印象的だった。
SWARRRM (神戸)
曲が始まってみるとこの日一番ブラックメタルだった、というか完全にブラックメタルだ。ギタリストの一人は多分7弦ギターで、ベーシストと三人で相当テクニカルなリフを矢継ぎ早に繰り出していく。ミュートも使いながらも主体となるのはブラックメタル然としたトレモロを主体としたリフで、不穏なアルペジオや低速パートを使いながら自らの持ち味である激速トレモロパートに持ち込んでいくスタイル。面白いのは「ろくろ」ではYvonxheなんかはアンダーグラウンドなブラックメタルだったが、このPterionに関しては曲に起伏があるし、ドラスティックな曲作りをしていて結構メジャー感というか、そういう感じがあって面白かった。多分メンバーはまだすごく若いと思うが、あまり動かないメンバーに対してボーカリストの人は声にバリエーションがあるし、動きも派手。面白かった。
KLONNS (東京)
つづいては唯一の東京のバンド。ライブを見るのは2回め。ブラッケンドとは距離をおいている的なインタビューが面白かったが、たしかに音源を聞いてみてもライブを見てもバンドの核はハードコアな感じ。メンバー全員が黒い服に身を包みスタイリッシュ。
ぬろぬろ動き回るベースがかっこいいのだが相当な轟音でとにかくやかましい。ドラムもとにかく叩きまくりで、ギターとボーカルには強烈なリバーブ効果がかけられており、特にギターは音がでかい。非常にノイジーだが、例えばノイズ専用の装置を使っていないところなどあくまでもハードコアで勝負という姿勢の現れだろうか。曲も基本的にはシンプルな構成で、たまにギターソロなどを挟むもののほぼ一直線で進行するオールドスクールスタイル。ボーカルも歌うというよりは要所要所に吐き捨てて置いていく、のような歌唱方法。ステージを降りてきて客席に突っ込むという場面もあり、この日一風変わったバンドが多い中で一番やかましく、一番肉体的だったのがこのKLONNSだったと思う。
ILIAS (神奈川)
トリを飾るのはコンピレーションの冒頭を飾るILIAS。ライブを見るのは初めて。専任ボーカルにギタリスト二人を擁する5人組。「存在と理由」というタイトルの1曲からはいわゆる激情系かとおもっていたが、ライブで見るともっと、というかだいぶかっちりとしたハードコアだった。ニュースクールや日本の激情を巻き込んだバランスの音で、ハードコアなりの強面感と叙情感を勢いを殺さずに取り込んでいる。曲によってはガッツガッツした暴れるパートとドラスティックと言っていいくらいのトレモロい叙情的なパートが奇妙に同居している両極端さが魅力的。この日のバンド概ねそうだが、このバンドも激情というよりは絵もバイオレンスという感じで、冗長とした感じは皆無。ボーカルの人のちょっとかすれた歌唱法もあって、場面によってはkhmerの新作がちらっと頭をよぎった。ブラッケンド感は皆無だし、一聴したところクラスト感もそこまで感じられないのだが、(MCでもあったが)あとからそのような流れを聴いて影響を受けたのかもしれない。
この日唯一のMCをちゃんとするバンドでポジティブなメッセージが印象的だった。
音楽を本当に好きな人は国や州、県、など地域で音楽を語り、そのときは所々の「シーン」という言葉が出てくる。今少なくとも日本を含めた先進国だとおおよそインターネットを通じて均等に音楽の昨今を知ることができるが、それでもやはり地方ごとのシーンが出来上がるのは面白い。(すべてが均質化されているならそもそもシーンと言う言葉がなくなるはずだ。)先輩からの伝統だったり、内輪での流行り廃りだったり、きっとそういうものが積み上がって地域ごとの差を生み出しているのだろう。別に全国からバンドを集めようというコンセプトではないだろうが、結果的に「ろくろ」というコンピレーションには相通じる要素を通して全国のバンドが名を連ねたわけで、この日はそんな各所のシーンを垣間見れて面白かった。出演者の皆様はわざわざ遠いところありがとうございました。
Prize of RustとUnfaded、それからungodlyの音源を買って帰宅。
PRIZE OF RUST (茨城)
ungodly (香川)
unfaded (奈良)
SWARRRM (神戸)
Pterion (京都)
KLONNS (東京)ILIAS (神奈川)
ご覧の通り東京のバンドが一つしかない。奈良、神戸、京都、香川と普段はなかなか見れないような地域で活動しているバンドが名を連ねており、それならこの機会に見るべき!と思ったわけ。もちろんコンピレーションアルバム「ろくろ」の内容が素晴らしいことも理由の一つ。
この日会場のSEではHelmetが流れていた。アメリカのオルタナティブ・ロック(メタル)バンドである。この3LAというレーベルは一風変わったハードコアを世に紹介するレーベルで、もう一つの可能性という意味で「オルタナティブ」という言葉がよく似合う。その集大成の一つが日本全国からバンドを集めて作った「ろくろ」なわけで、それが眼前で見れるということで期待が高まる。
例によって道に迷ったので(馴染みのない駅を使うとかならずぜんぜん違う出口を選択するのが私)私がおっとり刀で会場にたどり着くとすでに一番手が始まっているところだった。
PRIZE OF RUST
茨城(いばらき)のハードコアバンド。この間見たときも同じ3LA企画でやはり同じ会場だった。4人組のバンドでコンピレーションアルバムでもお気に入りだったので二回目に見るのが楽しみだった。改めてライブで見るとニュースークール・ハードコア!という感じ。音が非常にゴツゴツしている。音が非常にメタリックで、ミュートを使った刻み込んでくるリフをあまり多様せず、滑らかにつややかなリフを弾きまくる。このリフが非常にメロディックで、ツインボーカルはシャウトしかしないのでその対比が本当に”叙情的”という感じ。低音低速で力任せにぶん回すモッシュパートみたいなのもあって非常に暴力的だが、歌詞は多分日本語で、モッシュ用ハードコア(それはそれで好きだけど)ではなくて訴えかける何かがある。マイクにかぶりつくように歌う様もそうだが、前のめりにメッセージ性がある感じは日本の激情系からの流れを感じさせる。個人的には日本ならではのニュースクール・ハードコアという感じで、どうしても悩みすぎている激情に比較すると、懊悩はあるけどアクセルを踏み切っているような潔さが魅力。重量感があるけど滑るようなメロディアスなリフを低音で急ブレーキ掛けるところが非常にかっこよかった。
ungodly (香川)
続いては香川のバンド3ピースでボーカルの方がボーカルを取る。「ろくろ」収録の曲しか知らないものでどんな音なのか?白塗りにしている動画があったようだしブラックメタルよりの(ブラッケンドな)ハードコアかな?と思っていたら、結構想像と違った。まずはリフの音の数が多い。刻みまくるような密度濃く詰め込んだリフは、相当テクニカルでかっちりしたスラッシュの影響色濃いデス/ブラックだった。トレモロにそこまで比重をおいているわけではないというか、印象ではもっと刻みまくっていたようなのでボーカルの喉に引っ掛けるようなイーヴィルなシャウト意外はわかりやすいブラックメタルの要素はないし、塊をぶん回すのがハードコアの真髄の一つだとするとそういった意味ではハードコア感はほぼない。ただ(間違っているかもだが)ドラムはツービート主体だったり、曲もアルペジオをなどを効果的に導入しつつ起伏に飛んでいるが、ダラダラ長くないし、あまり耽美/アーティステックな雰囲気もしないので終始殺伐としてて個人的にはそこが良かった。
unfaded (奈良)
つづいては奈良のバンドで、MCでいっていたのだが10年位は活動しているが県外でライブをするのは2回めで東京はこの日が初めてだったらしい。「ろくろ」ではとにかく攻撃的でメロディアスな楽曲がかっこよかったのでこの日楽しみだった。
スリーピースで基本的にギタリストの方がボーカルを取る。この日一番”激情”という感じだったのでなかろうか。内省的な歌詞をうずまきのような轟音にのせて送り出すあのスタイルである。ただいわゆる激情というよりはむしろエモバイオレンスという感じで、具体的には激情でありがちな静かなパートは必要最小限にとどめて勢いとスピードを殺さないように、そして飾らないシンプルさでほとばしる激情を披露していた。歌詞に関しては演奏の合間に吐き出す、というようなスタイルで演奏のよく練られた細やかさが感じられた。うるさいバンドだが、なんとなく寡黙でいぶし銀なスタイル。ギタリストの方はDeath SideのT-シャツを着ていたが、envyからの激情というよりはむしろジャパニーズ・ハードコアの流れを強く感じた。音源を購入したのだがシンプルだが力強い歌詞も勿体つけない音楽性とあいまってシンプルかつ力強いハードコアの進化系という方がしっくり来る。ドラムがやたらと印象的だった。
SWARRRM (神戸)
続いては「カオス&グラインド」を掲げるSWARRRM。この日は冒頭から激速で一気に耳目を集め、そこから「幸あれ」、そしてkillieとのスプリット音源から「愛のうた」「あなたにだかれこわれはじめる」、ろくろ収録の「March」と大胆に歌を取り込んだバンドの昨今を披露していく。「カオス&グラインド」とは単なるスローガンではなく1曲に1回はブラストビートを入れる、という厳格なルールでもある。このバンドは常に何かに挑戦しているように個人的には感じられる。すべての曲はそれ自体完成品だが、同時に何かに対する一つの試行錯誤の結果に見れる。バンドとしての挑戦の結果が曲として残っているようなイメージだ。常に高みに、だから孤高のバンドと呼ばれるし、目下最新アルバム「Flower」以降での大胆な歌へのアプローチも単純なセルアウトとは絶対解釈されようがない。ルールと言うのは縛るものだが、他のバンドが良くも悪くもとどまり続けるフィールドを、SWARRRMはルールを使ってあっさり(はたからそう見えるだけで実際には苦労を重ねた末にだと思うが)乗り越えていく。ビリビリ震えた。
Pterion (京都)
つづいては京都のバンド。このコンピで初めて知ったのでバンドの情報については殆ど知らなかった。(結成は2017年ということもあり。)5人組でボーカルは専任。ボーカル以外は顔を白く塗っている。ボーカルがガッチリした体躯に編み上げブーツを履き込んで一人だけ素顔を晒している。他のメンバーは顔を塗っているものの服装は結構バラバラでなかなか作為が読み取りにくいスタイルで面白い。曲が始まってみるとこの日一番ブラックメタルだった、というか完全にブラックメタルだ。ギタリストの一人は多分7弦ギターで、ベーシストと三人で相当テクニカルなリフを矢継ぎ早に繰り出していく。ミュートも使いながらも主体となるのはブラックメタル然としたトレモロを主体としたリフで、不穏なアルペジオや低速パートを使いながら自らの持ち味である激速トレモロパートに持ち込んでいくスタイル。面白いのは「ろくろ」ではYvonxheなんかはアンダーグラウンドなブラックメタルだったが、このPterionに関しては曲に起伏があるし、ドラスティックな曲作りをしていて結構メジャー感というか、そういう感じがあって面白かった。多分メンバーはまだすごく若いと思うが、あまり動かないメンバーに対してボーカリストの人は声にバリエーションがあるし、動きも派手。面白かった。
KLONNS (東京)
つづいては唯一の東京のバンド。ライブを見るのは2回め。ブラッケンドとは距離をおいている的なインタビューが面白かったが、たしかに音源を聞いてみてもライブを見てもバンドの核はハードコアな感じ。メンバー全員が黒い服に身を包みスタイリッシュ。
ぬろぬろ動き回るベースがかっこいいのだが相当な轟音でとにかくやかましい。ドラムもとにかく叩きまくりで、ギターとボーカルには強烈なリバーブ効果がかけられており、特にギターは音がでかい。非常にノイジーだが、例えばノイズ専用の装置を使っていないところなどあくまでもハードコアで勝負という姿勢の現れだろうか。曲も基本的にはシンプルな構成で、たまにギターソロなどを挟むもののほぼ一直線で進行するオールドスクールスタイル。ボーカルも歌うというよりは要所要所に吐き捨てて置いていく、のような歌唱方法。ステージを降りてきて客席に突っ込むという場面もあり、この日一風変わったバンドが多い中で一番やかましく、一番肉体的だったのがこのKLONNSだったと思う。
ILIAS (神奈川)
トリを飾るのはコンピレーションの冒頭を飾るILIAS。ライブを見るのは初めて。専任ボーカルにギタリスト二人を擁する5人組。「存在と理由」というタイトルの1曲からはいわゆる激情系かとおもっていたが、ライブで見るともっと、というかだいぶかっちりとしたハードコアだった。ニュースクールや日本の激情を巻き込んだバランスの音で、ハードコアなりの強面感と叙情感を勢いを殺さずに取り込んでいる。曲によってはガッツガッツした暴れるパートとドラスティックと言っていいくらいのトレモロい叙情的なパートが奇妙に同居している両極端さが魅力的。この日のバンド概ねそうだが、このバンドも激情というよりは絵もバイオレンスという感じで、冗長とした感じは皆無。ボーカルの人のちょっとかすれた歌唱法もあって、場面によってはkhmerの新作がちらっと頭をよぎった。ブラッケンド感は皆無だし、一聴したところクラスト感もそこまで感じられないのだが、(MCでもあったが)あとからそのような流れを聴いて影響を受けたのかもしれない。
この日唯一のMCをちゃんとするバンドでポジティブなメッセージが印象的だった。
音楽を本当に好きな人は国や州、県、など地域で音楽を語り、そのときは所々の「シーン」という言葉が出てくる。今少なくとも日本を含めた先進国だとおおよそインターネットを通じて均等に音楽の昨今を知ることができるが、それでもやはり地方ごとのシーンが出来上がるのは面白い。(すべてが均質化されているならそもそもシーンと言う言葉がなくなるはずだ。)先輩からの伝統だったり、内輪での流行り廃りだったり、きっとそういうものが積み上がって地域ごとの差を生み出しているのだろう。別に全国からバンドを集めようというコンセプトではないだろうが、結果的に「ろくろ」というコンピレーションには相通じる要素を通して全国のバンドが名を連ねたわけで、この日はそんな各所のシーンを垣間見れて面白かった。出演者の皆様はわざわざ遠いところありがとうございました。
Prize of RustとUnfaded、それからungodlyの音源を買って帰宅。
登録:
コメント (Atom)